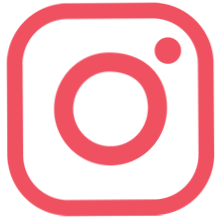学校苦手!だけど人は好き!はADHDキッズあるある
我が家の息子はADHDです。
現在11歳になりますが人は大好きだけどみんな一緒に活動が疲れてしまい、学校が苦手になりつつあります。
これって実は息子だけの話ではなくADHDキッズあるあるな話なんです。
ADHDキッズのヘェ〜っていう特徴をご存知ですか?
それは『人が好き』ということです。
大きくうなづいてるお母さんも多いかなと思います^^;
人が好きだからとっても人懐っこいし明るさもあるから好かれます^^
そして基本的にお友達大好き!な子が多く、小さい頃は学校も好きな子が多いです^^

けれども、学校は学校。大人にとっては勉強する場所という概念が頭にありますし、実際勉強する時間が大半を占めています。
そして特に日本は椅子に座って前を向いて先生の話を聞くのが当たり前…。
みんなと同じことを同じようにできるのが当たり前…。
それができる子ももちろんいますができない子もやっぱりいるんです…。
板書がどうやってもうまくできない。
だから連絡帳もうまく書けない。
読解力が弱いから、文章問題を理解するのが難しい。
漢字が書けない。
などなど他の子達が普通にやっていることがうまくできないのはADHDキッズ達には、よくあることなんです。
ですが、残念ながらできない子は怠けている、我慢がきかないと責められてしまう傾向がありますが、本当はそうではない!!
できない子にはできない理由があるんです。
だけど、その理由はとってもとってもわかりにくい…。
だから理解もされないし、みんなと同じができない子は日本では嫌がられてしまう…。そして学校が苦手になってしまう…。それが現実です。

大事なのはママの理解!
だからお母さん達にまず知って欲しいことは、お子さんを知って欲しい!ということです。
お母さんがお子さんの特徴を知ってあげることで、色々な困り事や怒りの問題を解決することができていきます!
ADHDキッズができないことが多いのは脳の凸凹のせいです。
決して彼らが怠けているわけでも、彼らがふざけているわけでもありません。
やろうとしてもできないんです。
ですがそんなことは誰も知ろうともせず、みんなと同じようにできないあの子はダメな子!とレッテルを貼ります。
そして周りがこぞってみんなと同じ振る舞いを求めて注意をしたり叱ったり。
そして残念なことに、みんなと同じができない自分は悪い子だと、子ども自身も思い込んで苦しくなってしまい、
ストレスを溜め込み荒れていきます…。
荒れるということはイライラすることが増えるということ。
そこに元々の感情コントロールの苦手さや衝動性、言葉での表現が苦手などが加わると、怒りが爆発し癇癪となってしまう。。

ですがお母さんがお子さんのことを理解してあげたら、声かけから変わってきます。
「ノート取るのが難しい?先生に話して対応してもらおうか」
「連絡帳書くの時間かかるよね、だったらお母さんから先生に聞くね」
「文章問題、わかんないか。だったらお母さんと一緒にやろう!」
「漢字難しいよね、書けないの悔しいね」
などと声かけが寄り添う言葉に変わっていきます。
そしてお母さんのイライラも減っていくと思います。
プリントぐちゃぐちゃにもってきて!「もぉ~っ!!」と思うのではなく、
この子は整理整頓が苦手なんだなぁ…
だったら大きめのファイルケースを毎日待たせて、
「全部ここに突っ込んできてね!」と伝えてあげるのも一つ。
先生からいつもゴソゴソして話を聞いていないんです!
というご報告を受けたら「先生の話を聞きなさい!」と叱るのではなく、
授業つまらなくて聞けないんだな…と理解して
先生にどうも集中が苦手みたいだからもし授業の邪魔になるのなら、
本を読ませておいてくださいとお願いしてみるなど
お母さんがお子さんを理解するとお母さんの行動が変わり、
お子さんもお母さんがわかってくれてる!と感じて、落ち着いていきます!

カナダの子育て、カナダの教育はこんなに違う!
カナダでは小さい子達はつねに椅子に座らせることはありません。
彼らのキャパシティ(できる範囲)に合わせて行動させます。
カーペットがクラスに敷いてあって、そこでゴロゴロ寝転んだりリラックスすることだってできるんです。
ウロウロしてしまう子には、先生がこの子は考える時に歩くことが必要なのよね!と理解を示してくれます。
子育てに関してもそうです。
ママがパパがその子の特性を理解し彼らに合う対応をするから、子ども達がストレスなく自分の特性を受け入れることができる子が多いと感じます。
だから自己肯定感が下がることなくストレスが溜まりにくく問題行動が起きにくいんです!
なので私たちができることは何かといえばお母さんがお子さんを理解すること。
理解できているようで、出来ていないのが現実です。
理解すればお母さんがお子さんに合う対応ができるようになっていきます。
理解できるようになるにはお子さんを良く見て、好ましい行動を肯定してあげること。
それだけでお子さんのことが今よりももっと見えるようになるはずです♪
我が子がみんなと同じように振る舞えない、1人だけ問題行動を起こしてしまう、という現実は初めは正直受け入れ難いですよね。
だからちょっとだけ…お子さんがみんなと同じように振る舞えない理由を、探してみてあげてください。
そうするとお母さんの考え方がちょっとだけ…変わります。
試してみてくれると嬉しいです!
こちらの電子書籍に肯定の仕方を書きました!
参考にしてみてくださいね♪
自分でクールダウンできる子に!
「叱らず育てたい!」が叶う書籍はこちら
↓↓↓
執筆者:梅村やよい
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)