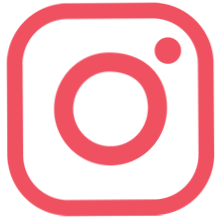小1で登校しぶりと不登校を経験した息子、原因は「過剰適応」だった
注意欠陥/多動性障害(ADHD)×自閉スペクトラム症(ASD)グレーゾーンの息子は、小学校に入学して1ヶ月ほどたった頃、登校しぶりが始まりました。
小学校に入ってすぐから、
「もう小学生だから、自分で学校行く!」
と張り切って、まだ周りはお母さんが付き添っていた時期から、
付き添いなしでお友達と登校していました。
入学から一ヶ月ほど経ったある日、
「何もしてないのにお友達にこんなこと言われた」
といった発言が見られるようになって、学校への足取りは重くなり、その数日後には、登校途中で嘔吐してしまいました。
そこからはしばらく登校できない日があったり、付き添い登校をしたり、といった日々が続きました。

今から考えると、「過剰適応」の典型的なパターンで、
ストレスが限界を迎えてしまったのですが、
当時、知識も経験もなかった私は、
「小学生になって頑張ってるな〜」
と呑気に見ていて、完全に過剰適応を見逃してしまっていたのです。
外ではいい子、家だけ荒れる子が1分で気持ちの切り替えができる子になる!
繊細でがんばりすぎる子への対応がわかる1冊はこちら↓
過剰適応とは?
過剰適応とは、周りに合わせようと頑張りすぎている状態です。
誰でも、新しい環境に慣れようとするときには疲れやすいものですが、環境に馴染むために自分を変えようとしすぎる状態を「過剰適応」といいます。
小学生の場合、特に進学や進級のタイミングで、新しい環境に慣れようと頑張りすぎることで、ストレスが溜まり、登校しぶりや不登校につながってしまうことがあります。

過剰適応の子は、学校での問題行動はないため、先生からは「いい子」と認識されています。
そのため、ストレスへの対応が遅れてしまいがちなんです。
外ではいい子だからこそ、お子さんの様子や体調の小さな変化に気付き、早期にケアしてあげることが大切です。
過剰適応への対応
まずは特性を理解する
過剰適応には、実は注意欠陥/多動性障害(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)といった特性が関係していることも。
・こだわりが強い
・完璧主義
・感覚過敏
といったASDの特性や、
・じっとするのがしんどい(多動性)
・集中力が長く持ちにくい(不注意)
・思いついたままに行動してしまう(衝動性)
といったADHDの特性があると、
集団生活に適応するのに、人一倍エネルギーを使うことになります。
その結果、過剰適応で疲れ切って、学校に行くのがしんどくなってしまいます。
まずは、そういった特性で、子どもが困っている可能性があることを理解するところから始めましょう。
子どもの気持ちを代弁・共感する声かけ
特性が理解できると、子どもの困りごとや本音が見えやすくなります。
こういったタイプの子は、環境の変化や人の気持ちにはとても敏感なのに、自分の気持ちには鈍感。
そのため、本人も気づかないうちに、ストレスが溜まっていってしまうことも。
「おうち癇癪が増えてきたな」と感じたら、
「今日は参観日だからちょっと緊張するね」
「新学期だから疲れてきたかな?」
と代弁、共感する声かけで、自分の気持ちに気付くサポートをして、ストレスを和らげていきましょう。

普段からの「肯定」
そして、一番大切なのが、普段からの肯定的なコミュニケーション。
外で頑張って疲れているところに、
「宿題したの?!」
「まだごはん食べ終わってないの?!」
「早くゲームやめなさい!」
といった否定的なコミュニケーションをしていると、家でもストレスが溜まってしまい、学校に行くエネルギーがなくなってしまいます。
・「おかえり!」と笑顔で出迎える
・「ごはん食べてるね」とできていることを実況中継
・「そのゲーム楽しそうだね!」と興味を示す声かけ
などの肯定的な声かけを心がけましょう。
ストレスを軽減し、親子の信頼関係を築くことができるので、学校で困った時には、お母さんに相談しやすくなります。
執筆者:大谷むつみ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)