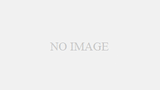安心感を伝えることは最初の一歩です!
登校しぶりや学校で話せない場面緘黙症の子にも、こうしたい!という意思があります。
もしかしたら、他の子どもよりも意思を曲げない強さ・頑固さがあるかもしれません。
だからこそ、無理に話させたり、無理やり学校へ行かせようとプレッシャーをかけたりするのは逆効果です!
その意思を表出できる人というのは場面緘黙症の子は安心できる人の前だけなのです。だから、「何か困っていることがあれば話してね」といったとしても、話せるのは安心できる関係を築けた人だけなのです!
だから、無理に話させようとしたり、言葉を引き出そうとすると、かえって子どもの不安や緊張感が増して、心を閉ざしてしまう可能性があります。

非言語コミュニケーションの効果
ここで注目してほしいのが、「非言語コミュニケーション」です。
例えば、子どもに優しい視線を送ったり、落ち着いた態度でそばにいるだけでも、大きな効果があるのです。
特に、場面緘黙症の子は身近にいる人の表情や態度から安全を感じ取って、少しずつ心を開いていくものです。言葉で表現できなくても、安心できる環境が整っていれば、子どもは落ち着くことができるのです。
場面緘黙症の子に大事にしたい『ホームカウンセリング』
そして、もう一つ大事なのが「ホームカウンセリング」です。
登校しぶりや場面緘黙症の子が話し始めたら、その言った言葉が的を得ていなくても否定せず、耳を傾けてみるのです。
大人が意見を押し付けたり、「そんなことは気にしなくていい」とすぐに解決してしまうと、子どもは「自分の気持ちを分かってもらえない」と気持ちに蓋をしてしまいます。
子どもの言葉や表情を受け止めて、気持ちを聞いてる、という分かりやすい姿勢を示すことで、信頼関係が深まっていくのです。
場面緘黙症の子が自分の気持ちを表現しやすくなる『柔らかい質問法』
場面緘黙症の子が安心して話せるためには、『柔らかい質問法』を使うことも効果的!
柔らかい質問法とは、シンプルで分かりやすい質問です。
「今日はどんなことがあった?」「今、どう感じてる?」といった質問をプレッシャーを与えることなく投げかければ、子どもが自分の気持ちを表現しやすくなるのです!
登校しぶりや場面緘黙症の子との信頼関係を築くには、焦らずに非言語コミュニケーションやお家でのカウンセリングを重視した対応が求められます。子どもが自分の気持ちを表現できる安心のサポートを続けていきましょう!