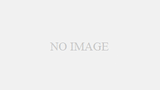場面緘黙の子にあるあるな「こだわり」とは?
この記事では、場面緘黙の子や発達・グレーゾーンの子によくみられる「こだわり」について説明していきます。
そもそもの話ですが、緊張や不安が強くなると、人ってどんな反応を起こすと思いますか?
例えば、大舞台など、緊張や不安で震えてしまう時に、手のひらに「人」という文字を指でなぞり、それを飲み込む仕草をする。
こんな事を過去にしたことがある!という方はいませんか?
わたしは、あります!
なぜなら、「そうした方がいい!」と教わってきたから。だから、そうしているだけなのです。つまり、何の根拠もありません。

色々調べていると、ある大学の研究で、緊張状態の時に「人」という文字を書いてのみ込む仕草で緊張を緩和できるのか?という面白い論文を見かけました。
やはり、「プラセボ効果」とか「特に根拠はない」と書かれていましたが、小さい頃からそれが習慣になっていたとしたら、緊張状態になる度に、手のひらに「人」をかいてのみ込む仕草をしてしまいますよね。
これは、いわゆる習慣や経験からの「こだわり」だと私は思うのです。
場面緘黙の子がこだわる本当の理由
そもそも、同じことをするという「こだわり」ってなぜするのでしょうか?
それは、「安心したいから」するのであって、裏を返せば、「不安だからこだわってしまう」ということ。
だから、不安な時はこだわりを満たしてあげればいいんです!
例えば、朝になる度に、昨日の夜せっかく準備したランドセルから荷物を全部出して、忘れ物がないかどうか確認をし始めてしまう。

親としては「昨日も見たじゃん!」「早くしなよ!」「何してんの?!」って言いたくなるのですが・・
場面緘黙の子は不安におそわれると、脳がパニック状態になってしまいます!
なぜなら、忘れ物をしたらどうなってしまうのか、ネガティブな経験を記憶しているから。これから同じことを絶対に繰り返してはならないと、脳が不安にさせているのです。
・忘れ物をすると、先生に怒られてしまう・・あの時の先生の顔が忘れられない。
・忘れ物をしたら、連絡帳に忘れた物を赤鉛筆で書かされる。
・次は忘れないようにと、何度も書かされる。
いわゆる、昔ながらの「罰」とか「しつけ」ですよね。これでは、忘れ物をしなかったとしても、いつまでたっても忘れ物をしてはいけないという恐怖感と戦っていかなくてはいけないのです。
息子は小学1年生の頃、こんな状態でした。だから、忘れ物をした日には、連絡帳が赤色で目立っていて、次は絶対に忘れてはいけない・・忘れてはならない・・という白黒思考が強くなっていきました。
私も、その当時は叱ることが多かったため、学校の先生同様、お家でも忘れ物をしないように!と叱っていました。
脳というものは緊張や不安を感じるとフリーズしてしまいます。そうなると、思考の脳が働かなくなってしまいます。つまり、感情だけが暴走してしまうのです!
だから、理由はどうであれ、こだわりを満たして「安心させてあげある」のです!
そして、その都度対処する治療よりも、普段から予防行動をしておけば上手くいくのです!

場面緘黙の子の「困り事を見つけたら対処する」を「予防対策」へ変える!
場面緘黙の子どもの困りごとって見つけるとその都度対処したくなるんです。
ですが、それでは終わりがないんです。
だから、考え方としては、「その都度対処」より「普段の親子の会話で脳を育てるという予防対策」に関わり方を変えておけば、困りごとが起こる前に対処できちゃうので子育てがラクになるのです!
だから、困りごとを追いかけるイタチごっこはしなくていいんです!

身近にいる子どもにとってお母さんの声かけってとっても影響力があります。そんな影響があるお母さんの声かけを質のいいものに変えてあげれば、もっと効果的なんです!
今の関わり方でお子さんが変わらないと感じているなら、気づいた今だから変えてみるのも一つの選択肢だと思うのです。困り事を追いかけるイタチごっこは、もう卒業しましょう!