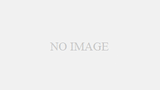緊張すると脳の中で何が起こるのか?
お子さんが緊張しているとき、脳の中ではいくつかの重要な反応が起きています。この仕組みを知ることで、緊張が「コントロールできるもの」だと理解できるようになります。
脳の「扁桃体」が過剰に反応する
緊張したとき、脳の「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる部分が活発になります。この扁桃体は危険を察知して体を守る役割を持っていますが、場面緘黙症のお子さんの場合、人前で話すことや注目を浴びることを「危険」と認識してしまい、強いストレス反応を引き起こします。
自律神経が緊張を引き起こす
扁桃体が活発になると、体を守るために自律神経が働きます。その結果、心拍数が上がったり、息苦しくなったり、手汗をかいたりします。この状態では、リラックスして話すのが難しくなります。
脳の前頭前野の働きが低下する
緊張が強くなると、脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の働きが弱くなります。この部分は、冷静に考えたり判断したりする力を司る場所です。そのため、緊張しているときは頭が真っ白になり、考えがまとまらなくなります。
緊張した脳を落ち着かせる方法
お子さんが緊張しているとき、脳の状態をリラックスさせるためにできることがあります。ここでは、家庭で簡単に取り入れられる方法をご紹介します。
深呼吸を促す
深い呼吸は、自律神経を整える効果があります。一緒にゆっくり深呼吸をして、「吸って、吐いて」のリズムをお子さんと共有してみましょう。これだけでも、脳に「大丈夫」というメッセージを送ることができます。
身体を動かして緊張をほぐす
軽い運動やストレッチは、脳に酸素を送ると同時に、緊張で固まった体をほぐします。朝の時間に軽い体操を一緒にやると、学校へ行く前の緊張が和らぎやすくなります。
環境を整える
緊張が強くなる場所や状況をあらかじめ避けるのも一つの方法です。学校や習い事でできるだけリラックスできる環境を先生に相談し、お子さんにとって過ごしやすい場を作る工夫をしてみましょう。
お子さんの脳と心を理解するために
緊張を感じているお子さんに対して、「どうして話せないの?」と問い詰めたり、「もっと頑張って」と励ましたりするのは逆効果になる場合があります。お子さんの脳や心を理解することが、何よりも大切な第一歩です。
無理に話させない
場面緘黙症のお子さんにとって、「話すこと」は最も大きなハードルの一つです。緊張しているときは、話すことを求めず、安心感を与える声かけをしましょう。例えば、「今日は黙っていても大丈夫だよ」と伝えるだけで、お子さんはほっとします。
小さな成功体験を積む
脳は、安心できる経験を繰り返すことでストレスに強くなります。家族や親しい友達と少しずつ会話の練習をし、「話せた!」という成功体験を積み重ねていきましょう。
感情を認める
「緊張してもいいんだよ」「誰だってそういう時があるよ」と伝え、お子さんが自分の気持ちを否定しないようサポートしてあげてください。
ママができることは「安心を与えること」
お子さんの脳が緊張を感じているとき、一番必要なのは「安心感」です。ママがそばにいて、「あなたの味方だよ」という気持ちを伝えることで、お子さんの脳は徐々に落ち着いていきます。
お子さんのペースを大切にする
緊張しやすい脳は、急に変わることはありません。無理させず、お子さんのペースで少しずつステップを踏んでいくことが、安心感を育む鍵です。
ママ自身もリラックスを心がける
ママが焦ったり不安を感じたりすると、その感情が無意識にお子さんに伝わってしまいます。ママ自身もリラックスする時間を取り、心に余裕を持つようにしましょう。
緊張は成長のきっかけになる
緊張しやすい脳を持つ場面緘黙のあるお子さんは、その分だけ感受性が豊かで、物事を深く考える力を持っています。
場面緘黙症はお子さんの個性の一つであり、その特性を理解してサポートしていくことで、お子さんは自分のペースで成長していくでしょう。
緊張そのものを「悪いもの」と捉えるのではなく、「成長するためのきっかけ」と考えることで、ママも前向きな気持ちでお子さんと向き合えるはずです。
お子さんの気持ちや脳の状態に寄り添いながら、一緒に小さな一歩を踏み出していきましょう。