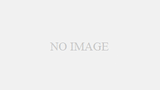「嬉しい」「悲しい」と感じても、学校では言葉や態度で表現しない場面緘黙症の子
なんらかの感情を感じていても、緊張してしまう学校では、言葉や態度で表現できない場面緘黙症のお子さんはいませんか?お家との姿の違いに、歯がゆい思いをするママも多いのではないでしょうか。
自分の気持ちを伝えることに慣れてなかったり、何を考えているのか分かりにくいタイプのお子さんは場面緘黙症に限らず、意外と多いものです。
実際に、場面緘黙症のある息子さんを育てるYさんも、同じ悩みをたった一人で抱えていました。
「嬉しいなら思い切り表現すればいいのに!」
「どうして気持ちを伝えるのが恥ずかしいの?」
そんな風に思っても、どう接したらいいか分からないのです。
ですが、実は子ども自身もどう表現すればいいか分からなくて困ってるようなのです。この思いは場面緘黙症の息子が教えてくれました。

場面緘黙症の子は、なぜ感情を表現できないの?
場面緘黙症のお子さんが感情を表に出さない背景には、いくつかの理由があるといわれています。
感情表現のバリエーションが少ない
「嬉しい」「悲しい」「楽しい」という気持ちはあっても、それをどのように表現すればいいのか分からない。その結果、何も言わず黙ってしまうのです。
「積極的であることが良い」という価値観
私たち親世代は「明るく」「元気に」「積極的に友だちを作る」といったことが良しとされる教育を受けてきました。
成績表にも「積極的」という項目がありますよね。逆の「消極的」は評価できないということが見え隠れしていますよね。
そのため、無意識のうちに「自分を出さなければダメ」と思われがちです。
親に心配をかけたくない、どう相談すればいいか分からない
場面緘黙症の子は、自分が「感情を表に出せないこと」で親が心配するのを分かっています。そのため「心配をかけたくない」と思って何も言わないケースもあります。
また、「気持ちを伝えたくても、うまく言葉にできない」という理由で黙ってしまう事もあります。

場面緘黙症の子の感情表現力を引き出すには?
では、どうすればお子さんが安心して感情を表現できるようになるのでしょうか?
ポイントは「肯定すること」です!
Yさんには、まず親子の会話の中で感情を交えたやり取りを増やしてもらいました。
例えば、
「今日の出来事で楽しかった第一位は何でしょうか?」とインタビュー形式でママが聞く!
「それってすごく嬉しかったんじゃないですか?」と感情を交えて聞いてみる!
「もし私が同じ立場だったら、ちょっとドキドキしちゃうかも」と感情を交えた会話を続ける!
このような形で、お子さんの気持ちを引き出しやすくする質問をママが楽しんでみる!さらに「感情に名前をつけてあげる」ことで、少しずつ自分の気持ちを言葉にしやすくなっていくのです。

場面緘黙症の子を育てる親子に起こった変化とは?
この「肯定する関わり」を1〜3ヶ月あきらめずに続けたことで、Yさんのお子さんは少しずつ感情を表現できるようになりました。そして、「今日こんなことがあって…」と自分から話してくれることが増えていきました。
すると、Yさんの息子さんだけでなく、Yさん自身も「自分の気持ちを伝えたほうがラク」と実感したのです。体験から学ぶことって、親子で実感できる!
こういった感情の共有が、さらに感情を交えた会話を豊かにしていくと、私は思うのです!
その後、Yさんの息子さんは「どうすればいいか」を冷静に考えられるようになっていきました。
さいごに、感情表現は練習で伸ばせます!「話せない」「気持ちを出せない」ことは、決して悪いことではありません。ですが、ママが焦りや不安感から「もっと話して!」と急かすことが、プレッシャーになってしまうこともあるのです。
大切なのは、子どもが安心して気持ちを出せる環境をつくり、「経験させる」こと!
そのために、今からママにできることは
①ママがお家で感情を交えた会話を増やす
②「気持ちを表現することって楽しい」と感じられる経験を増やし、感情を共有すること。
親子の会話の中でちょっと意識するだけで、お子さんの世界は大きく広がっていきますよ!
ぜひ、やってみてくださいね!