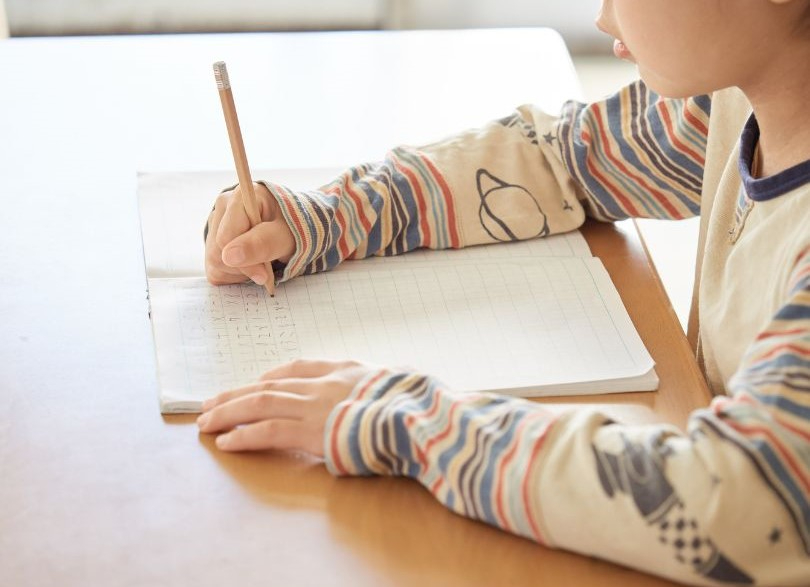「勉強をしない我が子にイライラ」
「否定しないように接したいのに、つい口から出てしまう」
「勉強が遅れたまま、中学に進んで大丈夫?」
そんなふうに悩んだことはありませんか?
勉強が大キライ、苦手、なかなか進まない・・・
そんな子を見て、落ち込んでしまうこともあると思います。
ですが、実は、
子どもが「勉強できないやらない問題」の多くは
「才能がないから」ではありません。
脳の発達の特性として、“まだ使えていない部分”があるだけ。
そして、その部分を使うスイッチを押せるのは、
療育や塾でもなく、一番そばにいるママなんです^^
ママが「関わり方」を変えることで、
子どもは脳を広く深く使えるようになり、
これまで見えなかった「才能」が見えてきます。
例えば、夏休みの宿題・・・
土日の追い込みで、
子どものイライラや癇癪の嵐に
巻き込まれたママも多かったのではないでしょうか?
×をつけると怒りだす。
直させようとするとイライラ暴れだす。
かといって、そのままにするのも不安・・・
実はここに、大きな突破口があります。
大きな声では言えませんが・・・
私はよく、間違いを見ても
あえて「見て見ぬふり」をしていました。
宿題のノート(プリント)を
じぃーーーーっと見て、
顔を上げてにっこり。
「素晴らしい!」「天才!」と言って、
大きな花丸をひとつ書くだけ。
これが“間違いスルー戦略”です。
驚くかもしれませんが
次の日にトラブルになったことは一度もなし。
むしろ先生や友だちに指摘されるほうが、素直に理解できる子は多いんです。
もし「ママのせいで恥をかいた!」と怒られても大丈夫。
「そうなんだ!どこ?」と聞いて説明させれば、理解はさらに深まり、記憶にも残ります。
「〇〇(←お子さんの名前)先生! ありがとう! ママも間違えてた~」
そんな風に言えば、子どもは「大人に教えた成功体験」を積み、
同時に「ママだって間違えるんだ」という気づきで
「白黒思考」が和らぎます。
つまり、
「間違いに気づける体験」や
「間違えても大丈夫な体験」を積ませること。
これが学びの土台を作るんです。
正確さを追うのは“もっとやりたい!”が育ってからで十分。
まずは、「できた量」「楽しい気持ち」を優先することが
将来の正確さや持続力につながるのです。