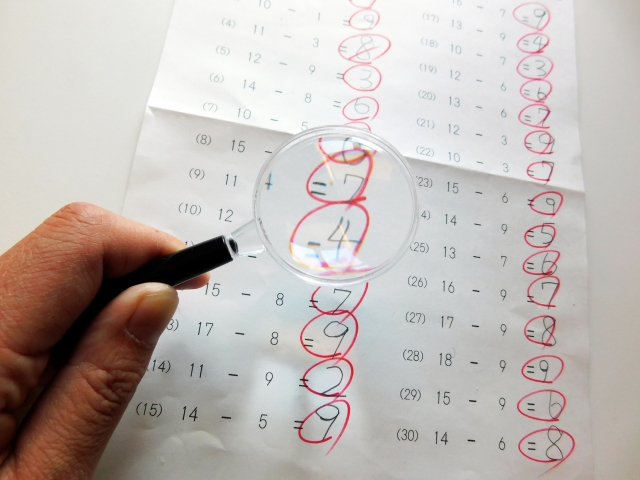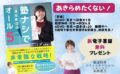お盆休みがスタートしたママも
多いでしょうか?
帰省の前にお子さんの宿題チェックに追われている・・・
そんなママに質問。
丸付けをしていて
「あれっ?」
「理解しているのに間違える子」
っていませんか?
計算も文章題も分かっているはずなのに、
なぜか引き算が足し算になったり、
途中で数字が抜けてしまったり・・・
「ちゃんとやればできるのに、なんで・・・?」と、
見ている親の方が歯がゆくなるあの現象です。
実はこれ、やる気や努力不足ではなく、
脳の“作業机”の容量=短期記憶(ワーキングメモリ)が小さいために起こることが多いんです。
さらに、感情の揺れが大きいお子さんだと、
この作業机の上が一気に散らかって、
今やっていたことをポロッと落としてしまう・・・
だから、調子がいい時はスラスラできるのに、そうでない時はミス連発、なんてことも起こります。
脳の作業机は、「正しい関わり方」で「生活を整える」ことで広く、そして散らかりにくくできます。
しかも、無理に計算練習させるのではなく、日常生活の中で鍛えることができるんです。
たとえば
おつかいミッション
「冷蔵庫から卵と牛乳とケチャップを持ってきて」
→ 複数情報をまとめて保持する力を鍛える。
思い出しクイズ
「昨日の夕ご飯、何だったっけ?」
→ 過去の出来事を思い出すことで、記憶の引き出しを使う習慣をつける。
おしゃべり実況中継
「洗濯物をたたんで、引き出しにしまったら、私に教えてね」
→ 行動の順序をイメージしながら進める力を育てる。
ミッションクリアーごとに
めいっぱい肯定してくださいね^^
どれも、ママと子のコミュニケーションが整っていることが大前提のミッションではありますが・・・
こういう日常的な声かけは、
勉強よりもハードルが低いので、
成功体験が積みやすく、
「やればできる」の感覚とワーメモの両方を伸ばせます。
あるお子さんは、数日間ママが関わり方を変えただけで、
家事や勉強に自分から取り組み、
別人のように穏やかになりました。
これは、一時的に刺激の入り口を整えただけで、
脳の机が片付いた状態になったからです。
私自身、わが子や受講生さんの変化を何度も見てきました。
やればできるのに成果が出なかった子が、
脳の使い方を変えて、
生活も勉強も一気に動き出す瞬間があります。
その変化の鍵は、才能や根性ではなく、
ママが「脳に合った関わり方」を知っているかどうか、
それを継続して、環境が整ったかどうか、
ただそれだけです。
夏休みは、学校ストレスが減り、
脳の机を片付けるチャンス。
ここで整えておくと、
秋からの学習定着がぐっと上がります。
2学期は宿題・テスト・行事の連続で、
机の上はまた散らかってしまいます。
もしも
「うちもこのタイプかも・・・」と思ったら、
夏の間に“片付け方”を身につけてしまいましょう^^
お子さんと関わる時間が増える
夏休みがチャンスです☆