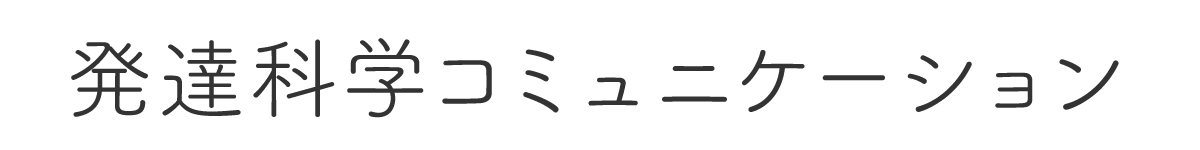不安が強い子どもは、日常のちょっとしたことでも、心が大きく揺れ動きます。そんなわが子を前に、ママは「どう声をかければいいの?」と悩んでしまいますよね。実は、ママのたった一言が、子どもの不安をやわらげ、心を開くきっかけになることがあるんです。この記事では、今日からできる「安心を届ける声かけ」をご紹介します。
不安が強い子は「否定されること」に敏感です
「そんなに気にしなくていいよ」
「大丈夫、大丈夫、行ってみたらきっと楽しいよ」
「そんなこと思う子いないよ」
励まそう、
元気づけようとしたつもりでも、
子どもは「わかってもらえなかった」と感じて、
余計に心を閉ざしてしまうことがあるのです。
人は不安を感じているとき、
わかってもらえないかもしれないという恐れを同時に抱えています。
とくに不安が強い子どもは、
心の中でこんな思いを抱えていることが多いのです。
「こんな気持ち言ったら怒られるかな」
「おかしいって思われるかな」
「また心配しすぎって言われるかも…」
だからこそ、
最初に気持ちを
否定されず
比べられず
受け止めてもらえる体験をすると、
子どもはこう感じます。
「あ、大丈夫なんだ」
「この人は、話をちゃんと聞いてくれる」
「言ってもいいんだ」
これが、ここなら話しても大丈夫という安心感の正体です。
そしてこの安心感は、
脳の「不安中枢」である扁桃体(へんとうたい)の働きを落ち着かせ、
思考を司る前頭前野(ぜんとうぜんや)がスムーズに動き出すことにつながります。
つまり、
安心できる声かけは、
子どもが「落ち着いて考えられる状態」へと導く
働きもしてくれるのです。
不安が強い子は、
正解が欲しいのではなく、
まずは安心が欲しいのです。

不安が強い子どもほど、「安心できる場所」を早くつくってあげる
不安のパターンは放っておくと定着しやすいから
子どもは繰り返しの経験から、「どう対応すればいいか」を学んでいきます。
そのときに、「話しても否定される」「不安はわかってもらえない」という体験が続くと、
やがて不安を外に出さずに、ためこむクセが身についてしまうことがあります。
それは、小学校高学年・中学生…と成長する中で、
-
自分の気持ちを言えない
-
我慢しすぎて爆発する
-
“わかってくれない”と人を遠ざける
といった形で現れてしまうこともあるのです。
親の関わりは「今がいちばん届きやすい」から
子どもがまだ小さいうちは、
ママの表情・声のトーン・言葉選びが、そのまま「安心の土台」になります。
不安が強い子でも、「ママがわかってくれた」と感じると、少しずつ心をひらいてくれます。
この時期に“安心して話せる親子関係”をつくっておくことが、今後の大きな支えになるのです。
「安心して話せる経験」は一生の財産になるから
安心して話せる経験を積んだ子は、
やがて「気持ちを言葉にして、相手とつながる力」を身につけていきます。
それは、学校生活、友人関係、将来の人間関係でも、
自分を守りながら、自分らしく生きていく力の土台になります。

私は安心の声かけができませんでした
「そんなに気にしなくてもいいよ」
不安そうにする息子に、
私は何とか元気づけようと、
前向きな言葉をかけてきたつもりでした。
でも、ある日、
息子が何も言わずに、
ただ泣くようになったんです。
「行きたくない理由」を話してくれない。
「イヤ」と言うだけで、何も伝えてくれない。
こんなに声をかけているのになんで?
日に日に元気がなくなる息子を見るのが辛く、自分を責めました。
不安が強い子が落ち着いて話せる子に変わる声かけ5選
以下の言葉がけは、不安が強い子どもにとって、心がふっと軽くなる魔法のような言葉です。
①「そうだったんだね」
子どもの気持ちに共感するシンプルな一言。
「わかってくれた」と思える安心感を与えます。
②「怖かったね」
不安や恐れの感情をそのまま言葉にしてあげることで、
子ども自身が「そうだったんだ」と気づけることもあります。
③「そう思ったんだね。教えてくれてありがとう」
気持ちを言葉にできたことに価値を置く声かけ。
自己肯定感を育てる一言です。
④「お母さんもそうだったことあるよ」
自分だけじゃないとわかると、子どもは安心します。
ママの経験を少しシェアするのも効果的。
⑤「じゃあどうしたいか、一緒に考えてみようか」
気持ちを受け止めたあとで、やさしく前を向かせる言葉。
自分で選んで動ける子になる土台になります。

ママの言葉は、子どもにとって「安心のよりどころ」
不安が強い子は、いつも頭の中に「もしも」がたくさん浮かんでいます。
「もし失敗したらどうしよう」
「先生に怒られたらどうしよう」
「友だちがいなくなったら…」
そんなとき、ママの言葉が安心のよりどころになることで、子どもは少しずつ落ち着いて話せるようになります。
それは特別な知識や技術がなくても大丈夫。
ただ「受け止めてくれる存在がそばにいる」ことが、なによりの支えになるのです。