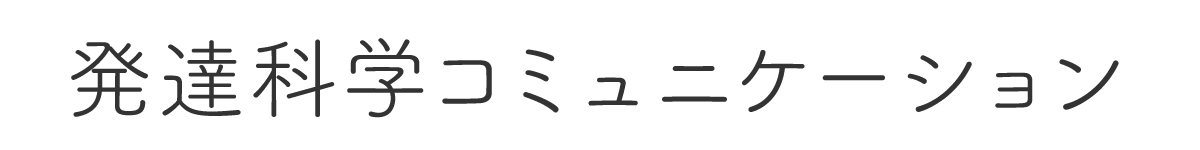「ASD(自閉スペクトラム症)」という言葉を聞いたことはありますか?
わが子の育てにくさや、ちょっとした困りごとに悩んでいるママにこそ、まずは知っておいてほしいことがあります。
今日は、ASDについての大切な
3つのポイントを、解説しますね!
① ASDって、昔は別の名前だったんです
以前は…
-
自閉症
-
アスペルガー症候群
-
広汎性発達障害(PDD)
など、
さまざまな名前で呼ばれていたものが、2013年に「自閉スペクトラム症(ASD)」という1つの診断名に統一されました。
「昔はアスペルガーって言ってたよね?」という声もありますが、
今ではそれらをすべて含めてASDと呼ぶのが一般的です。
② 「スペクトラム」って どういう意味?
スペクトラムとは、
「連続した幅がある」と
いう意味です。
たとえば、虹の色をイメージしてみてください。
赤から紫まで、
はっきり分かれているようでいて、実はなめらかにグラデーションでつながっていますよね。
ASDもそれと同じ。
ひとりひとりに違う「かたち」があり、どこかで線を引けるものではありません。
たとえば…
人とのやりとりがとても苦手な子もいれば、関わりたいけどうまく伝えられない子もいます。
音や光にとても敏感な子もいれば、まったく気にならない子もいます。
つまり、
「この子なりのASDのあらわれ方」があるということなんです。
③ 育て方のせいじゃありません
ASDは、
脳の感じ方や捉え方の特性によるもので、決してママやパパの育て方が原因ではありません。
「なんでこんなことで癇癪を起こすんだろう…」
「どうしてうまく伝わらないんだろう…」
そんなふうに悩む日があるかもしれません。
ですが、それは、
ママがわが子を一生懸命見ているからこそ生まれる気づきなんです。
理解なくして発達支援はできないと考えています。
ASDを知ること。
それは「この子をもっと理解したい」という、ママのやさしさのあらわれです。
診断の有無に関係なく、
「この子にはどんな感じ方があるのかな?」と目を向けるだけでも、親子の関わりは、もっとあたたかく、スムーズになります。
ASDを知ることは、
子どもとの毎日をちょっとラクにするヒントにもつながります。
そして何より、子どもらしさを大切にできるようになる、やさしい一歩です。
一緒に、「うちの子らしさ」を大切に育てていきましょう!