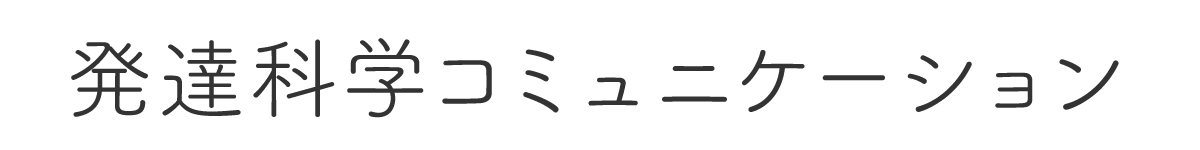発達障害の子どもと関わる上で絶対に知っておきたい
「二次障害」についてお話しします。
二次障害とは?
ほとんどの発達障害は生まれつきの脳の特性です。
一方、二次障害は生まれつきではなく、親や周囲の関わり・環境によって後から作られてしまう状態です。
たとえば…
・できないことを何度も叱られる
・コミュニケーションの苦手さを「空気が読めない」と否定される
こうした不適切な関わりが積み重なることで、もともと持っていなかった別の特性や問題が現れることがあります。
二次障害は、
大きく分けると、
2つのパターンがよく見られます。
① 反抗的な態度が強くなる
小学校高学年頃から挑発的な行動や授業妨害、さらに悪化すると非行や問題行動に発展することも。
活発なADHDタイプや学習障害タイプの子に多い傾向です。
② メンタル面への影響
うつ、不安障害、パニック障害、強迫性障害、場面緘黙(かんもく)など。特に自閉スペクトラム症(ASD)の子は、内向的なため自己否定感が強まりやすく、心の不調が長期化することもあります。
なぜ起きるのか?
理由はシンプルで、
「特性」への理解不足からくる関わりのミスマッチです。
たとえば…
椅子に長時間座ることが
難しい子に、
「なんで座っていられないの?」「立っちゃダメ!」と
繰り返し叱り続ける。
本人も「座らなきゃ」と思っているのにできない。
このギャップがストレスを積み重ね、やがて反抗や心の不調へとつながります。
叱っても変わらないのは SOSのサイン
「何度叱っても変わらない」場合、それは子どもがどうにもできないことかもしれません。
もし間違った関わりを続けてしまえば、元々の特性に対応する前に、まず二次障害から対処しなければならなくなります。
そうなると回復までに時間がかかり、親子ともに疲弊します。
覚えておきたい2つのポイント!
・発達障害の困りごとは放っておくと二次障害を起こす可能性がある
・親や周囲の関わり方を見直すことが予防につながる
この2つを、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。