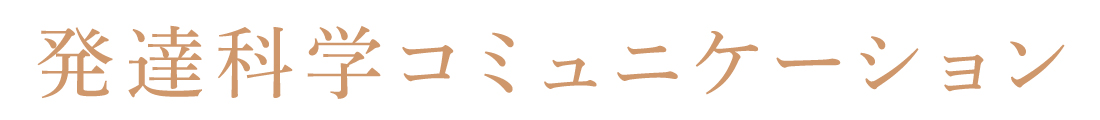連休明け、お疲れモードなお子さんはいませんか?
新学期が始まり、クラス、先生、友達、授業など多くのことがガラリと変わり、4月は緊張しながら毎日を頑張っていたお子さんが多いのではないでしょうか。
しかし、ゴールデンウィークが明けると、張り詰めていた糸が緩み、一気に疲れや不安が出てくるお子さんもいます。
我が家の繊細気質の息子の癇癪や登校渋りが本格化したのも5月でした。
いつもなら自分で時間内にやめられるYouTubeがなかなかやめられず、明日の準備も宿題も終わっていないのに寝る時間は過ぎていきます。
「そろそろ寝る時間だよ〜」の声かけには「ムリ!」の一言。
「宿題をさせなければ」「早く寝かせなければ」「歯磨きさせなければ」
私の焦りとイライラが時間と共に増していきます。

「もう寝る時間だよ、宿題は?明日の準備は?」
言っても火に油を注ぐだけ、分かっているのに言ってしまいます。
案の定、私のその言葉にさらに反発し、YouTubeもやめない息子…。
声かけに応じられず「ムリ!」となってしまうのは、毎日学校で精一杯頑張っていることによる、不安やストレスの現れです。
どうにか不安やストレスを和らげてあげたいですよね。
そもそも、不安って何でしょうか?
次で不安の正体について説明しますね。
「不安」を理解することで「不安」に対処しやすくなる
繊細気質のお子さん、いわゆる”繊細さん”は脳にストレスがかかりやすいと言われています。そして、不安は脳にストレスを与えます。
不安が強い状態というのは、不安が行動や生活に影響を及ぼしてしまうことを指します。
子どもの場合は、不安の中身を言葉で伝えることが苦手なので、「お腹が痛い」「学校行きたくない」など体に症状が出やすいのが特徴です。
繊細さんは我慢強い子も多いので、なるべく見過ごさないように観察してあげてください。
子どもが不安そうな顔をしているとついつい「何かあったの?」「何が不安なの?」「何が心配なの?」と聞きたくなりますよね。
私もそうでした。とにかく具体的な理由が知りたくて、子どもを質問攻めにしていました。もちろん逆効果でしたが…。
皆さんは、<恐怖>と<不安>に違いがあることを知っていますか?
この二つ、似ているようで実は違うものなのです。
- 恐怖=対象がハッキリしている
「先生が怖いから行きたくない」
「悪口を言うお友達がいるから行きたくない」
- 不安=対象がハッキリしないもの
「お母さんと離れたくない」
「教室に入りたくない」
<不安>は対象が漠然としていて、自分では切り替えることができません。
恐怖も脳にとってストレスですが、対象が分からない不安は、よりストレスとなってしまいます。
「何が不安なの?」と聞いても答えられない不安があることを私たち親が理解しておくと、不安への対処がしやすくなります。

では、どうしたら子どもの不安を和らげることができるのでしょうか。
次で対応のポイントをお伝えしますね。
子どもの不安やストレスを和らげる2つのポイント
子どもの不安やストレスを和らげるために、
私が実践した2つのポイントをお伝えします。
丁寧に話して不安を軽減してあげる
一旦、親は自分の気持ちを保留して、子どもの気持ちを理解できるように会話をし、共感するように心がけましょう。
我が家の場合、イレギュラーなことがあるとそわそわ不安になるタイプなのですが、尿検査を提出する前日にこんなことがありました。
「明日おしっこが出なかったらどうするの?」
「その次の日も出なかったら?」
「忘れたらどうするの?」
と聞いてきたのです。
つい「大丈夫、大丈夫!」と言ってしまいがちですが、それでは不安は解消されません。
「心配になるよね〜。明日おしっこが出なくても、別の日でも大丈夫だよ」
「尿検査できなくても大丈夫なんだよ」
と話し、トイレに張り紙をして忘れ防止対策をしました。
私の「大丈夫」を保留し、会話をしながら息子の不安を理解し、共感を伝える対応をしたところ、息子は安心したようでした。
分かってもらえた!という気持ちも不安を軽くしてくれるのです。
「〜しなければ」を手放して、「まあ、いっか」マインドに
子どもにとっては、お母さんの笑顔が何よりも安心材料になります。
イライラ怒った顔のお母さんがそばにいたら、心も休まりませんよね。
「宿題をさせなければ」
「早く寝かせなければ」
「歯磨きさせなければ」
その「〜しなければ」こそが、自分を苦しめているのです。
「〜しなければ」を手放すことで、お母さんが笑顔で過ごせる時間が増えていきます。
世の中には様々な情報があふれていて、「こうあるべき」という考え方になりがちですが、
少しくらい寝るのが遅くたって、宿題をやらない日、歯磨きしない日があったって大丈夫!
「まあ、いっか」と唱えてみてください。
心がふっと軽くなるのを感じられるはずです。
私もこれまでは「〜しなければ」という考え方に縛られていたひとりです。
「まあ、いっか」の考え方ができるようになってからは、私のイライラが減り息子も不安が和らぎ笑顔が増えました。
5月からは課外学習や行事もあったり、運動会の練習が始まったりと、4月とは違った大きな変化の時期です。
多くの子どもたちが疲れやストレスを抱えやすい時期でもあるので、親子共にリラックスして、無理せず過ごしていきましょう!

<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
仲村まな