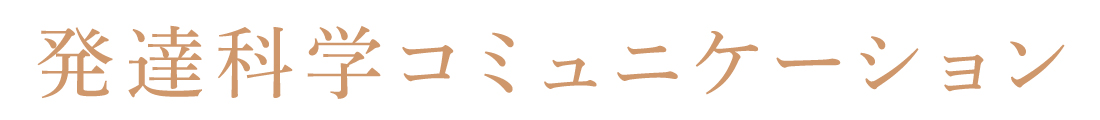泣く!叫ぶ!物を蹴る、投げる! 小学生の癇癪に困っているママはいませんか?
泣く、叫ぶ、暴言、机を蹴る、物を投げるなど、小学生の子どもの日々繰り返される癇癪に困っているママはいませんか。
最初は穏やかに接していても、だんだんと子どもの感情に巻き込まれてママもイライラしてしまうことがあるのではないでしょうか。
注意したり叱ったりしても効果はなく、癇癪はエスカレートするばかり。対応方法が分からないと、この先どうすればよいのか不安になりますよね。
私も子どもが小学生になって急に癇癪がひどくなり、どうしたらよいのか分からず、日々疲れ切っていました。
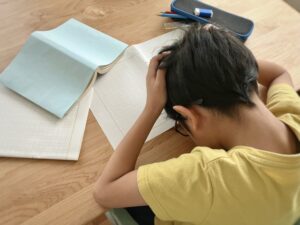
子どもの癇癪もママの怒りもエスカレート、負のスパイラルに陥っていた日々
繊細気質な私の息子は、小1のGWを過ぎた頃から突然癇癪がひどくなりました。
宿題で分からないところがあると、泣く、叫ぶ、机を蹴る、物を投げるなどの癇癪を起こすのです。泣き方もそれまで聞いたことのないような絶叫で、私に対しての暴言もひどくなる一方でした。
このままエスカレートしたらどうしよう…と不安な気持ちが大きくなっていきました。
私はどう対応してよいのか分からず、「どうしたの?」「何かあったの?」と矢継ぎ早に質問して理由を聞き出そうとしました。
最後には「言わないと分かんないでしょ!」と責めるような言い方で接してしまい、息子は無言で泣き続けるという負のスパイラルに陥っていました。
その後、息子は癇癪を起こすと毛布にくるまったり、部屋に閉じこもるようになりました。私はそんな息子の毛布をはぎ取って、「もう、いい加減にして!」と怒鳴ってしまったことも。
そして、癇癪は毎日のように続き、子どもと接することがだんだん苦痛になっていきました。
激しい癇癪のあと、子どもは泣き疲れて寝てしまうことが増えました。そんな寝顔を見ながら、自分のイライラをぶつけてしまった後悔と反省を繰り返す日々でした。
しかし、癇癪に対しての正しい対応方法を学んで、しっかり実践したことで、癇癪が減り、息子は癇癪を起こしても自分で切り替えができるようになったのです!

叱ることが子どもにとっては<注目のご褒美>になっている!?
なぜ叱ったり注意しても癇癪がおさまらず、エスカレートしてしまうのでしょうか?
それは脳の仕組みに答えがあります。
好ましくない行動(癇癪)を叱ったり、注意したりしても、効果が続かないことが多いと思います。それは、否定的な注目(叱ったり、注意すること)が子どもにとっては<注目のご褒美>になってしまうからです。
<ママが怒ること=ママが構ってくれる、自分の要求を通してくれること>として脳が誤って学習してしまっているのです。
また、行動は繰り返すほどに強化されるので、癇癪を繰り返すほどにエスカレートしてしまいます。
では、この負のスパイラルを正すにはどうしたらよいのでしょうか。
癇癪を起こしても、ママは構ってくれない、自分の要求が通らないことを気づかせることがポイントです。
具体的な方法を次で説明していきますね。

癇癪を繰り返させない対応方法! 4つのポイント!
子どもの癇癪を繰り返させない対応方法とは何でしょうか。
今日から実践できる対応方法と4つのポイントをご紹介します。
①癇癪が始まったらすぐに見て見ぬ振り!
まず、癇癪が始まったら、注意したり叱ったりしてから見守るのではなく、最初から見て見ぬ振りをすることが大切です。
②視線・体を向けない
癇癪の最中は、「ママは全然気にしていませんよ」という態度でいましょう。イライラしてるから無視してる感じにはならないように気をつけてくださいね。私は子どもが見えるところで家事をすることにしていました。
拭き掃除もおすすめです。一心不乱に床を拭く!拭き掃除に集中していると不思議とイライラも収まり、心もスッキリ。ついでに床もピカピカになって一石二鳥です!
③否定的な表情・態度・言葉・感情を示さない
そして、見て見ぬ振りをしている時は、ため息をつく、眉をひそめる、怒りのオーラを出すなどはNGです!どうしてもイライラが止まらない時は、「私は女優!」と心で唱えて乗り切っていました。
声かけ、声色、表情など、誰かモデリングできる人を作るのも効果的です。
私は下の子が通っている保育園の園長先生をモデリングしていました。そして「こんな時、園長先生だったらどんなことを言うかな、どんな表情かな」と考えるようにしました。
④褒める準備をする
最後に、癇癪が落ち着いてきたらすぐに褒める!素知らぬ顔で待ちながらも、褒め逃しのないように褒める準備をしておきましょう。
日々、癇癪が続いていると、子どものできていないところばかりに目がいき、口うるさいママになっていませんか?
「もう宿題始めたんだね!」
「この文字キレイにかけてるね」
「こんな難しい漢字書けるようになったんだね」
すでにできていることに注目し、肯定的な注目を増やしていくことも大切です。
癇癪を見守るのは、最初は難しいことです。私も最初はなかなかうまくできず、小言は飲み込めても怒りのオーラを消せませんでした…。
段々と対応に慣れてきて、癇癪を見守りながら過ごすようにしてからは、息子の癇癪が落ち着くまでの時間が短くなっていきました。そして、今では癇癪も減り、自分で気持ちの切り替えができるようになったのです。
私も子どもの癇癪に巻き込まれずに、穏やかな気持ちで過ごせるようになりました!
最初のうちは、慣れない対応方法にママも子どもも苦戦するかもしれませんが、何回か繰り返すうちに慣れ、癇癪も落ち着いてくるはずです。
子どもの繰り返す癇癪とママのイライラをストップしたい方は、ぜひ試してみてくださいね!

<執筆者>
発達科学コミュニケーションアンバサダー
仲村まな