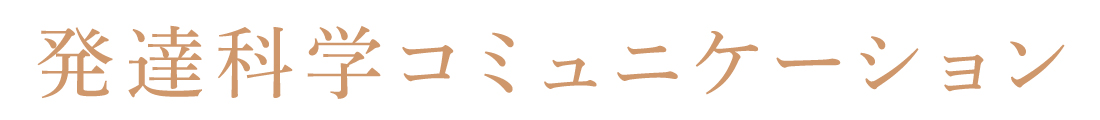勉強を始めるとすぐに癇癪を起こし宿題が終わらない小学生に悩んでいませんか?
宿題をすると言いながら結局やらないことはありませんか?
やっと勉強を始めても癇癪を起こし、やると言ったのにやらない小学生の子供にイライラして親子バトルに!
毎日宿題で癇癪を起こされるとママもイライラしちゃいますよね?

勉強になるといつも癇癪になり親子バトルに
我が家のASDグレーゾーンの娘が小学2年生だった頃、勉強を始めようとすると癇癪が起き、鉛筆を投げたり、机に鉛筆を思いっきり叩き付け刺したり、私を蹴ったり叫びだしたりと癇癪が始まることが多々ありました。
勉強しようか!と言うと
「お菓子を食べたらやる!」
「この動画見たらやる!」
「お風呂に入ったらやる!」
「習い事から帰ってきたらやる!」
と言うけれど結局なかなか始めることができず、結局やらないじゃない!と私のイライラもアップしていくいっぽうでした。
宿題を始めたかと思っても、勉強が得意ではない娘にはハードルが高く、宿題が嫌で癇癪が始まり、宿題ができるような状況ではなくなります。
「教えてよ!」と言われて教えようとしても癇癪が起きている娘は聞く事なんてできません。
「そんなに怒りながらやるならやっても意味ないからもうやらなくていい!!」
なんて言ってしまうこともよくありました。
毎日の宿題が私の苦痛であり、このままで娘の将来は大丈夫なのだろうかと心配ばかりでした。

行動する時には脳に生理的に負荷がかかる
ASDグレーゾーンの子どもや、宿題で癇癪を起こす子どもの特徴として、やれそうなことならやりたいけれど、やりたくないことや、やれそうにないことにはあまり行動を起こさない特性があります。
脳がまだ未熟な子どもはやるべきことをするという習慣がないことも多く、大人にとってはすぐにできてしまうと感じるプリント1枚でもすごく大変に感じてしまうのです。
例えば、脳は車のエンジンによく似ていて、車は40~50km/hになるまでは強くアクセルを踏まなくてはいけないけれど、トップスピードに入ればほとんどアクセルを踏む必要はありません。
脳も一緒で、行動し始めるときに最も生理的に負荷がかかるのです。
ASDグレーゾーンの子供は人一倍に苦手なこと、やりたくないことをやり始めるときに生理的に負荷がかかります。苦手な勉強に取り組む事はとても負荷がかかり、娘にはハードルが高いことなのでした。
また、宿題をやるという事はランドセルから宿題を出す、筆箱を出す、どの宿題から始めるか考えるなど、いくつかしなくてはいけない行動があります。
・段取りを考える
・段取り通りに行動する
など段取りが多いほどできない、やりたくないと思い行動することができなくなってしまいます。

3Sと行動の分解のお手伝いでスムーズに勉強に取り組めるように
では勉強で癇癪をおこす小学生にはどのようにしたらスムーズに宿題をはじめられるのでしょうか?
私が行ったことは主に二つあります。
・一つ目は、子供を勉強に誘うとき、会話の始まりをスムーズにスタートするために3Sで肯定的な声かけから始めます。
3Sとは
・笑顔(smile)
・ゆっくりと(slow)
・優しい声(sweet)の3つのSです。
そうすることにより子供は素直な気持ちでママの話を聞くことができます。
そして、行動を始めたら直ぐに褒めます。
途中もこまめに褒めると、止まりかけの行動にもう一度加速がつき、最後まで取り組みやすくなります。
・二つ目は始めるところを手伝うということです。
始めるときに最も負荷がかかっているため、あらかじめ段取りを考え、分解までしてやれそうなところからやらせます。
出来ないと思っている時こそ細かく行動を分解しお手伝いすれば自分でやりぬくことができます。
苦手なことはハードルを下げてできるかもに変えてあげましょう。
スタート段階をいかにスムーズにするかが重要なのです。
宿題や筆箱をランドセルから出し机に出して用意してあげる。
1問目はお母さんが解いて「2問目からやろっか!」でもいいのです。
そして、宿題は全部できなくてもOK
減らしたって大丈夫!
わからなかったら答えを見てもよし!
そんな気持ちでママがいると子供も大人も楽な気持ちで取り組むことができます。
今では娘の勉強中の癇癪はほとんどなくなりました。
今でもすぐに勉強に取りかかれないこともあり、今日はこれはやらないと言い勉強を減らしたりもしますが、習い事や遊びに行く前に先に宿題をやろうと取り組むことができるようになりました。
3Sに行動の分解をしてお手伝い。ぜひ勉強で癇癪を起こす小学生に取り入れてみてくださいね。

<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
澤村 祐依