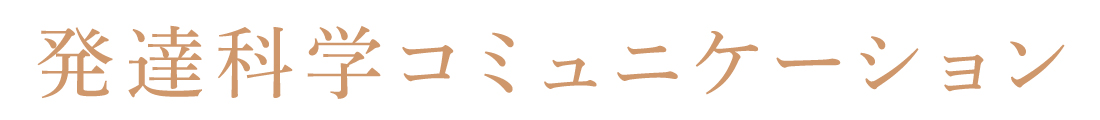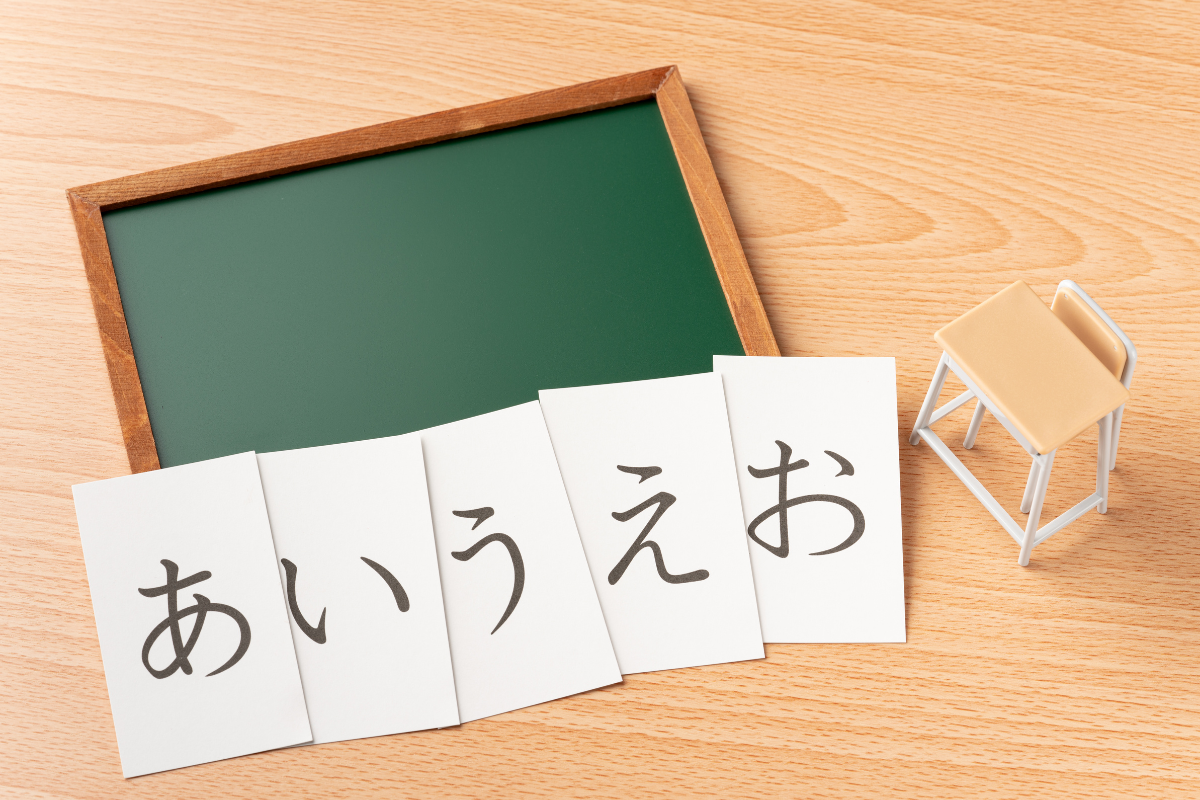ひらがなが読めない5歳児|発達に問題がある?
- 年長さんになったのにひらがなが読めない。
- 家や出かけ先で見た文字を読む様子がない。
- ひらがなの50音表で順番に言うことはできるけど、一文字ずつは覚えていない。
そんなお子さんはいませんか?
息子がひらがなが読めないことが気になり始めた時は、5歳でした。
5歳で読めた文字は1文字、6歳で読めた文字は自分の名前だけでした。
心配になって、保育園や子ども支援センターに相談したものの、
「文字は小学校になってから勉強するので、大丈夫ですよ」と言われました。
私は「大丈夫ではない」と思っていました。
まわりの子はもう自分で絵本を読んでいる。
くもんに通って文字を書いている子もいる。
保育園には自分の名前を書いた絵が飾ってある。
息子は、家で教えてもいっこうに覚える様子もないし、
それどころか、カルタや“音の出るひらがなおもちゃ”など文字を使う遊びに興味を示さなかったり、不機嫌になったりしました。
無理やりやらせても余計に嫌いになるだろうと思い、途方にくれていました。

実は、年長でひらがなを全部読めていない場合、文字の学習に何らかの困難を抱えている可能性があります。
小学校入学前に、その子に合った学び方を探していくことが大切です。
ひらがなが読めない理由|見る力と学習不安
専門家の調査では、「年長児の93%の子どもはひらがなを全部読めている」そうです。
「ひらがなを全部」とは、「ぴゃ」など小さい字をのぞき、「が」などを含んだ71文字です。
しかも、年長児でどれだけひらがなを読めるかというのは、家でどれだけ練習したかという時間と無関係だったそうです。
では、年長でひらがなが読めない子は、自然と覚えられる子と何が違うのでしょうか。
- 見る力の弱さ
- 学習への不安の強さ
この記事では、2つの理由を紹介します。
見る力の弱さ
文字を覚えるために必要な「見る力」を 視覚認知(しかくにんち) と言います。
この力には、2つの大事な働きがあります。
(1)文字の形をとらえる力
文字の形をとらえる力があると、見ただけで書き順のイメージがわきます。
例えば、「お」という文字は、
- 横線
- 「の」の上が飛び出した形
- 「、」
のパーツでできています。
でも、小さな子や見る力が弱い子は、文字を見てもパーツに分けて考えるのが難しいです。
そのため、「お」という文字を見た時に、書き順通りには書かず、「+」と「の」と「、」 をバラバラに書いて合体させることがあります。
息子もまさにこの状態です。

(2)文字の形を覚えておく力
文字を見たときには読めても、すぐに忘れてしまうことがあります。
たとえば、「あ」という字を五十音表で見れば読めるのに、一文字だけ見せると読めないことがあります。
これは、文字の形をしっかり覚えておくのが苦手な状態です。
見る力が弱いと、このようなことが起こりやすくなります。
学習への不安の強さ
年長さんや小学1年生でひらがなが読めなかった息子は、「周りの子は読めるのに、僕はひらがなが読めないんだ」と自覚していました。
自分だけ「できない」「読めない」という、ネガティブな経験が積み重なっている可能性があるのです。
教えてもらっても、覚えられないという経験も重ねています。
「自分はできないんだ」という自信のなさが膨らみ、学習への不安が強まります。
その結果、「ひらがなの練習しよう」と誘われても、不安が勝ってしまい、取り組めなくなっていたのです。

お家でできる!ひらがなが読めない子におすすめの克服法
ひらがなが読めない5歳児さん、学習への不安が強い年長さんや小学生に対して、何から始めれば良いでしょうか。
我が家の体験談をもとにご紹介しますね。
(1)ひらがな絵カード
ひらがなカードを毎日少しずつ、ママと一緒に楽しみながら読んでいくのがおすすめです。
はじめは、「あ」なら「あり」などの絵がついたカードが良いです。
絵を見れば「ありの“あ”だ!」とわかり、息子も「あ!」と自信を持って取り組みました。
子どもが読めない時には、否定せず、ママがさらっと読んであげてください。
読めるようになってきた字は、文字だけのカードを見せて読めるか確認していくと、さらに記憶が定着していきます。
絵カードの選び方ですが、文字の形と絵が合致した教材を選ぶとさらに効果バツグンです。
文字の形に絵が重なることで、見る力の弱さを補い、文字の形が記憶に残りやすくなります。
(参考:視覚デザイン研究所「かたちでおぼえるあいうえお」)

(2)ママが一緒に楽しみながら、「喜ぶ」&「驚く」
学習不安がある子にとって、「楽しくやる」雰囲気作りが何より大切です。
「“あ”だね~!!!」
「おぉ~~~!!読めた!」
と喜んだり、驚いたりすると、息子もニコニコと取り組みました。
「喜ぶ」と「驚く」は肯定の一つです。
子どももうれしくなって、ママとのひらがな絵カードの時間が好きになっていくでしょう。
ひらがなが読めない→3か月で読めるようになった小1の息子
息子は小1になってもひらがなが読めない状態だったのですが、「ひらがな絵カード」を続けたところ、3か月で50音を全て読めるようになりました。
はじめは、「ひらがなカードやろう!」と仰々しくせず、
私がカードを見ている所に、近寄ってきたら一緒に読むという感じで始めました。
息子が飽きないくらいの枚数を考え、7~8枚程度からスタート。
すると、息子も読めることがうれしくて、毎日やるようになりました。
文字の形と絵の形が合致しているカードがなかなか見つからなかったので、自作しました。
私が作っていることで、より興味を持ったのかもしれません。
「“い”には何の絵をつけようか?」
「いるか!」
など、子どもと相談したり、時には子どもが色をぬったりして作ったカードもあります。
50音を覚え終わると、「次はカタカナをやろう!」と自分から言い出し、今はカタカナを覚えている最中です。
ひらがなが読めないお子さんでも、その子にあった学び方をすれば、必ず読めるようになります。
ぜひ、お家でお子さんと楽しみながらできることで、取り組んでみてくださいね。

<執筆者>
発達科学コミュニケーションアンバサダー
松原みのり