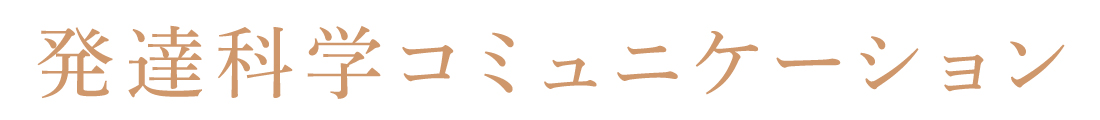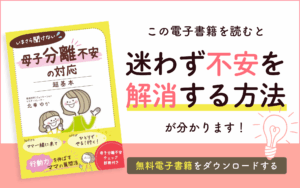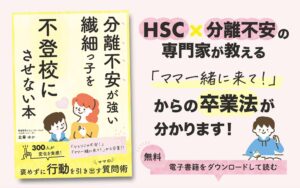繰り返す「トイレ行きたい」…心因性頻尿って知っていますか?
さっきトイレに行ったばかりなのに、またすぐにトイレへ行きたがる…
こんなお子さんの様子が続くと親としては心配になってしまいますよね。
うちの繊細な娘も、幼稚園の年少の春休みに何度もトイレへ行きたがることがありました。
特にお出かけ中に何度もトイレへ行きたがられると、トイレを毎回探すのも大変でした。
「さっき行ったばかりでしょ。」
「いい加減にして」
トイレばかり行きたがる娘に、私はイライラしてしまいました。
でもトイレへ連れて行くとちゃんとおしっこは出るのです。
娘が噓を言っている様子はありませんでした。
「なんでこんなにトイレが近いのか…」
「膀胱炎?でも痛がる様子はないし…」
そんな症状が数日間続き、私はどうしたらいいのかわかりませんでした。
ある時、ネットで色々検索していると“心因性頻尿”がヒットしたのです。
心因性頻尿とは何なのか、なぜ繊細な子どもにその症状が出るのかお話しします。

\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
トイレが近い症状は、子どものストレスが原因かも?
心因性頻尿とは、精神的なストレスや不安が原因で起こる頻尿のことです。
膀胱などの病気がないにも関わらず、何度もトイレに行きたくなる状態のことです。
夏休み明けの新学期や、新しい学年が始まる新学期は、繊細な子どもにとって緊張を感じやすい時期になります。
そして、新しい環境は脳に負荷がとてもかかります。
その脳の負荷が、子どもにプレッシャーやストレスを与えてしまい、トイレが近いという身体症状が出てしまっているのです。
実際に私も娘に「もうすぐ年中さんだね、しっかりしないとね」とプレッシャーを与えるような声掛けをしてしまっていました。
さらに、繊細な子どもはネガティブな記憶が残りやすい傾向があります。
トイレに失敗した記憶や、トイレの事で怒られた経験を忘れることができないのです。
そのネガティブな記憶を忘れられず、何度も思い出してしまいストレスが強くかかり頻尿が起こっている場合もあります。

ママの態度が大事、トイレを気にさせない解決方法
子どもがトイレへ行きたがったら、
「また行くの?」
「さっき行ったでしょ」
などと否定してはいけません。
「行ってらっしゃい」と笑顔で答えてあげるとよいでしょう。
ポイントはこちらは気にしていない素振りでいる事です。
逆にこちらが何度も「トイレに行く?」などと聞くのも、子ども自身にトイレのことを思い出させてストレスをかける事になるので、やめた方がいいでしょう。
実際に娘の通う幼稚園の先生にも、
「何度もトイレに行きたがりますが、何も言わずに笑顔で対応お願いします」
とお願いをしました。
子どものストレスのよる頻尿は、薬などを使って治療する方法はないので、トイレのことを忘れさせる事と、ストレスを軽減させてあげるかがポイントになります。

\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
トイレが近い症状が落ち着いた娘の変化
以前はトイレが近い娘にどうしていいか分からなかった私ですが、ストレスが原因の心因性頻尿だと知り、娘への対応を変えてみました。
このような対応を続けた結果、娘に変化が現れました。
徐々にトイレの間隔があくようになってきたのです。
そしてしばらくすると、何事もなかったように頻尿は落ち着いたのです。
今でもストレスやプレッシャーがかかる時は、トイレの間隔が近くなる時もありますが、平然とした態度をとっていると酷くならずに治っています。

いかがでしたか?
子どものストレスから来る頻尿は、早めの対応をすることで徐々に解決していきます。
あせらずに落ち着いて対応していきましょう。
\1日1回質問するだけ!/ \300人が変化を実感!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーションアンバサダー
川澄みさ