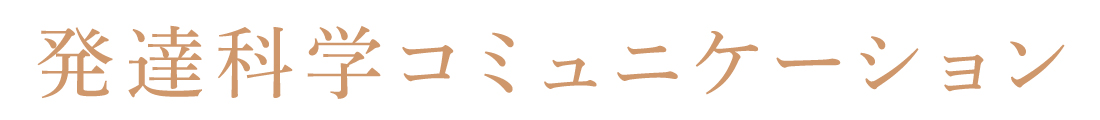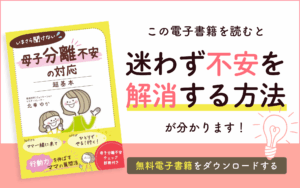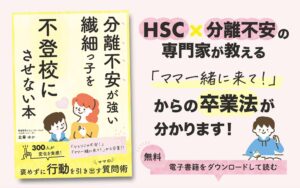【体験談】トイレが急に近くなった娘に戸惑った日々
最近、トイレに行きたいって言う回数が増えたな…
さっき行ったばかりなのに、また?
というように、突然、トイレばかり行くお子さんに戸惑っていませんか?
我が家の小学校1年生の娘は、幼稚園の頃から、突然このような症状がでることがあります。
普段はどちらかというとトイレの間隔が長い娘なのですが、ある時、外出先や家の中でも
「おしっこ!」とトイレに行ったと思ったら、数分後にまた「おしっこ!」と言うようになったのです。
お腹の風邪引いちゃったかな?
膀胱炎?
冷えたのかな?
と体の心配ばかりしていました。なのに、トイレに行く回数は増えるばかり。行っても出ないこともあり、「どうしておしっこが出ないの〜」と泣いてしまうこともありました。
そんな娘の姿をみて
「さっきも行ったでしょ!」
「行ったばかりなんだから、出るわけないじゃん!」
「トイレないから、少し我慢して!」
なんてきつく言ってしまったこともありました。

ですが、落ち着くどころか、悪化していったため心配になり調べてみたところ、娘に当てはまったのが「心因性頻尿」という症状だったのです。その時初めて、私はその言葉や頻尿が子どもにもあることを知りました。
この記事では、子どもの「心因性頻尿」に向き合い、どのように関わっていったかを我が家の例をあげてご紹介していきます。
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
トイレが急に近くなったのはなぜ?ストレスが関係していることも
心因性頻尿とは、病気や体の異常がないのに、トイレに行く回数が増える状態のことです。
大人にも子どもにも起こるものですが、子どもの場合は、心の不安やストレスが関係していることが多いそうです。
特に、環境の変化が重なる時期や、行事が続くタイミングなどは、子どもも知らず知らずのうちに緊張や不安を感じていることが多いのです。
我が家の娘は、不安が強く、繊細なところがあります。
そんな娘には、毎年秋ごろになるとトイレが近くなるという傾向があり、ちょうど、2学期が始まったばかりで、行事も続いていた時期と重なります。

繊細な子は脳のセンサーがとても敏感です。
例えば、先生やお友達のちょっとした表情や言葉、急な予定変更や、新しいルールなど。
大人にとっては何気ないことでも、敏感に感じ取ってしまう特性があります。
娘の場合、そんな園や学校での刺激が少しずつ積み重なると、不安や緊張が強くなり、そのストレスから、トイレばかり行く「頻尿」という症状がで始めるのだと、毎年の様子から分かってきました。
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
繊細な娘の頻尿が落ち着いた3つの関わり方
ストレスが原因の頻尿を落ち着かせるために、私が実際に意識して取り入れていたのが、次の3つの関わり方です。
・「肯定の注目」で自信を積み重ねる
・ スキンシップで不安な気持ちを和らげる
・「またトイレ?」と言わず、気にしない姿勢を大切に
頻尿の症状がでてきたということは、脳の中は不安や緊張でストレスでいっぱいになっている状況です。だからこそまず、脳に溜まってしまったストレスを和らげるために子供が安心できる環境を作ってあげることが大切です。
ここから、ひとつずつ紹介していきますね。
「肯定の注目」で自信を積み重ねる
環境の変化で、緊張して疲れを感じやすい時期に、不安を少しでも和らげる声かけのひとつとしておすすめなのは、肯定10:否定0の声かけです。
ママがしてほしいことや、結果が良かったりしたときだけ褒めるのではなく、無条件に肯定していくのがポイントです。
例えば、
「◯◯ちゃん、おはよう」
「◯◯ちゃん、大好きだよ」
「ごはん、綺麗に食べてくれてありがとう」
「学校おつかれさま!」
このように、何気ない毎日の中でママが優しい笑顔で声をかけるだけで、子どもは安心していきます。そして少しずつ、「自分は大丈夫かも…」「できているんだ…」と、小さな自信が積み重なっていくのです。
スキンシップで不安な気持ちを和らげる
スキンシップによって、「オキシトシン」という幸せホルモンが分泌されて、不安を感じたときに働く「扁桃体」の興奮を落ち着けてくれます。
肌が触れ合うスキンシップは、子どもの脳に安心感を与え、ストレスを和らげる効果があるのです。
特に繊細な子にとっては、ママと手を繋いだり、背中をさすったりするだけでも心に安心感を与えることができますよ。
「またトイレ?」と言わず、気にしない姿勢を大切に
「トイレ行きたい」と言われたときは、できるだけ気にせず、受け止めてあげることが大切です。本人にとっては、安心するための行動なので、「また?」「さっき行ったでしょ」とママが言うことで、不安を強めてしまうこともあるので注意が必要です。
私もこの関わり方を意識してからは、娘が「トイレ行きたい」と言っても、「うん、行っておいで〜」とだけ声を掛け、あとは口を出さないように心掛けました。
そして、遊びに集中していれば、トイレに行くことを忘れている様子もあったので、娘が夢中になれる遊びに誘って、気持ちを切り替えられるようにしていきました。

小学生になった今年も2学期の始めは、少し頻尿の症状が出ていましたが、この3つの関わり方を意識していたおかげで、2週間もしないうちに、落ち着きました。
頻尿が続くときは?受診を検討したほうがいいケースも
繊細な子の場合、ストレスや環境の変化が落ち着くと、少しずつトイレの回数も安定していくことが多いです。
ですが、2週間以上たっても頻尿が続く場合や、夜中に何度もトイレに起きるようなときは、念のため小児科で相談してみましょう。
また、次のような様子があるときも、体の病気が関係している可能性があります。
・おしっこのときに痛みがある
・発熱や腹痛をともなっている
・尿が濁っている、においが強い
・水を異常にたくさん飲む
こうした症状がある場合は、膀胱炎や尿路感染症、糖尿病などが隠れていることもあります。 検査を受けて「異常なし」とわかるだけでも、ママや子どもにとって大きな安心になります。
もし受診するときは、「いつ頃から」「どのくらいの頻度で」「どんなときにトイレに行きたがるか」をメモしておくと、医師にも伝えやすいですよ。

「トイレが急に近くなった」は、心のSOSかもしれません
娘の頻尿が続いていた時期、私は「体の問題」ばかりを心配していました。
でも実際は、娘の心がいっぱいいっぱいになって出していたSOSだったのです。
トイレの回数が増えると、ママも心配になりますよね。
でも焦らなくて大丈夫ですよ。少しずつ、子どもが安心できる環境を一緒につくっていけば、自然と落ち着いていきます。
ママが安心して関わることが、子どもの安心にもそのままつながります。
もし、同じようなお子さんの症状に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。
▼子どもの頻尿とママの関わり方が気になる方はこちら▼
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
白倉ひより