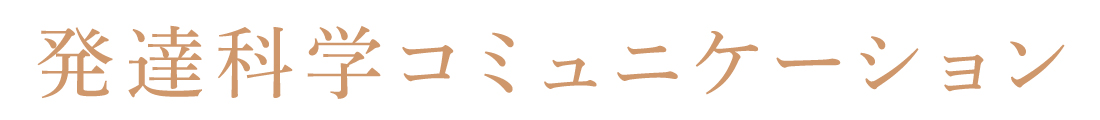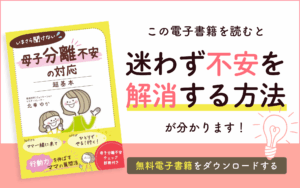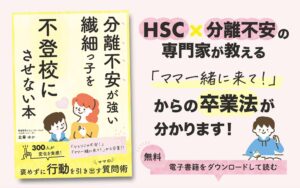「宿題やりたくない!」問題が解けないと怒るのは「分からない」のサイン
宿題で分からない問題が出てくると、突然怒り出す。
鉛筆や消しゴムを投げたり、プリントをぐちゃぐちゃにしたり…。
そんなお子さんに困っていませんか?
実は、問題が解けなくて怒る裏側には、「文章題が苦手」という原因が隠れているんです。
この記事では、
- 文章題が苦手な原因
- 我が家で効果のあったサポート法
を、息子の経験をもとにお伝えします。
我が家の小2の息子も、問題が解けないとすぐに怒っていました。
「もう嫌だ!」「分かんない!」と泣きながら癇癪(かんしゃく)を起こし、解き方を説明しようとしても「いいから答えを教えて!」と聞く耳を持たない。
最後には私がついイライラして「ちゃんと自分で問題を読みなさい!」と怒ってしまい、息子は「もうやりたくない!」と泣き出す…。
毎日の宿題タイムが、親子バトルの時間になっていました。
宿題をする様子を見ていると、計算問題はスラスラできるのに、文章題になると固まっていました。
- 問題を最後までよく読まない
- 問題の途中を読み飛ばしている
- パッと見て「分からない」とあきらめてしまう
そんな姿がよく見られました。
どうやら息子は、「問題の意味がよく分からない」というところでつまずいていたようです。

そして、宿題がスムーズに終わらない日は「明日、学校行きたくないな…」とぽつり。
宿題のつまずきが、学校へ行く気持ちにまで影響しているようで、「このままにしちゃいけない」と強く思うようになったのです。
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
「ちゃんと読みなさい」では届かない!文章題が苦手な本当の原因とは
文章題が苦手な背景には、「言葉の内容を処理する力」が弱いという脳の特性が関係している場合があります。
脳にはワーキングメモリと呼ばれる、頭の中のメモ帳のような機能が存在します。
文章題を解く時は、
・言葉を理解する
・読みながら内容を理解する
・前後の文をつなげる
といった複数の処理をワーキングメモリを使用して同時に行っています。
ところが、このワーキングメモリが弱いと、
・問題の内容を読んでいるうちに忘れてしまう
・登場人物や数字の関係を整理できない
・文の流れをつかみにくい
などのつまずきが起きやすくなります。

つまり、“頭の中で情報を整理しながら理解する力”が追いついていないので、問題の意味そのものが理解しづらいのです。
そのため、「ちゃんと読みなさい」と言われても、ただ読むだけでは理解が追いつきません。
「読んでも分からない!」という経験ばかりが増えて、文章題に対する苦手意識を抱いてしまいます。
では、どうしたら解決できるのでしょうか?
根本的な解決には、問題文が理解できるようにサポートするのがおすすめです!
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
少しの工夫で変わる!文章題を理解しやすくする3つのサポート
文章題の苦手意識をなくすには、「理解できた!」「解けた!」という成功体験を積ませることが大切です。
今日からできる、おうちで簡単にできる3つのサポートを紹介します。
①長い問題文は細切れにして、読みやすくしてあげる
「問題を読んでみて」と言っても、「読みたくない」「嫌だ!」と言うことはありませんか?
そんな時は、お母さんが問題文を短く区切って読んであげるのがおすすめです。
長い文章をまとめて読もうとすると、ワーキングメモリが追いつかず、読みながら内容を忘れてしまったり、文のつながりが分からなくなってしまうのです。
息子の場合も、私が細切れにして問題を読んだだけで、「そういうことか〜」とすんなり理解できることが増えました。
その結果、宿題中の癇癪はぐっと減りました。
「ちゃんと読みなさい」
「嫌だ!」
のやり取りを繰り返すより、お母さんが読んであげる方がスムーズですよ。
まずは読む負荷を減らして、「問題を理解できた!」という成功体験を作っていきましょう。

② 名前や場面を“身近なもの”に置き換えてイメージしやすく
細切れに読んでもピンとこない時は、登場人物や物・シチュエーションを子どもがよく知っているものに置き換えてみるのも効果的です。
例えば、
・問題に出てくる人の名前をお友達や兄弟の名前に変える
・問題に出てくる物を好きな食べ物やおもちゃに変える
といった具合です。
「りえさんがどんぐりを集めて・・」
「たろう君がカードを並べて・・」
など、知らない子の名前や想像しづらいシチュエーションだと、子どもは問題自体に興味を持ちにくく、内容のイメージが広がりません。
その結果、ますます問題文が“よく分からないもの”として感じられてしまいます。
子どもが日常で見慣れている名前や物に置き換えることで、情景が浮かびやすくなり、問題の意味がつかみやすくなるようになります。
「なるほど、そういうことか!」と理解のスピードがぐっと上がりますよ。
③ 図や実物を使って、見て分かる形にしてあげる
問題を一緒に読みながら、図や実物を使って視覚化するのもおすすめです。
例えば、
・登場人物や物を図で書き出す
・数の変化を矢印で書く
・できごとを時系列で書いてみる
といった形で、目で見て分かるように整理します。
実際にチョコレートやあめなどの具体物を使って考えるのも効果的です。
問題文に出てくる「あげた」「もらった」を実際にお母さんと実物を使って動かしてみると、問題の流れが分かりやすくなります。
ワーキングメモリが弱い子どもは、頭の中だけで登場人物や数字の変化を整理することが難しいので、言葉で説明するよりも視覚的な情報の方が分かりやすい場合があるのです。
息子も「分からない」と言っていた問題を、実際にあめを使って動かしてみると、 「なんだ、簡単じゃん」とスッと理解することができました。
「そっか、こういうことか!」と自分で気づける瞬間が増え、文章題への苦手意識も自然と薄れていきますよ。
できた!が増えると、宿題も学校生活もぐんとラクになる
小学3年生になった今、息子が宿題中に癇癪を起こすことはほとんどありません。
そして、「自分で解けた!」という成功体験を積むうちに、少しずつ文章題への苦手意識もなくなっていったんです。

そのおかげで、宿題の時間につぶやいていた「学校行きたくないな…」という言葉も、いつの間にか聞かなくなりました。
宿題で癇癪を起こしてしまうお子さんは、「どこでつまずいているのか」を見てあげることが大切です。
もしかすると、文章題が苦手なことが原因になっているかもしれません。
「うちの子もそうかも!」と思ったら、ぜひこの3つのサポートを試してみてくださいね。
\1日1回質問するだけ!/ \300人が変化を実感!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
▼小1の宿題癇癪でお困りの方はこちらも参考に!▼
<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
仲村まな