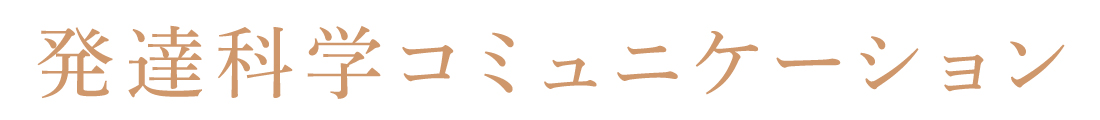宿題を始めるたびにイライラするお子さんに困っていませんか?
宿題を始めるとすぐに「分かんない!」「やだ!」とイライラするお子さんに困っていませんか?
我が家の息子が小1になり、頭を悩まされていたのが宿題の時に起こる癇癪でした。
毎日のことなので、どうにかしたい問題ですよね。
息子は宿題を始めると、「分かんない」「線がはみ出した」「消しゴムでうまく消せない」など、すぐにイライラモードに。
「ママ教えて」と助けを求めるのですが、私が教えようとしても話は聞かず消しゴムや鉛筆を投げてさらに癇癪がひどくなるので、私のイライラもヒートアップして悪循環に陥っていました。
しかし、毎日のように泣きながら宿題をしていた息子でも、今では宿題で癇癪を起こすことがなくなり、サクッと終わらせられるようになったのです!
宿題を始めると癇癪が起こるのはどうしてでしょう。その当時、息子に何が起きていたのでしょうか。

小1はストレスがいっぱい!癇癪の原因は宿題だけじゃないかも
そもそも宿題で癇癪が起こるのは、宿題だけが原因ではないかもしれません。
癇癪を起こす子は、初めてのことや変化を苦手とする傾向があると考えられます。
小学校に入学すると、それまでの保育園や幼稚園とは大きく環境が変化しますよね。
授業、給食、登下校など、初めてのことの連続です。小1の子どもは学校に行くだけでへとへとになっているんです。
疲れている時、ストレスや不安を抱えている時は脳がキャパオーバーになり、一時的に感情のコントロールが効かなくなることがあります。それが癇癪となってしまうのです。
我が家の息子も初めての小学校生活に疲れ、ストレスMAXだったのだと思います。
そこに宿題という新たなタスクが課されたことで、さらなるストレスが加わってしまいました。
それでは、ストレスMAXで癇癪を起こす子どもにどう対応すればよいのでしょうか。
いちばん大切なことは、癇癪を「習慣化」させないことです。
次で具体的なママの対応のコツをご紹介します!

癇癪に巻き込まれない!ママがやるべき対応2ステップ
癇癪を「習慣化」させないためには、ママが癇癪に巻き込まれないことがポイントです!
私は息子の癇癪に巻き込まれて、泥沼の親子バトルを繰り広げていましたが、ある対応をすることによって、帰宅後の穏やかな時間を手に入れることができました。
ママの対応のコツを2つご紹介します。
距離を保つ
感情は長続きしないという脳の特徴があります。
泣いたり怒ったりしていても、大体1〜2分で落ち着いてくるので、その感情に巻き込まれず距離を保って待ってみましょう。
私は癇癪を起こしている息子に、
「どこが分からないの?」
「泣いてちゃ分かんないよ」
などとしつこく話しかけていました。
すると、息子はさらに激しく泣きわめき、悪循環に…。
癇癪を起こしている脳はキャパオーバーになっているので、話しかけるのは火に油を注ぐようなものなのです。
それが分かってからは、癇癪が始まったら距離を保つことに徹しました。
息子が癇癪を起こしている最中は、気づかない振りをして、料理や掃除など他のことに集中。否定的な表情、態度、言動をしないように気をつけました。
余計な口出しをせず距離を保つようにしてからは、癇癪を起こして数分後に何事もなかったように息子から話しかけてくるようになったのです!
1〜2分で落ち着くことが分かっていると、私も癇癪に対して過剰に反応せず、落ち着いて距離を保つことができました。
宿題を中断して気持ちを切り替える!
癇癪を起こしている時は、感情系の脳が集中的に使われていると言われています。
脳は同じ場所を集中して使っていると疲れてしまう傾向があるので、使っている場所を変えてみることが有効です。
例えば、好きなアニメを見たり、好きな音楽を聞いたりして目や耳を使うことで気持ちを切り替えることができます。
息子は相撲や戦いごっこで体を動かし、声を出すことで気分がスッキリするようでした。
また、別のものを差し出して気をそらすことも有効です。
我が家では、癇癪が少し落ち着いてきたところで「おやつにする?」とブレイクタイムを作っていました。
すると、好きなお菓子で気持ちを切り替えることができ、落ち着いて宿題を再開することができました。
色々試してみて、ぜひお子さんに合った方法を見つけてみてくださいね。
5月からは本格的に授業も始まり、宿題の量が増えたり内容が変わったりする時期かもしれません。
多くの子どもたちが心身ともにストレスを抱えやすい時期でもあるので、親子共にリラックスして、無理せず過ごしていきましょう!

<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
仲村まな