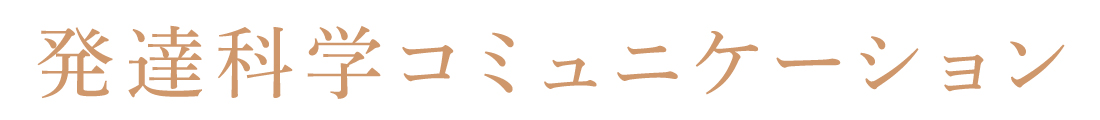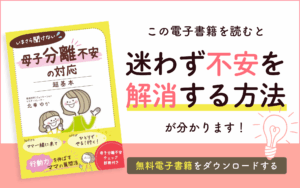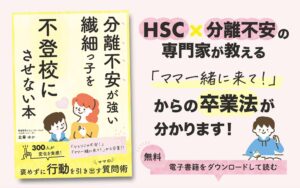新学期早々に始まる運動会の練習。登園しぶりが始まっていませんか?
新学期が始まり、少しずつ生活リズムが戻ってきたかなと思ったらすぐに、運動会に向けての練習が始まる園も多いのではないでしょうか?
運動会を楽しみにしている子がいる反面、繊細な子にとっては運動会が苦手で「幼稚園に行きたくないな…」という気持ちになることもあるのです。
実は、我が家の繊細な娘もそうでした。
2学期、園で運動会の練習が始まると、「運動会嫌い!」と登園しぶりが始まりました。
・頑張って!
・ママ、運動会楽しみにしてるね〜
といった励ましの言葉をかけていたのですが、繊細な娘にとってはそれがプレッシャーになってしまい、状況はどんどん悪化してしまったのです。
当時の私は、「周りの子ができているのだから、うちの子もできるはず」と思っていました。
ですが、繊細な子には、脳の特性から、園での運動会の練習が私が思っている以上にとてもハードだったのです。

この記事では、運動会を目の前にして登園しぶりが強くなった我が家の娘が、練習に少しずつ参加しながら、本番を笑顔で迎えられるまでの関わり方をご紹介します。
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
繊細な子が「運動会嫌い!」になるのは、脳の特性が関係していた
繊細な子がなぜ「運動会練習」を負担に感じるのか?
ここでは、繊細な子の脳の特性を2つお話させていただきますね。
1つ目は、環境の変化に弱いという傾向があります。
例えば
・いつもと違うスケジュール
・学年ごとの練習のため、いつもと違う先生
・暑いなかでの練習
・周りの子に合わせなきゃ行けない場面が多い
このような、いつもと違う=イレギュラーな状況に対して、繊細な子はたくさんの刺激を過敏に受け取り、私たちが思う以上に、強い不安やストレスを感じているのです。
我が家の娘も、予定が変わったり、いつもと違うことがあると「どうしたらいいの…」と不安が強くなります。 いつもと違うことにうまく対応できず、不安が積み重なって、だんだんと練習そのものがつらくなっていった様子がありました。
2つ目は、ネガティブな出来事を記憶しやすいという点があります。
娘の場合、
クラス対抗リレーで、お友達から悪気なく「〇〇ちゃん、足が遅いよね~」と言われてしまったことが、娘は深く傷つき、運動会に対してネガティブな気持ちが強くなり「運動会嫌い!」に繋がっていきました。

ですが、娘の脳の特性を理解し、運動会の練習では何が負担になっているかが分かってからは、対策を考え、関わり方を工夫していきました。
どのようなことを実践したのか、次にお話させていただきますね。
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
繊細な子が運動会の練習に参加できるようになった2つの対応
ここでは、実際に、幼稚園の先生に協力してもらいながら一緒に取り組むことで娘に効果があった方法を2つご紹介します。
スケジュールの共有
1つめは、大体の園では、練習日や時間の計画はある程度決まっていると思うので、運動会当日までの練習スケジュールを事前に先生と共有することがおすすめです。
繊細な子には「事前に何をするか」を伝えてあげることで安心することができます。
我が家では、練習の予定をカレンダーに書き込んだり、ダンスの曲を事前に聞いて予習したりしていました。また、園で習ってきた振り付けを一緒に楽しく復習するなど、少しずつ前向きな気持ちに繋げていきました。
さらに、 先生から、登園した朝、その日にやることを娘に個別で伝えてもらうようにお願いしました。天候などにより、急に予定が変更するときにでも、事前にやることがわかることで、安心した様子で取り組めたようです。
スモールステップで練習に参加
2つめは、いきなりみんなと一緒に参加させようとするのではなく、少しずつ慣れていくことを、先生にも事前にお願いして対応してもらいました。
繊細な子にとって、運動会の練習にいきなり完璧に参加するのはとてもハードルが高いことです。
まずはお友達の動きを見ることで、自分もこう動けばいいんだ!と理解し、少しずつ見通しを立てて動けるようになっていくのです。
わが家の娘も、
・みんなの練習を少しだけ見学できた
・鼓笛の楽器を、自分で選ぶことができた
・昨日よりも、長く練習に参加できた
このように、小さなできたを園でも先生に肯定してもらうことで、少しずつ「私もできるかも…」という自信に繋がり、運動会の練習に参加できるようになっていきました。

そして、本番では学年代表として、大好きなダンスで前に出て踊ることができたのです。
運動会当日までは緊張した様子があったのですが、その経験が更に自信となり、それ以降、登園しぶりは全くなくなりました。
娘の変化を目の当たりにして、無理にやらせるのではなく、子どもの「やってみようかな」という気持ちを引き出すことが、何よりの力になると実感しました。
もし今、同じように悩んでいるママがいたら、今回ご紹介した関わり方が少しでもヒントになれば嬉しいです。
ぜひ試してみてくださいね。
▼学校行事に行き渋る子にママができる対応方法はこちら▼
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
白倉ひより