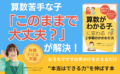「学校では頑張っているのに、
家ではやらない…」
こんな子は、
知識や計算力よりも
「自分はできる!」という感覚が
知識や計算力よりも
「自分はできる!」という感覚が
育っていないことが多いです。
2学期は、
算数好きと算数苦手の
分かれ道になる大事な時期。
算数好きと算数苦手の
分かれ道になる大事な時期。
だからこそ、
日常の小さな成功体験を
積み重ねる声かけが
とても大切です。
積み重ねる声かけが
とても大切です。
「できたね」
「いいね!」と、
「いいね!」と、
目の前の行動を認めるだけで
子どもの脳は
「やればできる!」を学びます。
が…!!
この「認めるだけ」が
意外と難しい~~!!
と感じるママは多いのです。
意外と難しい~~!!
と感じるママは多いのです。
かつての私もそうでした。
これは、
日本の躾け文化の名残で、
日本の躾け文化の名残で、
できないことを正すことが
当たり前になっているから。
ある意味仕方のないこと
なのです。ですから、
なのです。ですから、
ここから意識を変えていきましょう!
自分を責める必要はありません。
自分を責める必要はありません。
行動のゴールを細かく分解する
例えば、
計算ドリルの宿題をするとき、
計算ドリルの宿題をするとき、
「宿題を全部終わらせる」
をゴールにしてしまうと、
をゴールにしてしまうと、
褒められるのは
最後までやり切った時だけ。
でも、
行動をプロセスごとに分けると…
行動をプロセスごとに分けると…
-
宿題をやろうとした
-
宿題をやり始めた
-
最初の1問を解いた
-
半分までできた
-
あと少しのところまでできた
-
最後までやりきった
こうして細かく分けることで、
褒めポイントが増えます^^
褒めポイントが増えます^^
半分まででも…
「半分までできたね!」
「半分までできたね!」
机にドリルを広げただけでも…
「やろうとしたんだね!」
「やろうとしたんだね!」
こうして今できていることを
認めてもらった体験が
少しずつ自信に変わり、
少しずつ自信に変わり、
行動につながります。
今日、レクチャー3を
受講した生徒さんからも
こんな報告がありました。
こんな報告がありました。
「小2の息子が、今までなら
絶対にできなかった場面で
気持ちの切り替えが
気持ちの切り替えが
できるようになりました!」
毎日のかかわりが、
ジワジワと子どもに
浸透していくのですね^^
この2学期、
どれだけたくさんの
どれだけたくさんの
できた! を
経験させてあげられるかで、
経験させてあげられるかで、
算数を好きになるかどうか
が決まります!!
が決まります!!
次回は
算数嫌いな子の特性と
算数嫌いな子の特性と
脳タイプ
についてお話しします。
についてお話しします。