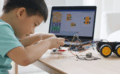「数の理解はできているのに、
学校の算数ではつまずく」
そんなお子さん、いませんか?
計算はできるのに、
やり方が自己流でミスが多い。
正しい方法を教えようとすると、
ママの言葉には反発。
「本当はできるはずなのに…」
そう思うママほど、
焦りやもどかしさを
感じてしまいますよね。
でも実は――
それって、
独創的に考える力がある証拠。
大切に育てたい
大切に育てたい
「才能の芽」なんです。
塾に通っていたTくん(小2)も
そんなタイプでした。
計算はスラスラ。
けれども、読む・書くは苦手。
けれども、読む・書くは苦手。
ひっ算を書くのを嫌がり、
文章題は数字だけ拾って式を立てる。
文章題は数字だけ拾って式を立てる。
当然、ミスが増えて
「違う!」と指摘されるたびに、
算数がどんどん
算数がどんどん
嫌いになっていきました。
私は、Tくんのやり方を
頭ごなしに直すのではなく、
「それもアリだね!」
と認めながら
できたことを一緒に喜びました。
と認めながら
できたことを一緒に喜びました。
すると少しずつ、
表情が変わっていきます。
4年生になる頃には、
「算数が得意になってきた!」と
「算数が得意になってきた!」と
笑顔で話してくれるように。
けれども、
おうちでは相変わらず
宿題バトルが続いていました。
なぜなら、ママは
「ちゃんとやらせなきゃ」
と思い、
「ちゃんとやらせなきゃ」
と思い、
Tくんは
「また怒られる」
と感じていたから。
「また怒られる」
と感じていたから。
でもね、
私が見ていて感じたのは――
私が見ていて感じたのは――
Tくんの脳が一番育っていたのは、
勉強している時間ではなく、
遊んでいる時間 だったんです。
プリントを終えて採点を待つ間、
Tくんは生き生きとお喋りし、
Tくんは生き生きとお喋りし、
ご褒美シールの台紙には
自由な発想で絵を描く。
私の机のクリップを全部つなげて、
「せんせい、見てー!」と
笑うその顔は輝いていました。
「せんせい、見てー!」と
笑うその顔は輝いていました。
好奇心のまま動いているとき、
その瞬間こそ、
その瞬間こそ、
脳が一番活発に働いている。
私はそう確信しました。
私はそう確信しました。
もしママが、
「正しいやり方」ではなく
「子どもの才能の伸ばし方」を
「正しいやり方」ではなく
「子どもの才能の伸ばし方」を
知っていたら・・・
Tくんが怒られる時間は、
もっと笑い合う時間に
もっと笑い合う時間に
変わっていたかもしれません。