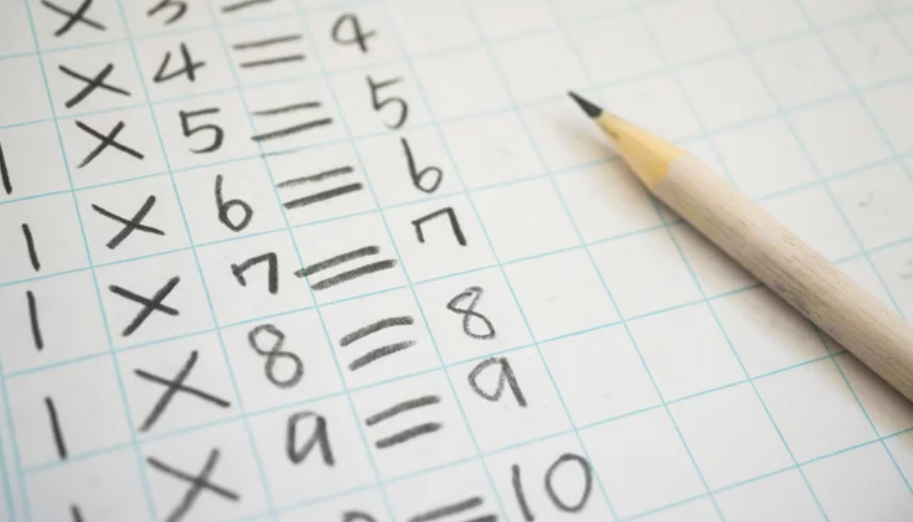先日受講生さんから
小2の娘ちゃんが
九九のテストで合格しました!
というご報告を受けました^^
嬉しくご報告を聞きながら、
冬休みをまたいで3学期になっても
まだ九九のテストがくり返されて
いることに少し驚きました。
最近は、
(いつからかわかりませんが・・)
上がり九九
下がり九九
ばらばら九九??
と、九九のテストのハードルが
高くなっていることにも
驚いています。
上がり九九だけでも
覚えるのが大変な子たちは
どうしているのか?と心配です。
おうちで楽しく練習が
できているのならいいのですが、
苦行になっているようであれば
小2の今、そこまで完璧に
九九を覚える必要はないことを
お伝えしたいです。
学校の先生は
「今覚えておかないと
3年生になったら困るよ~」と
おっしゃるかもしれませんが、
今、無理して九九を覚えさせて
算数をキライにさせるくらいなら
わり算の計算に
どうして九九を使うのか?
かけ算とわり算は
どういう関係があるのか?
あそびや体験を通して
計算の意味を理解していくこと
の方がこの先の算数の勉強に
期待が持てます。
何度繰り返しても
九九が覚えられない原因は
脳の発達と関係しています。
グレーゾーンにいる
隠れ算数障害の子どもたちは
特定の機能の発達が少しだけゆっくり・・
という子たちですから
反復練習を繰り返すと、
周りから少し遅れながらも
なんとかできてしまいます。
この「なんとかできる」ということが、
子どもたちを苦しめるのです。
学校の先生も、ママも、
子どもの自信につながると信じて
「やればできるんだから頑張りなさい!」
と叱咤激励しますが、
みんながラクにクリアしていることが
自分にはどうして
こんなにしんどいのだろう?と、
みんなと同じようにできないことに
傷つき、自信を失っていくばかりです。
算数の答えの導き方は
一つではありません。
九九表をつかってもいいし、
九九を使わずに考えてみるのも
大切な勉強です。
発達がゆっくりなだけで、
発達しないわけではないのですから、
その子のペースに合わせて
得意な所から伸ばしていくことで
追いついていくことができます。
そもそも、
すでに算数で自信を
なくしているのなら、
毎日の生活の中で
自信を育てることが先です。
遊んでないで九九を覚えなさい!
ではなく、
九九より楽しいことして遊びなさい!
と言ってあげられるママが増えると
算数嫌いな子はなくなるはずです^^