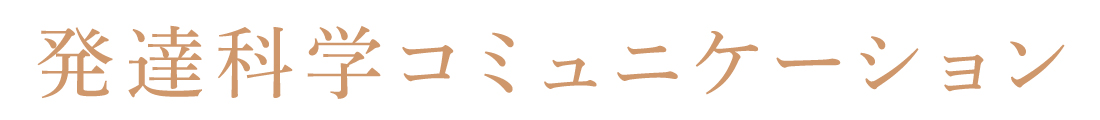「ママ行かないで!」と家の中でもついてくる子はいませんか?
母子分離不安でママの姿が確認できないと不安になりいつでも後を付いてくる。買い物など一人では待てないけれど、一緒に行くのも嫌がるため結局出かけることをあきらめなくてはいけない。そんな小学生はいませんか?
少しくらい一人で待てるようになると助かりますよね。
我が家の母子分離不安の当時小学4年生の娘は不安が強く、一人での留守番はもちろん、私が2階に物を取りに行く時や、家の前までゴミ出しに行くときでさえ一人で待つことができず、ついてきていました。
また、家の中で私の姿が見えないと何度も「ママ!」と呼んで居場所確認をしていました。
何も言わずにゴミを出しに行くと大慌てで泣きながらはだしのままついてくるなんてことも。
30mほど離れたお友達の家に忘れ物を届けるのも嫌がり、行かせてもらえないことも。
「金魚のフンはやめて!」なんて言ったこともありました。
ほんの1分も待つことができないママべったりの娘に、少しくらい待ってくれたらなと悩んでいました。

人一倍の不安の強さは脳の特性によるものでした
母子分離不安とは、母親から離れることに不安を感じたり、母親のいない場所に行くことに強い不安や抵抗を感じることです。
母子分離不安の子は不安を強く持ちやすいという特性があります。そのため、目の前のことに対する恐怖や、これから起こることに対する不安が他の人よりも過剰になりやすいのです。
小学生の娘も母親から離れる不安から、母親の姿が見えないことに不安を感じていたのでした。
恐怖とは・・・対象がはっきりしていて理由があるもの
不安とは・・・対象がはっきりしていないもので理由がないもの
恐怖は脳にとってストレスだけれど、不安はよりストレスになるのです。
不安はなくなることはないので、少しでも軽くしてあげることが大切です。では、どのようにすれば不安を減らし、ストレスをやわらげることができるのでしょうか?

分離不安のある小学生の娘にしたポイントは2つです
母子分離不安のある小学生の娘に私が実践したことは
①カウンセラーのように丁寧に会話をし、不安を軽減してあげることです。
ポイントは保留→理解→共感の順でお話をすることです。
娘は一緒についていきたくはないけれど、どうしても私が学校まで行かなければならないことがありました。
もちろん娘は「一人で待つのは無理!いかないで」と言い出しました。「大丈夫だって!」「すぐ帰ってくるから!」「行かなくちゃいけないからしかたがないよ!」
などと言いたくなりましたが、一旦その言葉は置いて保留しておきました。
そして何が不安なのかを聞き出したり、観察しました。
観察していると、一人で待つのはママと離れたくない不安、誰か来たらどうしようという不安、一人で待つという漠然とした不安があるようでした。
不安がわかったら理解し共感をします。
「ママに会えないのが心配かな?」「一人で待つのは心配になっちゃうよね」と共感をしめし、「じゃあどうしたら待てるかな?」と一緒に考えました。
家にWi-Fiのみでつながっているスマホを子供が使っていたので、「顔が見えるように電話しながらならどうかな?」と提案してみたところ「スマホで電話をつなげておけば、待ってもいいよ」と言い出しました。
学校に車で往復の5分ちょっとくらいの間でしたが、ずっとテレビ電話を繋いでおき、「今学校についたからね」「もうすぐ家に着くよ!」などと伝えました。
②できた行動に肯定の声かけでポジティブな記憶をつけ行動を引き出す
子供の脳は、言葉の中身より、表情・声色・語調などの非言語情報が先に処理されるため、優しい笑顔や明るい声、穏やかな声、アイコンタクトをするなどして子供のしたことの事実をそのまま言葉にして褒めます。
帰ったときに「一人でお留守番できたね!」と笑顔で言ったらできたことに喜んでいました。そして一人でお留守番ができたという成功体験になりました。
行動したことに肯定の声かけによるプラスの感情を結びつけることによってポジティブな記憶ができ、また行動したくなるのです。

母子分離不安があっても大丈夫!ママ行かないで!は卒業できます!
このように、分離不安のある小学生の娘に5分お留守番できたね!15分出来たね!と成功体験の記憶を作って自信が持ててきた為、通話をしながらの30分くらいの留守番はできるようになりました。
さらに自信がつき、外に友達と遊びに行く機会も増えました。また、途中から通話を切っても1時間以上一人でお留守番できるようになりました。
もう小学生なのにまだ一人で待てない。焦ってしまうと思いますが、カウンセラーのように丁寧に会話をし、子どもをよく観察して不安を軽減できる方法を探し、行動できたらポジティブな記憶をつけ自信をつけてあげましょう。

<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
澤村 祐依