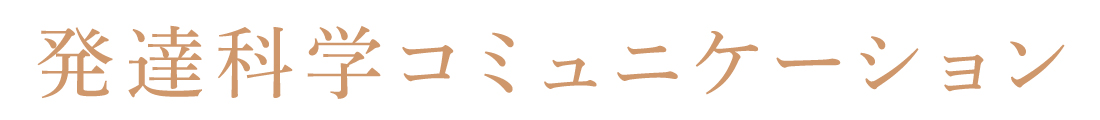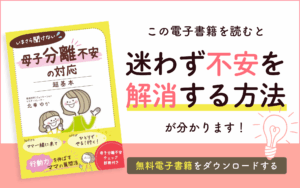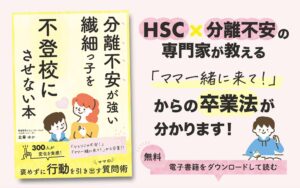給食が食べれないから、学校に行きたくない!
小学校から始まる給食。家で食べたことのない食材も多く、嫌がっているお子さんは多いのではないでしょうか?
今まで嫌いな食べ物がなくなるようにと、細かくして入れてみたり、形を変えてアレンジしてみたり。
どうにか一口は食べさせようと苦労してきたのに、なぜ好き嫌いが直らないのかとお悩みではありませんか?
我が家の繊細さんの娘も、給食のこんな悩みがありました。
・食べられる物が少ない
・残したいと言えない
・給食が嫌だから、学校は休みたい
給食が食べれなくて「学校を休みたい」と言い出した姿をみて、なんとかしなくてはと思い、娘の苦手な食材を食卓に並べて
「おいしいよ。食べてみて!」
となんとか食べさせようと努力しましたが、好き嫌いが解消されることはありませんでした。
こんなに苦労して作ったのに食べてくれない娘に、私の顔からは笑顔が消えていき、ため息が出ていました。
実は、このママのため息や無表情の顔が、繊細さんの好き嫌いを悪化させていたのです!

\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
給食が食べれないってただのわがままじゃないのか?苦手な本当の理由
①食事に対するネガティブな記憶
ママのため息や無表情が繊細さんの好き嫌いとどんな関係があるのでしょうか?
実は繊細さんは、相手の感情を読み取る力が強い脳の特性があります。
ママがため息などつくと
「ママの機嫌が悪い」→「怖いな」→「私がご飯を食べないからだ」
と自分を責めてしまいます。
そして繊細さんは1度嫌な記憶を持つと、良い記憶になかなか書き換えにくい特性もあります。
なので食事に対して嫌な記憶を残さないようにする事がポイントになります。
②感覚過敏が原因かも
繊細さんは脳のセンサーが敏感で、感覚過敏を持つ子が多いです。
揚げ物の衣が口に刺さって痛いと感じたり、野菜を噛んだ時のシャキシャキ感が苦手などがあります。
娘はお肉の脂身が苦手で、どんなに小さな脂身でも食べることはできません。
感覚過敏は無理強いすると逆効果になり、パニックを起こすことがあるので温かく見守りましょう。

\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
ママの対応がカギ!「食事は楽しい」と思わせる3つのポイント
①好きなものを食卓に出す
栄養面を考えると嫌いなものでも1口は食べてもらいたいですよね。
しかし嫌いな物を出して雰囲気が悪くなるより、好きな食べ物を食卓に出して、一緒に楽しんで食事することを大切にしましょう!
できていないことより、今できていることを見つけて、好きな物を美味しそうに食べていることを、褒めてあげると良いでしょう。
褒めることにより、お子さんも食べることへの自信がついてくるでしょう。
②ママの笑顔を見せる
繊細さんはママの機嫌をとてもよく見ています。
ご飯の時間はバタバタと忙しくて余裕はないかもしれません。
ぜひ、一呼吸おいて
「ご飯できたよ♡」と優しく柔らかい声のトーンで話しかけてあげましょう。
ママがニコニコと笑顔で接してあげると、お子さんも安心できますよ。
③会話をしながら楽しい食事
姿勢が悪かったり、肘をついていたりと、できていないことが気になって注意してしまいますよね。
注意ばかりになるとネガティブな記憶が多くなってしまい、逆効果になるので注意が必要です。
ぜひ親子で会話をして、楽しい食事の時間を過ごしましょう。
「今日学校の昼休みは何して過ごしたの?」
など答えやすい具体的な質問をして会話を引き出すと良いでしょう。
もしかしたら、しゃべることが苦手なお子さんの場合もあると思います。
そんな時は
「ママは今日〇〇へ出掛けてこんなことがあったの」
とママの楽しかったことを話してあげても良いでしょう。

食事のたびに「食べたくない」という娘の発言にイライラしていた我が家ですが、私自身の捉え方が変わり、今できていることに注目できるようになりました。
そして笑顔で娘を褒める機会も増えていき、食事に対するネガティブな記憶を、ポジティブに塗り替えることができました。
このような対応を続けた結果、娘に変化が現れました。
給食で苦手な頭つきの魚が出てきたのですが、少し食べることができたのです!
「意外とおいしかったよ」
こんな感想を聞いて、娘の中で少しづつ苦手な食べ物に挑戦しようという気持ちが育ってきていると実感しました。
いかがでしたか?ポイントは食事の時間をいかに楽しく過ごすかです。
みなさんのお家でもぜひやってみてください。
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーションアンバサダー
川澄みさ