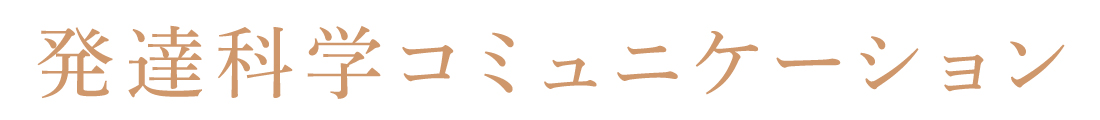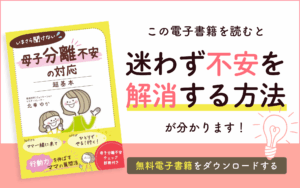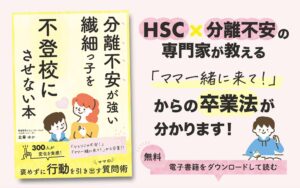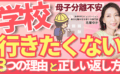夏休み明けの登園しぶりに、ママも不安になっていませんか?
長い夏休みが終わり、いよいよ2学期がスタートしましたね。
・ 朝、起きてくるかな
・「行きたくない」って言われたらどうしよう
・ 毎朝、泣いちゃうのかな
そう思うだけで、心がザワザワしているママも多いのではないでしょうか?
私も同じ気持ちを経験してきました。
我が家の、不安が強い繊細な娘は、幼稚園に通っていた頃、夏休み明けの2学期になるたびに登園しぶりを繰り返していました。
涙を浮かべながら「明日も幼稚園に行かなきゃいけないの?」と質問してくる娘に対して、
当時、私はどう受け止めればいいのか分からず、「なんで…うちの子だけ?」と一緒に不安になっていました。
そんなとき、私が頼りにしていたのは幼稚園の先生の言葉でした。
・夏休み明けは、みんなそうですよ
・幼稚園に来ちゃったら大丈夫です
・休み癖がついたら困りますから、泣いてても連れてきてください
その言葉を信じ、私は登園をしぶる娘に
・大丈夫だよ!
・頑張って行こうよ!
・行ったら楽しいでしょ?
毎朝、こんな声かけを繰り返しながら、泣いている娘の手を引っ張って幼稚園に連れていっていました。しかし、泣かないで行けるようになるどころか、朝、起きた瞬間から大泣きすることが増え、登園しぶりは悪化していったのです。
ですが、繊細な子がなぜ「行きたくない」と言うのか、脳の特性が関係していることを知り、関わり方を変えたことで、学年が上がるごとに、夏休み明けの「行きたくない」が減っていきました。
この記事では、ママのネガティブな関わり方を変えたら、子どもの不安も和らぎ、登園しぶりも解消されていった我が家の実例をご紹介します。

\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
わがままじゃない!繊細な子の「行きたくない」は脳のSOS
繊細で不安が強い子の脳は、不安を感じる「扁桃体」という部分がとても敏感な特徴があります。扁桃体は、感情をつかさどる脳の部分で、「危険を察知するセンサー」のような働きをしています。
自分の身を守るために、「怖いよ!」「不安だよ!」と脳が知らせてくれる、本能的な防衛反応を担う大切な役割があるのです。
そのため、「幼稚園=危険な場所」と脳が判断してしまったり、園での「嫌だったこと」や「怖かったこと」などネガティブな記憶を溜め込みやすい脳の特徴をしているのです。
我が家の娘もまさにそうでした。
娘は1学期に
・友達の輪に入れなかった
・先生に些細なことを注意された
・トイレに間に合わず、ちょっとだけ漏れてしまった
このようなことがあったのですが、これらのことをネガティブな記憶として溜め込んでいました。
夏休み中に、忘れられればいいのですが、繊細な子はずっと心に残っていて、2学期が始まる時に過去の記憶から、
・どうやって友達の中に入ればいいのかな
・また注意されたらどうしよう
・失敗したらどうしよう
など、まだ起こってもいない事まで心配して、不安でいっぱいになってしまうのです。その不安から「行きたくない…」という言葉につながってしまいます。
これは、「わがまま」ではなく、子どもの脳が「怖い」「嫌だ」と感じてしまっている状態なのです。
そんな時、「どうして行きたくないの?」「行かなきゃダメ!」と問い詰めたり叱ったりしても、子どもの不安はかえって逆効果になってしまいます。
なので、まずは、子どもが安心できる関わり方を意識していくことが大切なのです。

\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
繊細な子が不安を和らげるために、ママができる3つのこと
夏休み明けの「行きたくない」にママはどう向き合えばいいのでしょうか。
ここでは、私が実践したことを3つご紹介しますね。
できていることを肯定する
「すごいね」「えらいね」といった、漠然とした褒め言葉ではなく、具体的に伝えることがポイントです。
例えば
・「おはよう!今日は自分で起きてこれたね」
・「朝ごはん、食べ始めたんだね」
・「着替え、自分で選べたね。可愛い!」
このように、どんなに小さなことでも大丈夫です。「できたこと」に注目することで、子どもは「自分はできているんだ」と自信になり、次もやってみようと行動しやすくなります。
逆に「まだ着替えてないの?」「なんでグズグズしてるの?」と「できていないこと」に注目してしまうと、脳がネガティブモードに入り、思考や行動が止まってしまうのです。
また、繊細な子の脳は、ポジティブなことは記憶に残りにくく、ネガティブな言葉は何倍にもふくらんで記憶されてしまうため、このようなママの何気ない一言が、子どもを更に不安にさせてしまうこともあります。
私は、自分がやってほしいことではなく、娘が今できていることに意識を向けて声をかけるようにしました。
すると、だんだんと「ママに褒められるのがうれしい!」という気持ちが芽生え、
着替えも手伝わないとできなかった娘が、こっそり隠れて着替えて「ママ、みて〜ジャーン!」とサプライズしてくれるようになったのです。
表情や声のトーンに気を配る
繊細な子は、言葉より先に、ママの「表情」や「声のトーン」をキャッチします。
ママのちょっとした顔つきや口調が、子どもの不安を強める原因になることもあります。
だからこそ、子どもに声をかけるときは、
近くに寄って、笑顔で、ゆっくり・優しい声を意識してみてください。これだけでも、子どもの気持ちはずいぶん安定します。
私も、つい声を荒げてしまいそうになることがありました。
でも、そんな時こそグッとこらえて、あえて言葉ではなく、笑顔でうなずいたり、「グッジョブ!」のサインを出すように心がけました。
すると、自分の気持ちも落ち着き、娘にも安心感が伝わったように感じました。

ママの気持ちを整える
3つめは、ママ自身が子供の不安に巻き込まれないことが大切です。
おすすめなのは、「きっと行きたくないって言うだろうな」と身構えておくことです。
大人も、長期休み明けには「仕事行きたくないな〜」と思うことがありますよね。
子どもがそう言えるのは、素直に気持ちを出せている証拠と受け止めてみてください。
例えば
・夏休み明けだもんね〜
・ママもそういう時あるな〜
などと共感しながら、自分がやりたいことをすることがおすすめです。
私自身は、「行きたくないって言われたらこう返そう」とあらかじめ決めておいたり、
「じゃあ洗濯物でも干そう」とベランダに出て少し距離を取ったりして、娘の言葉に振り回されずに過ごせるようになりました。
このような対応を意識し、私自身が迷わず対応できるようになったことで、娘も年長の夏休み明けは行き渋りがみられたものの、2週間ぐらいで乗り越えることができ、運動会や遠足にも楽しく参加することができました。
小学校1年生になった今、娘は、新学期、行きしぶる様子もなく、お友達と待ち合わせをして元気にスタートしています。
子どもの休み明けの登園しぶりに悩んでいるママは、是非、試してみてくださいね。
少しずつ、登園しぶりは解消していきますよ。
\1日1回質問するだけ!/
母子分離不安の子の
行動力を伸ばす方法がわかります!
▼▼▼
\300人が変化を実感!/
「ママ一緒に来て!」から卒業する方法
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーション アンバサダー
白倉ひより