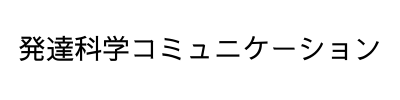こんばんは!
昨日は感情にいい悪いもないからこそ
負の感情も受け止め、感情を肯定することが
親子のイライラを抑える第一歩ですよ!
とお話ししました!
子どもの「怒りっぽさ」は
今や家庭内のことに限らず
社会問題の1つです。
不登校が35万人を超え、
問題視されていますが、
実は怒りによるトラブルも
年々と増加しているのは
ご存知でしょうか。

この図からもわかるように
学校においての暴力トラブルは右肩上がり。
特に問題視されているのが
小学校低学年でのトラブルの増加です。
一部のデータでは約5年で3.6倍に増えた
というものもあります。

参考:文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
これはかなり問題が
大きくなった状態での数字なので
家や学校での
「癇癪」や「怒りの爆発」は
おそらくもっと増加している
と考えるのが妥当です。
・本人の感情調整の低下
・ストレス耐性の低さ
がその原因とも言われています。
そのため国の教育方針を定める
「学習指導要領」には
子どもたちに「生きる力」を育むために
アクティブラーニングや
SEL(感情教育)を取り入れる
カリキュラムが組まれています。
が!!!
実際、現場では
先生方の人数が減っているのに
問題は増えていて、
トラブルを消す対応に追われ
前向きなプログラムは
中々実装されていないのが現状です。
では私たち親は
何をしたらいいのでしょうか。
怒りっぽさは
『感情を扱う力が育ちきっていないサイン』
だからこそ、
おうちでの関わり方を変えることで
子どもの未来は本気で変わります。
実は、感情の育て方は
学校よりもおうちのほうが
圧倒的に効果が出やすいんです^^
「じゃあどうやって育てるの?」
というところは
明日のメルマガでお話ししますね。
親が知っておくべき
「教育の3つのレベル」について
詳しくお伝えします。
もうすぐ2025年も終わります。
2026年、進級するわが子を
どんな状態で送り出したいですか?
・怒りが先に出る子
・感情を扱えるようになった子
この違いは、
これから数ヶ月の関わりで
大きく変わります!
一度、
ゆっくり考えてみてくださいね。
では^^