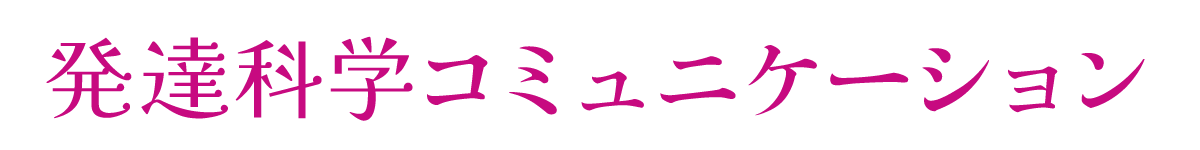さみだれ登校キッズに多い
本当はできる子なのに、
なぜ学校嫌いに
なってしまうのか?
その本当の理由を
脳の仕組みから解き明かしていきますね。
実は、
学校に行くのを嫌がる
お子さんの多くは、
知的能力や創造性
共感性などの面で
共感性などの面で
どちらかといえば
優れた力を持っている
ことが多いんです。
特に発達凸凹タイプの子や
環境変化に敏感なお子さんは、
その豊かな感受性ゆえに、
学校という環境に過剰に反応
してしまうんです。
脳科学の視点から見ると、
これには明確な理由があります。
発達特性のあるお子さんの
脳は、
脳は、
情報の処理の仕方が少し独特。
例えば、
同時に入ってくる色々な情報を
適切に「ふるい分ける」機能
(感覚フィルター)が弱いことがあります。
その結果、
教室内のささやき声
廊下の足音
蛍光灯のチカチカ
給食の匂い…
こうした
「他の子には気にならない」
刺激が全部同じ強さで
脳に入り込んで、
処理しきれなくなって
「パンク状態」になってしまうんです。

また、
不安が強いタイプのお子さんは
「予測できない変化」に対して
すごく強いストレスを
感じます。
急な予定変更
あいまいな指示
暗黙のルール
など、学校生活は
予測できない要素だらけです。
こんな状況で、
お子さんの脳は常に
ストレスMAX!
「警戒モード」に
なっているので、
本来は学習や友達づきあいに
使うべきエネルギーの大部分を
「環境への対処」に使ってしまうんです。

それは疲れますよね。
さらに見逃せないのが、
「完璧主義」の傾向です。
特に自閉スペクトラム症の
特性を持つお子さんには、
間違えるからやらない!
わからないからやらない!
という考え方にとらわれて
動けなくなってしまう子。
(まさにうちの長女がこれでした)
一度失敗した経験や、
友達から笑われた記憶が
強く脳に刻まれて、
もうあんな思いはしたくない
という回避行動につながるんです。
家では
リラックスして話せるのに、
学校では緊張して言葉が出ない。
家では集中して
取り組めることも、
教室では気が散ってしまう。
こういう違いは、
環境によって脳の働き方が
大きく変わることによって
起こります。
起こります。
ある意味、お子さんは
学校という環境に
「適応しようと頑張りすぎて」
疲れちゃっているんですね。
学校どうだった?と聞いても
「別に…」
「忘れた」
と答えるお子さんの中には、
言いたいけど、言葉にできない
そんな思いが
いっぱい詰まっていることも
実は多いんです。

ママとの安心できる
会話を通して
お子さんの脳は少しずつ
ストレスから解放されて、
本来の力を発揮できるようになります。
例えば、言葉にできない
思いをアウトプットさせて
不安を解消するために
「学校にいる時
こんな風に感じることある?」
と具体的に聞いてみる。
「教室の音が大きい!うるさい
って感じる?」
「給食の匂いで気持ち悪く
なることある?」
そんな風に聞かれて初めて
自分の感じていた違和感に
気づくお子さんもいます。
お子さんとの会話で
引き出した想いを
きっかけにして
きっかけにして
春休み中から少しずつ
準備したり、
学年の先生に事前に
相談することもできますよね。
苦手を受けとめてもらう事で
何でも話していいんだよ
というメッセージが伝わり
新年度の不安が軽くなります^^
失敗や困ったことを
共有できる関係性が、
お子さんの脳の回復力
(レジリエンス)を高めます!
お子さんの「本当の力」を
引き出すママに
一緒になりましょう^^