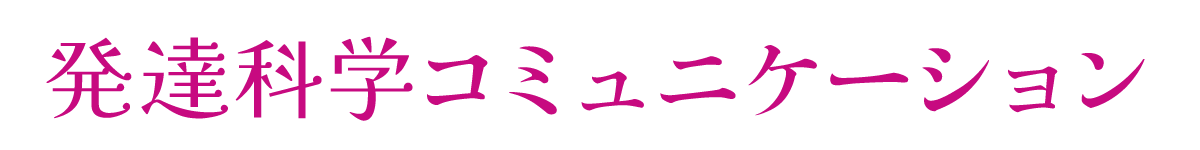小学生の娘の激しい癇癪に疲れ果てていた私
毎日のように繰り返される終わりの見えない癇癪。
・そんなことで!?と思うような本当に些細なことで怒り出す。
・自分の思い通りにならないと「バカ!」「大嫌い!」など暴言を吐き続ける。
・上手くできないことがあると物に当たる。
そんな娘の言動にイライラしてしまい、最後はいつも親子バトルに発展していました。
こんな子どもの泣き喚く声が毎日のように響きわたる家庭は普通じゃないと、わが家の光景を異常だと感じるほど癇癪に振り回されていました。

でも実は、発達障害・グレーゾーンの子どもの癇癪にはちゃんと“理由”があったのです!
発達障害・グレーゾーンの子に激しい癇癪がおこる原因
・気持ちをうまく言葉にできない
・思い通りにならないときに我慢がきかない
・怒りや不安のスイッチが入りやすい

優しく接する、寄り添う、というのが正しい対応だと思っていました。
つまり、癇癪のときにいくら言葉で落ち着かせようとしても子どもはそれを受け取れる状態ではないため効果はありません。
むしろ、火に油を注ぐようにますます激しくなってしまうこともあるんです。
じゃあどうすればいいのか?そこで必要になるのが「対応の順番」でした。
褒めたり、寄り添ったりするのが間違っているのではなく、そのタイミングが大事な秘訣なんです。
▼叱っても褒めてもやらない子の切り替え力が伸びる!
\表紙をクリックしてダウンロードできます/
癇癪が減り、自分で切り替えられるようになる!お母さんにできる対応法
発達障害・グレーゾーンの小学生の激しい癇癪の正しい対応の順番とは何か?
お母さんにして欲しい2つの対応の順番があります。
◆スルーする
まずは、癇癪をおこしてもスルーすることです。
だから癇癪の最中は、あえて反応せずにスルーします。
・視線を合わせない
・身体を向けない
・否定的な言葉や表情を見せない
こうすることで、その行動ではお母さんから注目を得られないと子どもが学習し、癇癪を続ける意味がなくなっていきます。
私は、娘の激しい癇癪が始まったら、洗濯物を取り込む、晩ご飯の下ごしらえをするなど家事に没頭します。
娘がしつこく付いて回るときには「お腹が痛い…」とトイレにこもることもありました。
娘の癇癪のことを考えるのをやめて、あえてこの時間を活用しようと他の事に意識をむけることを心がけ、娘が落ち着くまで待つようにしました。
癇癪がおこるのは親のしつけのせいではありません。自分を責めないでください。
◆褒める
癇癪がおさまったら、子どもが気持ちを切り替えて落ち着いたことをすかさず褒めてあげてください。
褒めてもらうことで子どもは安心感を抱きます。
「泣き止むことができたね」
「自分で落ち着くことができたね」
など、具体的に褒めてあげます。
褒められることで「癇癪をやめた方がいいことがある!」と感じるようになります。
そうすると次第に切り替える力が育っていきます。
娘は癇癪をおこして落ち着くと、「泣き止めたよ」と自分から話してくれるようになりました。
私は、冷静に何事もなかったかのように「自分で落ち着けたんだね」としっかり褒めます。

最初は難しく感じるかもしれません。
だけど、スルーというのは無視ではなく、落ち着きを待つための温かい関わりなんだと理解できると揺るがず対応できるようになります。
お母さんが、発達障害・グレーゾーンの特性を理解して正しい対応をすると、小学生の子どもであっても癇癪は確実に減っていきます!
そして何より、「この対応でいいんだ!」と自分の対応に自信をもつことができます!
癇癪に振り回される毎日から抜け出し、親子でニコッと笑い合える時間を増やしましょう!