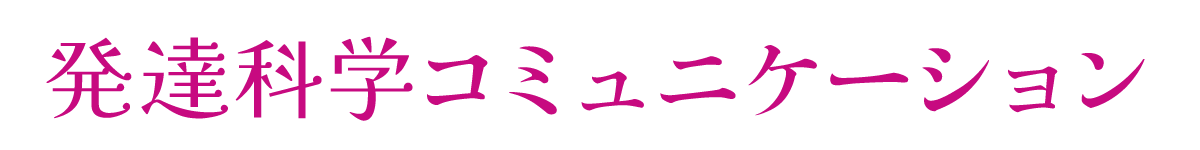お風呂の時間になるたびに、マイペースでなかなかお風呂に入らない時、イライラしませんか?発達障害の子の特徴をとらえて、「お風呂イヤイヤ」の奥にある、子どもの脳のしんどさとそこに気づいたママの関わり方の変化についてお伝えしますね。
どうしてこんなに毎日お風呂を嫌がるの?イライラの毎日
毎日の生活の中で「お風呂」は生活の中で、欠かせないことの一つだと思います。

だけどそのお風呂、毎日「めんどくさい」「入りたくない」と言っていつまでも入らないことありませんか?
私の娘は、繊細なASDっ子です。低学年のうちは一緒にお風呂に入り、特に問題はありませんでした。
だけど、学年が上がり、一人でお風呂に入るようになってから状況が変化してきました。
お風呂に入ることを毎日のように「めんどくさい」と言って、いつまでもお風呂に入らずに、時間ばかりが過ぎていく状態でした。
そんな状況に毎日イライラしていました。
また、お風呂に入るという娘を信じて、順番を待っている家族もなかなか順番が回ってこないため、他の家族もイライラすることもありました。
お風呂に入るという行動、実はたくさんの工程をこなしている
♦︎実は「お風呂に入る」って子どもにとっては10個以上の行動を切り替える“ミッション”なんです。
娘の「お風呂めんどくさい」の言葉から、お風呂の工程について考えてみました。
・まずはお風呂の後に着るための下着などの準備
・服を脱ぐ
・身体や髪の毛を洗う
・湯船に浸かる
・お風呂から出たら身体を拭く
・着替えた後には、髪の毛を乾かす
など、たくさんの工程を一人でこなさなければなりません。
発達特性がある子は、段取りの切り替えや「次に何をするかを予測する力」が苦手なため、この工程が“めんどう”に感じやすいのです。

これまで、私と一緒にお風呂に入っていたため、それほど面倒に感じてはいなかったのかもしれません。
大きくなれば、当然一人でできるものと感じてしまいます。できないことにイライラしてしまいがちです。
だけどお風呂に入るという行為が、娘の負担になっていたことに気がつくと、どうしたら娘がスムーズにお風呂に入れるようになるのか考えてみました。
間違った対応は逆効果
そこでまず、私が行ったことをお伝えします。
お風呂になかなか入ろうとしない娘の行動を一旦は見守ることにしました。
見守ったあと、娘がお風呂に入るための行動をなにかしたら、すかさず「着替えを持ってきたんだね」などと声かけを行いました。
だけど、娘はそこからスムーズには動き出してはくれず、時間ばかりが過ぎてしまうこともありました。
結局、私もイライラしてしまい、我慢ができずに、余計な一言を言ってしまうこともありました。
そこから当然娘は不機嫌となり、時には癇癪を起こすこともありました。

また、娘は時々「お風呂がつまらない」「どうしたらお風呂に楽しく入れるのか」などと言ってくることがありました。
嫌いなことをさせると、脳に負担がかかるため、脳の活動はストップしてしまいます。
嫌いなことをさせるためには、楽しいことを組み合わせることで、行動力がアップします。
そこで、私はお風呂を楽しくするために、音楽を流しながらお風呂に入ることを提案しました。
最初のうちは、その提案を受け入れて、お風呂に入る前に、好きな音楽を選び、その音楽を聴きながらお風呂に入っていました。
最初のうちは、これまでやってきたことではなかったため、楽しそうに好きな曲を選んでいました。
だけど、これもだんだんと飽きてしまい、長続きしませんでした。
音楽を選ぶ時間がかかること、音楽を選ぶことも面倒になっていたようでした。
子どもがどうやってお風呂に入りたいかが大事!時にはお風呂に入らない選択も悪くない
間違った対応を踏まえて、私が行って、娘が少しずつ変化してきたこと、また、私自身もお風呂に対する考え方を変えてみたことで、娘の行動も変化してきたことをお伝えします。
まず、一つ目はとにかく、娘のお風呂に入ろうとする行動を見守りました。
正直、「いつになったらお風呂に入るのだろう」「次の人がお風呂に入りたいのに・・・」などという感情が湧き上がり、イライラもしてきます。
でも、ここではとにかくその感情を一旦保留しておきます。
すると、「シャンプーするのがめんどう」「今日はどうしてもお風呂に入りたくない」などと、娘の気持ちが吐き出されてくるようになりました。
娘が伝えてくれた言葉を一旦受け入れて、できそうな状況であれば、「今日はシャンプーをしてあげようか?」などと提案します。
娘がそれを受け入れてくれた時は、娘のシャンプーを手伝ってあげることが二つ目です。
娘の負担と思っていたことを少しお手伝いしてあげると、その後の行動がスムーズになりました。
いつもよりお風呂にかかる時間も短くなり、娘本人だけでなく、他の家族の待ち時間も短縮することができました。
三つ目に、どうしてもお風呂に入りたくない日は、「お風呂に入らなくても良い!」と私自身が考えることにしました。
娘が「どうしても今日はお風呂に入りたくない!」と言ってくる時は、無理にお風呂に入らせとようとはせずに、「今日はお風呂お休みにしてみたら」などと声かけしてみました。
「〇〇するべき」という思考が強い娘なので、最初のうちはお風呂に入らないと汚い」などと言って怒ってしまうこともありました。
しかし、私が穏やかに伝え続けてみると、「今日はお風呂に入らなくてもいい?」などと、娘の方から聞いてくるようになり、そんな時は「いいよ」と穏やかに娘に返事をしてあげました。
するといつもなら、なかなか朝起きてこない娘も、翌日シャワー浴をするために、早めに起きてシャワー浴をする姿もみられました。
夜にお風呂に入らないという選択を続けた結果、夜にお風呂に入らないで寝ると「体も気持ちも不快感」感じるようになり、夜にお風呂に入らないという選択はかなり減ってきました。
こんなやりとりを続けているうちに、娘の行動も変化してきました。
娘の方から「今日は湯船に入らずに、シャワーだけにしよう」
「シャンプーするのがめんどうだから、湯船に入るだけにして、明日の朝、シャンプーをしよう」などと自分で考えて、行動できるようになりました。
そんな時は「それもいいね」などと、娘の選択したことを受け入れる言葉かけをしました。
時には、お風呂に入る予定ではいるけれど、今は入りたくないという時には、他の家族にお風呂の順番をゆずるということもできるようになりました。
基本的にはお風呂に入ることは「めんどくさい」という考え方は変わりません。
・まずは娘の行動を観察
・時には、お風呂に入るためのお手伝いをしてあげる
・「お風呂に入らない」という選択もあり
と私自身の考え方を少しだけ変化させることで、娘の行動も変化してきました。
お風呂に一人で入ることはできるけれど、「めんどくさい」と言ってなかなかお風呂に入ってくれないお子さんへ、よかったら試してみてくださいね。
執筆者:岩瀬 紗和
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)