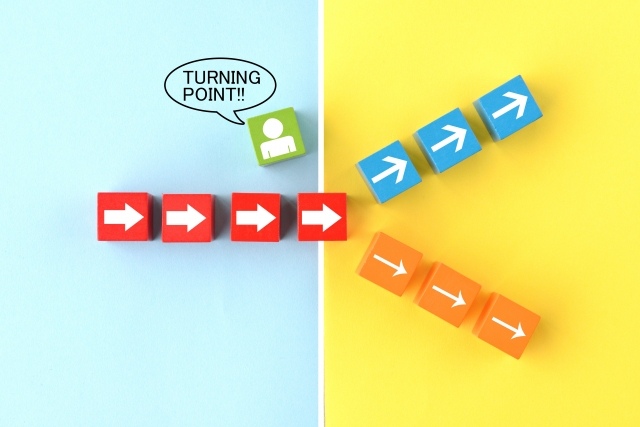褒めても癇癪が減らない!ADHDタイプの脳の特性
「褒めているのに、なんでまた癇癪?」
「このままで小学校に行けるのかな?」
そんなふうに、子どもの将来がふと心配になること、 ありませんか?
実は頑張って褒めているのに癇癪が減らない。
そう悩むママはとても多いんです。
でもそれには、ちゃんと理由があります。
ADHD(注意欠陥多動性障害)タイプのお子さんの癇癪が減らない主な3つの原因

①「ネガティブな記憶」を強く、長く残しやすいという脳の特性
・少し注意されただけでも、心に深く刺さる
・否定的な言葉ばかりが頭の中に残る
・褒められたことよりも叱られたことの方を強く覚えている
こうした傾向があるため、 いくら褒めていても、たった一つの否定が全てを打ち消してしまうことあります。
②「完璧じゃなきゃダメ」という思い込みを抱えやすい
頑張り屋で繊細な子ほど、 失敗=ダメな自分と受け取りやすい傾向にあります。
その結果、うまくいかない→自信をなくす→癇癪爆発という悪循環が生まれてしまうのです。
③褒められることに慣れていない
ADHDタイプのお子さんは失敗が多く、日常的に「注意」や「指摘」を受けることが多いもの。
だからこそ、褒められても「どうせ次は怒らる」「うそでしょ?」と 素直に受け取れないことがあります。
褒めることが少ない環境では、安心してママの言葉を受け取れる関係づくりから始めることが大切なんです。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

褒めるよりも指摘が多かった過去の私の関わり
以前の私は、褒めているつもりでした。
なぜならば、「褒めることが癇癪を減らす第一歩」だと知っていたからです。
できたことをみつけては、「できてるね」と声をかけ、 怒らないように、できるだけ笑顔で接していました。
それなのに、 ちょっと注意しただけで、泣く、怒る、叫ぶ。
「また癇癪?」
「なんでこんなに不安定なの?」
そう思うたびに、私の中にもイライラと不安がどんどん積もっていきました。
でも、正直に言うと、 私は褒めるよりも否定の言葉をたくさん使っていたんです。

「まだできてないよ」
「何回言わせるの?」
「早くして!」
そんな言葉が、つい口からでてしまう毎日でした。
いくら褒めていても、その何倍もの否定があれば 子どもの心には「出来なかった」「怒られた」記憶ばかりが残ってしまいます。
発達科学コミュニケーションで声かけを学んだのに、当時の私は、まだそれに気づいていませんでした。
褒めているのに子どもが変わらないのは、否定の記憶が上書きしていたからなんです。
だから私は、もう一度「学んだこと」を思い出し、意識して声かけをすることに集中しました。
すると少しずつ息子の癇癪が減っていったんです。
そして何より私自身の心にも余裕が戻ってきました。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

癇癪が落ち着く!ADHDキッズに届く褒める関わり方
必要なのは「圧倒的に褒める=子どもを肯定する量を増やす」ことです!
褒めているのに癇癪が減らない。
それは、子どもの心に否定の記憶が積み重なってしまっているから かもしれません。
だからこそ大切なのは、「褒めたのに」ではなく、肯定のシャワーでネガティブな記憶を 上書きしていくことなんです。
ここで私が、実際に取り入れて効果を感じた方法を2つご紹介します。
1〉肯定:否定=8:2の黄金比を意識する
注意や指摘をゼロにするのはどんなママでも難しいこと。
だからこそ、意識的に肯定の量を増やすことが大切なんです。
肯定の割合をぐっと増やしてバランスを整えると、 子どもは「見てもらえてる」「認められている」と感じ、 安心感がぐんと高まります。

そしてその安心感が「自分はできる」「やってみよう」という自信ややる気の源になるのです。
2〉できた瞬間よりもやろうとしている瞬間に注目する。
「褒めるところが見つからない」
「できていないことばかり目についてしまう」
そんな時は、できた結果ではなく途中の姿にも注目してみてください。
肯定できるタイミングは実はたくさんあります。
肯定のタイミング例
①できたこと
「靴を自分で履けたね」「お着替えできたね」
②今していること
「頑張って字を書いているね」「お箸でご飯食べてるね」「着替えしてるね」
③やろうとしていたこと
「お、今着替え始めようとしたんだね」「宿題やろうとしてるね」
子どもは完璧にできたときよりも、「やっている途中」や「やろうとした気持ち」を認められたときに、ぐんと自信を育てていきます。
「できなかった」ではなく「やってみようとしたね」「まだ途中」でも「ここまでできたね」
その小さな肯定が、子どもの心にちゃんと届く関わりに変わっていくのです。
癇癪っ子が自ら動きだす毎日に変わった!
癇癪が多い我が子にとって 「完璧にできる」こと自体がとてもハードルの高い挑戦でした。
それなのに私は、完璧にできたときだけを褒めて できてなかったことばからを指摘していたんです。
その結果、子どもの心に残ったのは、「出来なかった記憶」「また怒られた」という ネガティブな記憶ばかりでした。
だから、私は「見る視点」をかえました。
「できた?できなかった?」ではなく、「やろうとしてたか?」「頑張っていたか?」に目を向けるようにしたんです。
視点を変えるだけで、 息子の癇癪は少しずつ減り、自分から動き出せる場面が確実に増えていきました。
癇癪を減らすために大切なのは、 叱ることでも完璧を求めることでもありません。
否定を少なくし、肯定する声かけを増やす関わり方が大切です。
もしお子さんの癇癪が減らないと悩んでいたら、今日から少しずつ「できていること」や「頑張っている瞬間」に目を向けてみてください。
あなたの見る目がかわれば、子どもの世界も、少しずつ変わっていきますよ。
執筆者:大下せいこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)


イライラ育児を卒業するためのママの声かけについて紹介しています
▼無料メール講座の登録はこちらから