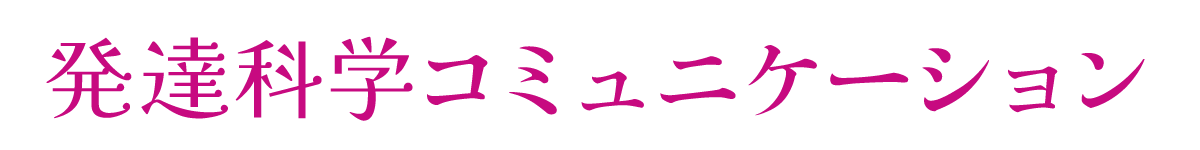今日は、学校嫌いなお子さんの
脳を育てる
親子の大事な
コミュニケーションについて
お伝えします。
脳科学の研究によると、
子どもの脳の発達には
「安全・安心の環境」
と
「適切な刺激」
の両方が絶対に必要なんです。
特に前頭前野という部分は、
「自己調整」
「計画性」
「共感性」
「柔軟な思考」
といったような脳の中でも
高度な機能を担当する場所
なんですが、
ここを伸ばすには
ストレスの少ない環境と
たくさんの対話経験が
特に大事なんです^^
凸凹キッズの多くは、
この前頭前野の発達に
独自のペースがあります。
そのため、
前頭前野の発達が未熟なことで
色々な困り事があったり
するわけですが
これは「障害」だから
治らないではなくて、
脳の「発達タイミングの違い」
なのでママの適切な声かけで
伸ばすことができるんです^^
その方法は、
脳を発達させるなら
苦手だった勉強をおさらいする
ドリルをやらせよう
ではなく、
一緒に過ごす時間が多い
春休みだからこそ
学校に適応できる力を伸ばす
もっと根本的なサポートとして
脳の土台を発達させる
ことにチャレンジしてみませんか?^^
わが家の繊細ちゃんの次女は
この春休みは、
大好きなお料理を思いっきり
やりたい!と
毎日作りたいもの
食べてみたいものの
レシピを探すことに大忙し^^
毎日色々作ってみることで
段取りがどんどん上達して
作るスピードが上がったり
段取りがどんどん上達して
作るスピードが上がったり
必要な材料を買いに
お姉ちゃんと二人で
電車に乗ったりと
私から離れて動くことが
この春休みは
格段に増えました!
格段に増えました!
ポイントはそんなチャレンジを
そんな会話で成功体験にするか?
ですよね^^
ですよね^^
この春休みは、
娘たちそれぞれのやりたいことを最優先にしながら
娘たちそれぞれのやりたいことを最優先にしながら
私も親子の会話を
成長のきっかけにしています^^
そんな春休み中にできて、
学校嫌いを解決するための一歩となる
親子コミュニケーションの
方法を3つご紹介しますね!
-
「じっくり聴く」時間を意識的に作る例えばお子さんが「学校始まるの嫌だな」と言ったとき、すぐに「お友達待ってると思うよ」と説得したり、励ますのではなくまずはその気持ちを受け止めて、「そうなんだね」「何が不安とかある?」とじっくり聴いてみる。この「ただ聴く」という行為が、実はお子さんの脳を守り、育てる貴重な時間になります。脳は「わかってもらえている」と感じると、ストレスホルモンの分泌が減って、考えたり感情を整理する機能が回復します^^
-
「選択」と「決定」の機会をたくさん作る春休み中のお手伝いでも、「これ手伝って!」とこちらがやることを決めるのではなくて、「食事を運ぶウェイターさんとテーブルを拭くふきふき大臣どっちがいい?^^」とお子さんにお仕事を選ばせる。もしくは、「お昼ごはん何食べたい?作りたいものある?」って聞くことで、お子さんの脳に「考える」「判断する」「自分で決める」という刺激を与えられます。自分で決める経験は、前頭前野の「実行機能」を強化して、自律性の発達を促しますよ。
-
「一緒に見る・感じる」を大切にする同じものを一緒に見て、感想を共有する経験は、脳の社会性の回路を活性化します^^例えば、春休み中に料理を一緒に作りながら「この野菜の色、きれいだね」「この音、面白いね」と感覚的な体験を言葉にする。お花見に行って、どの桜が一番きれいに咲いているか一緒に探してみる。こうした「共同注意」の積み重ねが、お子さんの共感性や社会性を育てることにつながります^^
この3つの取り組みで伸びる力は
一見遠回りに思えるかもしれないけれど
今よりもっと学校生活を
ラクに過ごすための
脳の発達には直結しているんです。
親子の温かいコミュニケーションは、
お子さんの脳の発達そのものを支える
おうち教育です^^
特に学校での居場所が
見つけにくいお子さんにとって、
安心できるおうちこそが
「脳が回復して、成長する場所」
なんです。
春休み中の小さな対話の積み重ねが、
お子さんの脳を育てて、
内側から未来の「働く力」を
引き出していきます^^