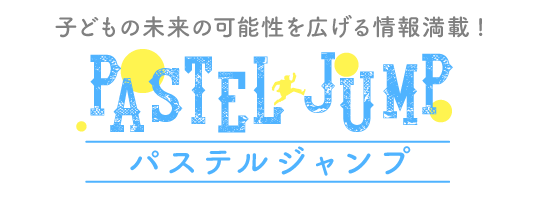環境の変化に弱い
発達グレーっ子に
やってあげたい
ホントの入学準備とは?
というテーマでお届けします!
ちなみに「入学」をテーマに
お話をしますが
進級による環境の変化でも
似た問題が起きやすいので
ぜひ置き換えて
読んでいただければ
嬉しいです。
さて、今日は
ーーーーーーー
入学シーズン
子どもにとっての
ハードルや予想される課題とは?
ーーーーーーーー
<小学校入学編>です。
なんと言っても最大のカベは
生活環境が
ガラッとかわること
です。
一口に「環境の変化に弱い子」
と言われることが多いですが
私たち大人が思う以上に
子どもたちは大変なんだよ
ということを
今日はお話をします。
幼稚園保育園までは
(園の方針もありつつ)
ある程度「自由に過ごす」ことを
認めてもらえる環境だった。
それが、いきなり
「集団」のルールに合わせて
さあみんな一緒にやりますよ!
というスタイルになるわけです。
その急激な変化に
ついていける子、
ついていくのがしんどい子、
に分かれていきます。
▼発達科学の視点で解き明かす。
不登校が続く不安を「成長のステップ」に変える、親子の対話術

メールアドレスの入力で無料でお届けします!
ー環境の変化3つのカベー
その1)指示・行動のカベ
今までは先生が近くで
「⚪⚪くん、遊びは終わりの時間だよ」
とわかりやすく伝えてくれていたのに
↓
小学校では、「一斉指示」が
基本になります。
先生は、教壇の上から
クラスみんなに向けて声をかけます。
先生の話を「聞けること」
を前提とした指導スタイルです。
ですが、
不注意の傾向があると
指示を聞きのがしてしまったり
(ADHDタイプの子に多い)
興味のないことには
反応できなかったり
(ASDタイプ:こだわり・過集中)
過敏さがあって
教室のざわざわの中から
先生の声を聞くのに
パワーを使ってしまって
ヘトヘトになる
(ASDタイプやHSCの子に多い)
などなど、
先生のお話をきく
という1つのことをとっても
発達の特性のある子には
こんなに壁があるんです。
その2)お友達関係の変化のカベ
慣れ親しんだお友達と
別の学校、別のクラスになる。
それだけでも、不安が強い
グレーっ子にとっては
ストレスなんです。
そこに加えて、
新しい先生や友達が
「ニューキャラ」として登場します。
自分を取り巻く環境が
自分のことを理解してくれている
人たちだけではなくなるのが、小学校。
そんな中で
人との関わりのつまずきを
抱えているグレーっ子は
・相手の気持ちが理解しにくい
・自分の主張ばかり
言いたいことばかり話してしまう
・気に入らないことを言われると
衝動的に手が出てしまう
・やりとりを
正確に把握できない(認知の課題)
などの特性があって
気がついたら、
友達と喧嘩してたり、
集団から抜けて
一人ぼっちで過ごしていたり、
ということが起きやすくなります。
だけど、じゃあそれを
周りの大人が指摘しようと
思っても実は難しい。
発達段階として
コミュニケーションスキルが
育つ時期と重なるので
大人も
「今はできていないだけなのかも」
「これから、上手になるのかも」
と様子を見られてしまうことが
多いんですよね。
大人が様子を見ている間に
子どもは、どんどん、ストレスを
溜め込んでいってしまいます。
自分を取り巻く
人が変わって、
刺激が増えて、
トラブルやストレスが
増えやすい、これが2つ目のカベです。
その3)勉強のカベ
小学校に上がると
書く、読む、話す、
というお勉強・授業スタイルが
スタートします。
決められた通りに、
決められた手順で、
正解を求めて、
やらなくちゃいけない、
しかもどの教科も
同じように
できなくちゃいけない、
これがグレーっ子には難しい!
書く、読む、話す、
このどれかが得意で
どれかが苦手という子も多い。
例えば、
大人のような語り口で
立派に喋るタイプの子は
一見「頭がいい」と
誤解されがち。
だけど、書くことは
苦手だったりする子もいるのです。
だけど、私たち大人は
「あれだけ立派に喋れるんだから
国語は得意なはず。」
「さあ、作文頑張りなさい」
「漢字をがんばりなさい」
という思考になりがちなんです。
他には、科目によって
苦手得意が分かれる子もいます。
算数ができるから
この子は頭がいい!
頭がいいなら
国語も、英語も、ほらがんばって!
となりがちですが
決められた「法則」にのっとって
計算をするのはできるけれど
文章は苦手
登場人物の気持ちを考えるなんて
大の苦手、なんて子も多い。
今、もし毎日学校に行けなくても
"大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
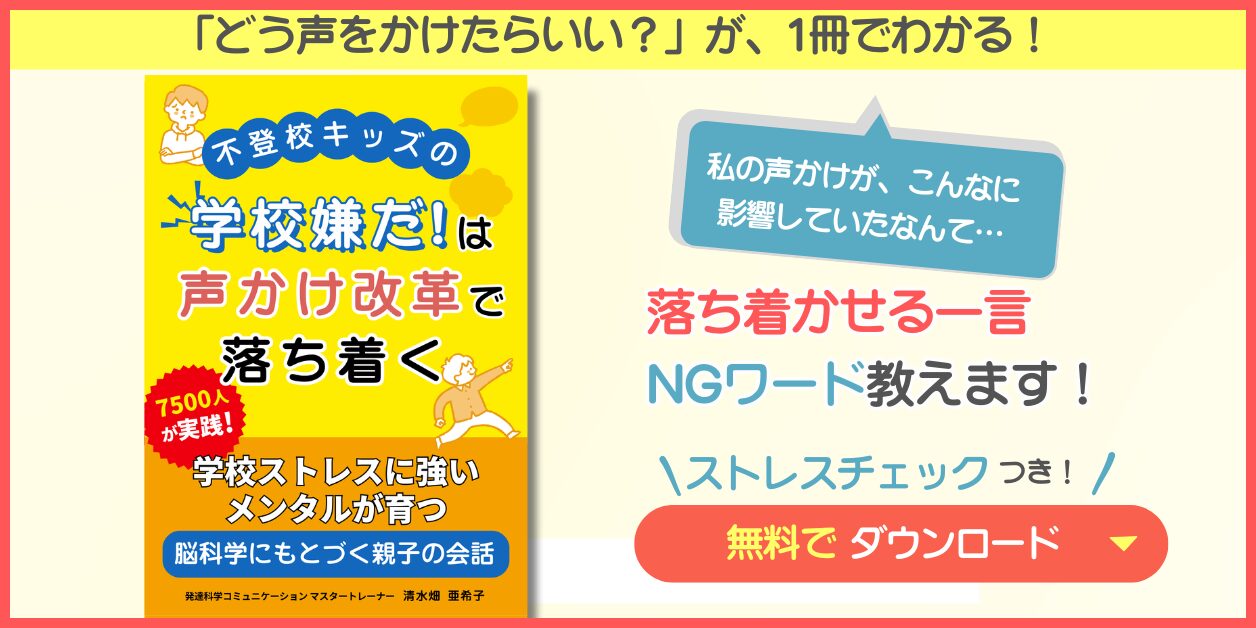
ーーー
今日ここまでお話ししたのは
本当にわかりやすい
一部の「カベ」について
整理をしてお話をしました。
ですが、子どもが感じる
カベというのはさまざまです。
だからお母さんにやって欲しいのは
「こういう時はどうしたらいいのか」
という正解をネットで
探すことではなく
「お子さんの様子をよく観察し
把握をすること」です。
お子さんが
荒れたり、鬱々したり、
笑わなくなったり、
朝起きられなくなったら、
それは、SOSのサインです。
そのサインを見逃さない
ママになるための
心構えを、最後にお話しします。
「等身大のお子さんの力を
認めてあげましょう」
もう1年生だから、
もう中学生だから、
「これができてあたりまえ」
「⚪⚪くんも頑張ってるから
あなたも頑張って」
この考え方が
お母さんご自身も
お子さんも、
追い詰めてしまいます。
グレーの子たちは
その瞬間だけ切り取ると
お友達と同じように
できていないことが
あるように見えますが
適切な関わりがあれば
ゆっくりでも
力をつけていくことができる
そんな子たちなんだよ
ということを
ぜひ知っておいてほしいです。
そうなると
おのずと、かけてあげる言葉も
変わってくるはずです。
今日は、長くなりましたので
一旦ここまで。
声かけのヒントはまた次回。
執筆者:清水畑 亜希子
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)
▼750人の生徒さんが「学んで良かった!」と納得の
脳科学に基づいた親子のコミュニケーションのコツをお届け!