ダンスを踊らない子…園や学校行事が憂鬱
ダンスを踊らない子に頭を抱えていらっしゃる方はいませんか?
他のお子さんが楽しく踊っている中、わが子だけ1人ポカンとしている。
わが子より月齢が遅い子や、学年が下の子の方が上手に踊れている。
恥ずかしいから踊らないの?
わが子は慎重派だから、最初は様子を見ているだけで、そのうち踊るようになるのかな?
わが子はリズムに合わせて身体を動かすことが、他の子より苦手なのか?
理由を考えるけれど、はっきりしたことはわからずママの不安は募る一方…。

特に保育園や学校の行事で、1人だけダンスを踊らない子を見ると、
「他の親御さんはうちの子を見てどう思っているのだろう?」
と気になってしまうこともあるのではないでしょうか?
【期間限定ダウンロード】
毎日の親子バトルは卒業!
冬休み明けを穏やかに過ごしたい親子へ♪
今だけ!!無料ダウンロードはこちらから
↓↓↓
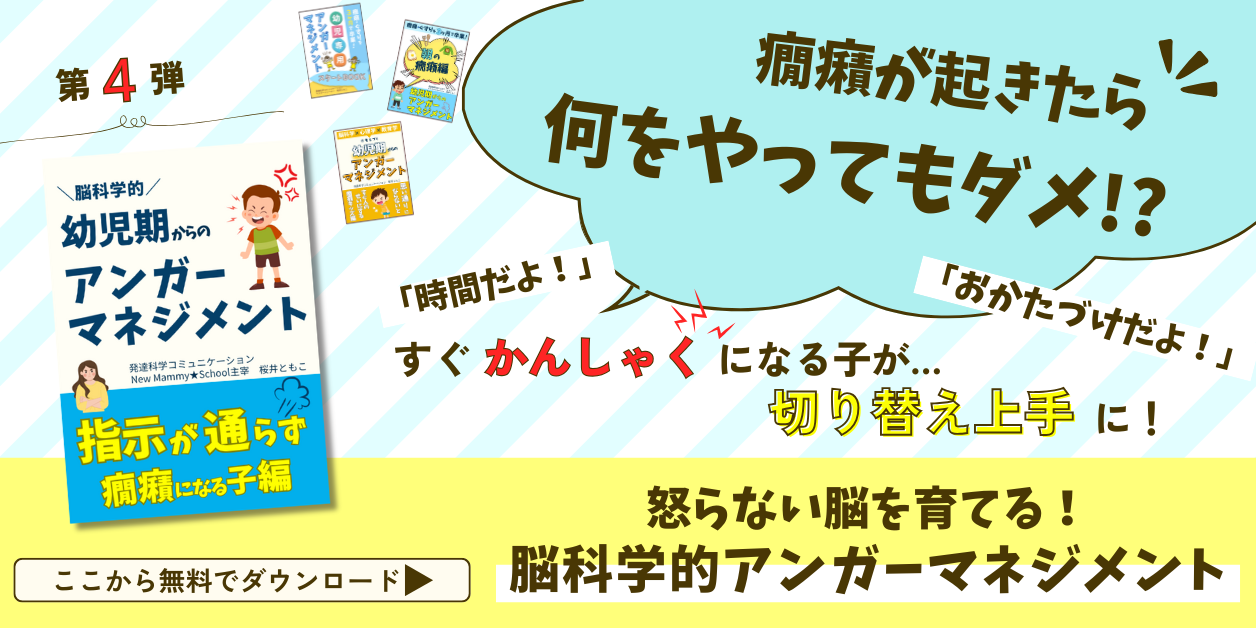
運動会でダンスを踊らない子→発表会で目立ちすぎる子
娘は入園前から、子育てサロンなど未就園児が集まる場でも、ダンスを踊らない子でした。
それどころか、ダンスの時間は他の子どもたち輪に入ろうともしない。

年少の運動会も棒立ち。
入園しても「ダンスを踊らない子」というのは変わらず、「保育園に入ったら…」という私の期待は大きく裏切られました。
先生の笛の合図があっても、隊形移動(前列と後列の交代)もしないでずっと後列にいる。
クラスごと輪になる場面でも、先生に連れて行ってもらわないと動けない。
かと思えば、同じく年少時の保育園の発表会のダンスでは、1人だけみんなと違う動きをして保護者の注目の的となる。
「お願いだからみんなと同じようにダンスを踊って!悪目立ちしないで!」
これが私の願いでした。
「他の親御さんの撮影の邪魔になっていたら申し訳ない」
「周りの目が怖い」
という気持ちもあり、園行事はいつも憂鬱でした。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

ダンスを踊らない子…原因はこの2つだった!
ダンスを踊らない子、原因の1つはボディイメージの苦手さと言われています。
ボディイメージとは、自分自身の身体に関するイメージのことです。
自分の体の幅はどれくらいか、どれぐらい力が入っているか、どれぐらい傾いているか、などを感じる能力です。
ダンスであれば、手はどのぐらい高く上げれば先生の見本通りになるか、足はどれぐらい前に出せばいいか、などボディイメージをフル活用しています。
そのため、このボディイメージが苦手な子は、リズムに合わせてダンスを踊ることが難しくなりやすいです。
結果的に大人から見ると「ダンスを踊らない子」と映ってしまいます。
また、不安や緊張の強いお子さんは、練習ではできても本番は固まってしまうことがあるかもしれません。

練習と本番では観客の有無はもちろん、先生方やお友達の緊張感も違いがありますよね。
繊細なお子さん、不安の強いお子さんはそのような違いを敏感に感じ取りやすいです。
子どもが自信を失う前に手を打つ!「事前準備」も練習しておこう!
行事以外でも、プール前の準備体操や集会など、ダンスを踊る機会は保育園だとたくさんあります。
小学校に行っても、学年によっては運動会の種目がダンス、という所もあるかもしれませんね。
子どもたちは年齢が上がるにつれて、自分と友達の違いがわかるようになってきます。
「あの子は上手に踊れているのに、自分は上手くできない」と気付いてしまうと、それだけでお子さんが自信をなくしてしまうかもしれません。
その自信のなさがますます「ダンスを踊らない子」を作ってしまう…という悪循環にもなりかねません。
そうなってしまう前に、ダンスへの苦手意識は克服し、他の子と大差なく、堂々と踊れるようにしてあげたいですよね。

また、お子さんに見通しを持たせてあげられるようなママの事前準備が、特に不安の強いお子さんにとってはとても重要になります。
進級進学や進路選びなど、事前準備や見通しがものをいう場面は今後もたくさんあります。
そのため、園行事など細かなタイミングでも、無理のない範囲で「お子さんに見通しが持てるような事前準備」の練習をしておくことは、今後も役に立ってくるはずです。
「ダンスを踊らない子」を克服するために、ママができること
ボディイメージを高める
季節や天候、住んでいる地域にもよりますが、公園遊びやプール遊び、スキーやそり遊びなど身体を大きく動かす活動は効果大です。
親御さんの金銭面での負担のない範囲で楽しんで下さいね。

お子さんの年齢によっては、お風呂で身体を洗うときや保湿のときに身体の部位を言いながら行うと、お子さんの意識がその部位に向きやすくなるかもしれません。
お家でも踊る環境を準備
好きな曲やその子が踊るのが得意そうな曲をYouTubeなどで流すことで、踊ってくれる可能性が高まります。
サビなど一部分でも構いません。
「苦手克服を先にするのではなく、その子の好きなことや得意なことから脳(発達)を伸ばしていく」という方が、脳の発達ははやいのです。
大人でも好きなことや得意なことには没頭しやすいですよね。
没頭するということはそれだけ脳を使っているということです。
脳は使えば使うほど発達します。
ダンスに置き換えると、得意な曲をどんどん踊らせた方が、ダンスが上手になるための近道、ということです!
完璧に踊れていなくてもいいです。
「ここの部分が上手だったよ」「楽しそうに笑顔で踊れていたね」などできていた所を一つでも褒めてあげてください。
そうすることで、「ママが褒めてくれて嬉しい」「また踊りたい」というお子さんの意欲にも繋がります。
可能であれば親御さんも一緒に踊ることで、子どもに「興味関心を示す」ことに繋がります。
発達科学コミュニケーションでは、まず最初に「肯定的注目」が何より大事であり、子どもの行動になぜ変化をもたらすのか、ということを学びます。
「興味関心を示す」ということは、この「肯定的注目」の1つになります。
自分がダンスが苦手だと気付いている子は、褒められても
「でも他の子と比べたら上手にできてないし…」
「◯◯ちゃんの方がきれいに踊れているもん」
と思ってしまうことがあります。
これだと子どもの自信はつきません。
そこで活躍するのが「興味関心を示す」という方法なのです!
「褒める」と違い、その子ならではの好きなことや着眼点を認めていくことになるので、お子さんが他の子と比較して自信をなくすことはありません。
お母さんがダンスを一緒に踊ってくれている(=自分の好きな曲に興味をもってくれている)ということ自体が、子どもにとっては大きな喜びとなるのです。
その子が嫌がらないのであれば、本番で踊る曲をYouTubeなどで事前に一緒に見ておくことで、不安軽減にもなります。
私が上記の手立てをとったことで、娘は年中さんの発表会(11月)では他の子と遜色なく、満面の笑みでダンスが踊っている姿を見ることができ、それはそれは感動ものでした!
ちなみに娘は、YouTubeで発表会のダンスの曲の動画は見てくれましたが、
「踊るのは保育園だけ」
と言い、家では最後まで踊りませんでした。
私が踊ることも嫌がったため、私もただYouTubeを流し、一緒に動画を見ていただけです。
さあ、次はこの記事を読んでくださっているあなたの番です!
「ダンスを踊らない子が集団生活でダンスを踊れるようになった感動」を味わっていただけるよう、心から応援しております!
執筆者:たちばな あずさ
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)


お子さんの「できない」を「できた」に変え、自信をつけていきましょう!
▼無料メール講座の登録はこちらから



