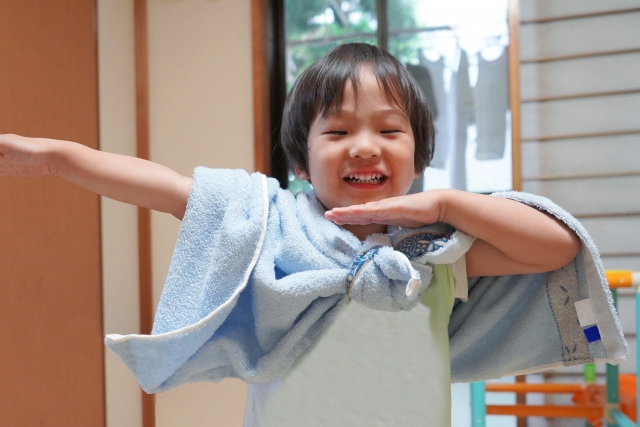子どもの発達障害をカミングアウトできない、周りが信頼できない…
子どもの発達障害や特性について、周りのママにどうカミングアウトしようか悩んでいるママはいませんか?
カミングアウトしてしまった方が私の気持ちは楽かな?
でもカミングアウトすることで、変な目で見られたらどうしよう?
他のママに勝手に話されてしまったら嫌だな。
他の子どもとの遊びの場に、自分の子どもを連れて行きたくないな。
そのお気持ち、とてもよくわかります。
私の娘はASD(自閉スペクトラム症)の診断があります。
私も半年くらい前まで、周りのママのことを誰も信頼できず、娘の発達障害についてカミングアウトしていませんでした。
なぜなら1年以上前、信頼できると思っていた保育園のママ友に娘の発達障害についてカミングアウトしたところ、勝手に他のママに言われてしまった経験があったからです。
一人にそのようなことをされると、その方以外のママも信頼できなくなってしまいました。

また、娘の発達障害に気付かれたくなくて、娘と同年代の子どもたち(凸凹キッズではない)が集まる場所に、娘を連れて行かないようにしていたこともありました。
今考えると、無意識ではありましたが、私自身、娘が発達障害であることで、娘のことを
「劣った子、できない子」
という目で見てしまっていました。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

子どもも大人も、発達障害の有無も関係ない!脳の仕組みとは?
現在は昔に比べると、発達障害も含め多様性を認める時代になってきています。
しかしそんな中でも、発達障害の子どもは世間から
「かわいそうな子、厄介な子」
という目で見られることは少なくないかもしれません。
それにより、発達障害の子どものママにとって、周りにカミングアウトしにくい雰囲気ができてしまっているのではないでしょうか?
だけど考えてみてください。
世の中に「全く同じ脳を持った人」はいると思いますか?

脳はその働きによって、大きく8つの場所に分かれます。
運動…スポーツ、手先を使うことなど
視覚…見ること
聴覚…聞くこと
記憶…覚えること
感情…自分の気持ちを抑えることや他人の気持ちがわかること
伝達…他人に伝えたいことを伝えること
思考…考えること
理解…人から言われたことやその場の雰囲気などがわかること
です。
この8つをさらに細かく分けると、その数は120になります。
120の場所の働きの組み合わせをかけ合わせていくと、82億(2025年現在のだいたいの世界の人口)より多くなります。
つまり、発達障害の有無にかかわらず、世の中に「全く同じ」人は1人としていないのです。
また一口に「発達障害」と言っても、特性の出方は十人十色であるのはこれが所以です。
発達障害があろうとなかろうと、苦手なことは誰にでもあるし、得意なことと苦手なことの差(凸凹)が全くない人はいないのです。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

子どもの発達障害のカミングアウト、タイミングはいつ?
私の住んでいる自治体もそうですが、地域によっては、他の子どもやママとの付き合いは12年間(保育園から中3まで)続くことになります。

そのため、早い段階で自分の子どもの発達障害についてカミングアウトしておくことで、助けてもらえることも増えるかもしれません。
一方で、現代でも発達障害について差別的な目を向けてくる人や、周りに言いふらしてしまう無神経な人も少なからずいます。
長いお付き合いになるからこそ、カミングアウトはタイミングを見て、慎重になった方がいいかもしれません。
「発達障害」という言葉は使わない!?特性の伝え方
ここで私が取っている、娘の発達障害のカミングアウトの方法をご紹介します。
あくまでも一例として参考にしていただけたらと思います。
①娘の友達やそのママに発達科学コミュニケーション流のかかわりかたをします。
発達科学コミュニケーション流のかかわり方は、子ども大人にかかわらず、相手との関係を良好にする効果があるからです。
具体的には、
「いつも仲良くしてくれてありがとうございます」
「◯◯ちゃんお遊戯会の歌、大きな声で頑張って歌っていましたね」
など、いつもお世話になっていることへの感謝や、相手の子どもさんのいい姿をお伝えします。
②その上で、診断名を伝えるというよりも、発達科学コミュニケーションで学んだ脳科学の知識
「発達障害の有無にかかわらず、同じ脳を持った人は一人としていない」
「苦手なことはどの子どもにもある」
を思い出しながら、娘の苦手な部分について伝えていきます。
例えば、娘は一列に並んで移動することが難しかったため、運動会の行進では友達が手を繋いでくれていました。
私はその子のお母さんに年度末、このように手紙を書きました。
「〇〇ちゃんはうちの娘にもいつも明るく話しかけてくれて嬉しかったです。
娘は一列に並んで歩くことができないので、運動会の行進では〇〇ちゃんにとてもお世話になりました」

このように、カミングアウトといっても、「発達障害です」と直接的なことを言ったり診断名を出したりするのではなく、
・相手の子どもさんのいいところを褒める
・自分の子どもの苦手な部分や、それによって助けてもらってありがたかったことを伝える
という方法にしました。
辛いとき、私を励ましてくれる言葉をご紹介!
発達障害のカミングアウトというのは、相手との関係性にもよりますし、一概には言えないデリケートな問題かと思います。
私の記事を参考にしながら、ご自身の一番いいやり方を探っていっていただくのが一番かと思います。
ですが、最後に皆さんにどうしても紹介したい言葉があります。
発達科学コミュニケーションの大好きな師匠、桜井ともこさんからいただいた言葉です。
「凸凹キッズ(発達障害やグレーゾーンの子どもたち)はできない子やかわいそうな子ではなく、ジュエルの原石である」
私も今でも娘の子育てに挫けそうになることはありますが、この言葉を軸に頑張れています。
一緒に「ジュエルの原石」を磨いて、凸凹キッズの可能性を最大限引き出していきましょう!
執筆者:たちばな あずさ
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)


ママも子育てに自信を持ち、凸凹キッズの得意な面をさらに伸ばして行きましょう!
▼無料メール講座の登録はこちらから