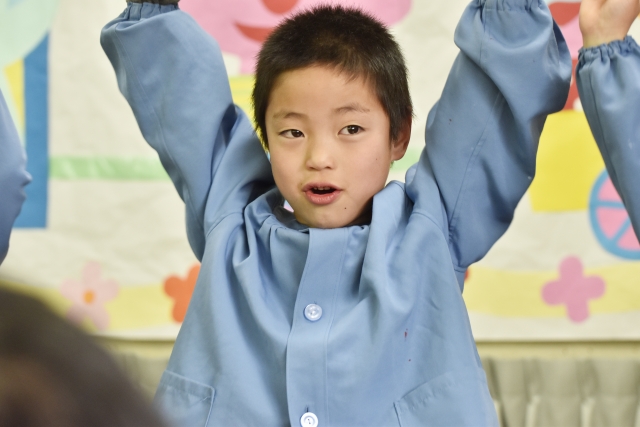進級やイベント時期に癇癪や登園しぶりがでるADHDキッズの特性
今まで楽しく通えていた幼稚園、突然行きたくない! と子どもが言ったり、家でも外でも何だか急に癇癪が増えたと 感じた経験はありませんか?
我が家の息子も幼稚園で、発表会の練習が始まった頃に、 癇癪、登園しぶりが始まりました。
では、何が原因なのか…。
原因がわからずこんな状態が続いたら不安になりますよね。
それは、ADHD(注意欠陥多動性障害)タイプのお子さんの衝動性やワーキングメモリーの弱さ、先延ばし癖からくる「見通しを立てることが苦手」ということや、「失敗体験の積み重ねから自信喪失」ということに原因があるかもしれません。

【ADHDタイプのお子さんの特性とは?】
①衝動性
自分のやりたいことや興味のあるものを優先してしまうから思い通りに動けない。
つまり、今は遊びたいから発表会の練習はしたくないという気持ちになってしまう。
②ワーキングメモリーの弱さ
一時的に記憶を保持する容量が少ないため、優先順位をつけて行動できなかったり、何をすればいいかわからなくなる場合がある。
つまり、いつもは遊んでいる時間なのに、今日はどこで何をするの?とわからないから不安になる。
③先延ばし癖
興味のあること・ないことの差が大きいため、興味のないことは後回しにする傾向がある。
今は遊びたいから、練習は後にしようと遊びを優先させてしまう。
④ADHDに伴う不注意や多動性・衝動性などの特性が原因となり、「頑張っているのにうまくいかない」という悔しい思いや「またやってしまった」という失敗体験の繰り返しの積み重ねにより、「どうせ頑張っても僕にはできない」「また怒られる」など、自信を失いがちになる。
【期間限定ダウンロード】
毎日の親子バトルは卒業!
楽しい冬休みを過ごしたい親子へ♪
今だけ!!無料ダウンロードはこちらから
↓↓↓
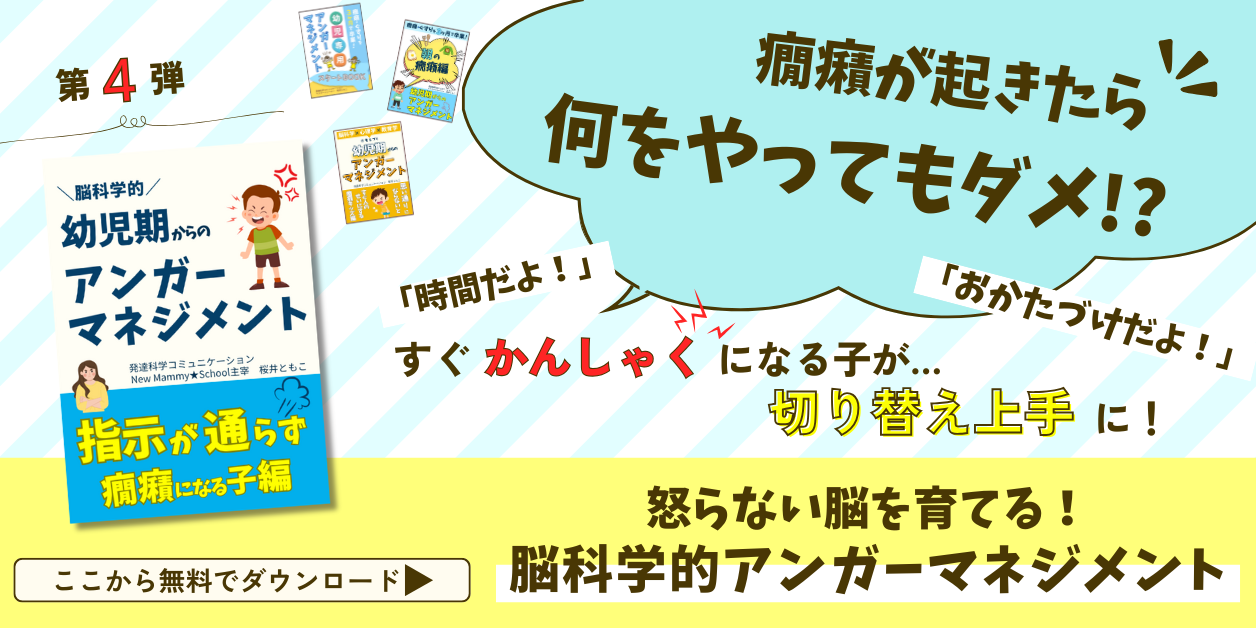
癇癪や登園しぶりを悪化させたママのNG対応
私は、「幼稚園行きたくない!」という息子に対して、「早くいこうよ、幼稚園楽しいよ?」と早く行くようにせかしたり、 息子の言葉に耳を傾けることもしませんでした。
なぜならば、仕事や幼稚園に遅刻したらいけない、予定があるから早く行かなきゃいけないという思いが強かったからです。
さらに、些細なことで癇癪を起こす息子にイライラして、なんでそんなことで怒るの? と私も怒り返して、さらに癇癪がヒートアップするという悪循環な毎日でした。
そんな日々をなんとかしなくてはと思っていた私は、 発達科学コミュニケーションで学んだ声かけを徹底することにしました。
すると、次第に癇癪は落ち着いていき、登園しぶりも解消していきました。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

癇癪と登園しぶりを解消する対応2ステップ
私がおこなった対応は2つです。
1)脳がママの声かけを受け取る土台を作る
2)行動を引き出す3ステップの関わりをする
1)脳がママの声かけを受け取る土台を作る
まずは肯定の声かけを増やすことです。
肯定の声かけには、自分が行動できているということを気づかせ、 良い行動を増やす効果があり、自信につながります。

「お着換えできたね」「靴はけたね」という声かけや goodやokのジェスチャーでできているよ! を沢山伝えていきましょう。
2)行動を引き出す3ステップの関わりをする
登園渋りが出ているお子さんの脳は否定の言葉に敏感になっています。
次の3ステップで脳が動き出しますのでやってみましょう。
登園渋りが出ているお子さんの行動を引き出す3ステップ
①ママの気持ちを一旦横に置いておく
いきなり「これやろう!」と誘っても脳は動きません。
また、やりたくない気持ちの時に「やろう!」と誘われると、 ママの声かけをできていない自分に対する否定の声かけと捉えるお子さんも多いです。
まずはママの気持ちを一旦横に置いておきましょう。
②子どもの気持ちを否定せず、受け止める
自分の気持ちを否定をされると、 防衛本能が働き、ADHDタイプのお子さんは「癇癪」をおこしてしまう場合があります。
スキンシップなどをとりながら、 ママは子どもにとって安全な場所であるということを示していきましょう。
③子どもの気持ちを代弁する
子どもの発する言葉をそのまま受け取らないことが大事です。
子どもは自分の気持ちをうまく言葉にできないため、 子どもが話す言葉の裏にはどんな意味が隠れているのか、 どんなことを感じて、何を分かって欲しいのかを汲み取り、 ママが気持ちを代弁してあげましょう。
実際に私がやってみた声かけはこんな感じです!
1⃣まずは、歌を歌いたくない・幼稚園に行きたくないという息子の思いに対して、歌を歌って欲しい、幼稚園に行って欲しいという私の思いは一旦保留します。
2⃣次に「どうして?」「楽しいよ!」「行こうよ!」と急かしたりせず、「そっか、そっか」と気持ちを受け止めます。
この時に、子どもの様子をみながら、抱っこをしたり、ぎゅーっと抱きしめて、話を聞くようにしました。
3⃣ADHDタイプのお子さんは特に自分の気持ちを言葉にすることが苦手なので、「歌の練習嫌なんだね」「練習が辛いんだね」「だから幼稚園に行きたくないんだね」と息子の気持ちを代弁していきます。
このように1⃣2⃣3⃣の順番で対応していくと、子供は、自分の気持ちをわかってもらえたと感じるので、息子も幼稚園に行く!と行動し始めたのです。
さらに、幼稚園でも先生に、「歌や劇の練習も頑張っていますよ!」と言ってもらえるようになりました。
登園しぶりが出ているような時には「行動を引き出そう!」と ママもあれこれ声をかけたくなりますが、 実は無理に行動を引き出しても子どもは「否定された!」と余計に 行動できなくなるお子さんが多いです。
脳が動き出すためにはステップがあるんです。
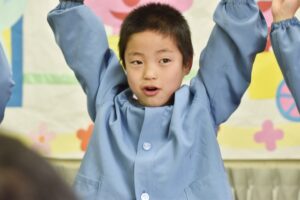
私がこのように対応を変えたことで、息子は幼稚園や練習も休むことなく、無事、発表会に参加することができました。
最後まで堂々と舞台に立つ姿に本当に感動しました!
環境の変化で不安定になりやすいADHDタイプのお子さんには、肯定を増やし、自信をつけてあげることがまず大事です。
そして、成功体験を積み重ねていけば、ADHDタイプのお子さんもいろんなことに挑戦できる子に変化・成長していけます。
ぜひ、否定ばかりせず、お子さんのできていることに注目し、子どもの変化・成長を喜べるママになってくださいね。
執筆者:大下せいこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)


「怒らない脳」を育てるママの声かけをたくさん紹介しています
▼無料メール講座の登録はこちらから