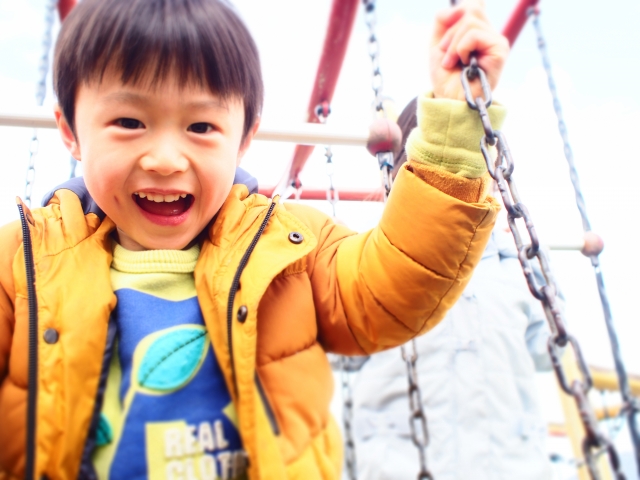「ママやって!」が癇癪につながるADHDタイプの脳のクセとは?
「ママやって」一人でできそうなことまで頼んでくる。
そして、「もう自分でやって!」と突き放すとすぐに泣きだして癇癪。
そんな毎日に困っていませんか?
実は、この「できない」にはちゃんと理由があります。
それはADHD(注意欠陥・多動性障害)タイプのお子さんに多い脳のクセが関係しているのです。
1、実行機能の弱さ-行動のスイッチが入りにくい
ADHDタイプの子どもは、脳の前頭前野の働きが未熟で 「やろう」と思ったことを実際に行動に移す実行機能が弱い傾向にあります。
大人から見れば「できるでしょ?」ということも、 子どもにとっては
・スタートを切れない
・手順を組み立てられない
・最後までやりきれない
という壁があるのです。
2、ワーキングメモリの弱さ-手順を覚えておけない
「靴を履いて」
「カバン持って」
「帽子かぶって」
こうした一連の手順を、頭の中で覚えながら進めることが苦手です。
一人でやろうとすると途中で「次は何だっけ?」 と混乱し、不安や焦りが募っていきます。
だからこそ、「ママやって」と頼ることで安心しようとするのです。
3、感情コントロールの未熟さー癇癪に直結する。
「やろうと思っているのにできない」 この小さな挫折が積み重なると、子どもの心に強いストレスが生まれます。

感情を調整する脳の仕組みも未熟なADHDタイプの子はそのストレスをうまく処理できず癇癪として爆発してしまうのです。
「ママやって!」は怠けでも甘えではありません。
それは「まだ一人では不安」「助けてほしい」というSОSのサインなのです。
親がこの背景を理解できると、対応は大きく変わります。
「サボっている」と突き放すのではなく、「やろうとしているんだけど難しいんだね」と受け止めることで、子どもの心は安心し、自立への一歩を踏み出せるようになります。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

自立させなきゃという焦りから見えなくなっていた息子の気持ち

当時の私は、息子が一人で出来そうなことでも「ママやって」と言って来るたびに イライラしていました。
「なんでこんなこともできないの?」
「もうお兄ちゃんでしょ!」
「小さい子に笑われちゃうよ?」
そんな言葉を口にしては、「自分でやって!」と突き放す日々。
なぜならば、私はとても焦っていたからです。
息子は3月生まれで、同じ学年でも一番幼く、しかも男の子。
周りのお友達が当たり前に出来ていることを、息子だけができないように見えて、「どうしてうちの子だけ?」と不安になっていました。
「そろそろ自立させないと」
「このままじゃ置いていかれる」
そんな焦りが、私をどんどん追いつめていきました。
だから、息子が「ママやって」という度に、「甘えている」ように見えてしまったのです。
でも、本当は、息子は「甘えていた」のではなく、「助けて欲しい」というSОSを出していただけでした。
私はそのサインに気づかず、できない姿ばかりに目を向けていたのです。
そんな私が、発達科学コミュニケーションで声かけと脳の仕組みを学び、対応を変えたところ、息子が一人で行動できるようになっていったのです。
自立は急がせるものではなく、安心の中で育つものなんだと気づきました。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

やらせるより手伝う!ADHDタイプの子の自立を育てる関わり方
まず大切なのは、突き放すのではなく「手伝って成功体験につなげること」です。
子どもはできたという成功の積み重ねから自身と自立心を育てていきます。
ここで、私が実際に行って効果のあったADHDタイプの子の「自立につながる4つの手伝い方」をご紹介します。
1、いちばん大事なことは「笑顔で対応すること」
子どもは言葉よりも、表情や声のトーン〈非言語〉を敏感に受け取ります。

ママが笑顔で「やってみよう」を声をかけるだけで、子どもの脳は安心し、行動のスイッチが入りやすくなります。
逆に、ため息混じりや険しい表情で対応すると、「やっぱりできない」「怒られるかも」と不安になり、行動が止まってしまうことも!
だからこそ、「笑顔で対応」が自立を支える第一歩です。
2、全部ではなく「ちょっとだけ手伝う」
いきなり全部を任せるより少しだけ一緒にやることで成功体験を作ります。
・袖に腕を通すだけ手伝う
・靴下のつま先だけを一緒に入れてあげる
・トイレは入口まで付き添って「ママここにいるよ」と伝える
こうした「ちょっと手伝う」が、子どもの「自分でできた!」という自信を育てます。
その自信が次に行動への意欲を生み出すのです。
3、「できたね」をすぐに伝える
行動できた瞬間に、「できたことをその場で言葉にして伝えること」が大切です。
「最後までできたね」
「ここまで一人でできたね」
ありのままの「できた」を言葉で伝えると、「ママがみてくれてる」「認めて貰えた」という安心感が生まれます。
この繰り返しが、子どもの自己効力感(やればできるという感覚)を育て、「次もやってみよう!」という自立へ繋がります。
4、どうしても無理な時は全部手伝ってもОK
「やっぱり無理」となった時は、無理にやらせる必要はありません。
一度ママが全部やってあげることで、子どもの脳は安心を取り戻します。
その安心が次のチャレンジのエネルギーになります。
やらせることよりも、安心を渡すことが先。それが、自立への最短ルートです。
癇癪が減り、自分から動けるようになった息子の成長
対応を変えてみたところ、少しずつですが、 息子は自分で行動できることが増えていきました。
もちろん今でも「ママやって」と言ってくることはあります。
そんなとき、私はできる限り笑顔で対応することを意識しています。
忙しいときは、ついイラっとしてしまうこともある。
けれども、「まだできないところ」よりも 「ここまでできるようになった」という成長に目を向けられるようになりました。
「手伝うって、自立には遠回りじゃない?」と そう思うママもいるかもしれません。
だけど、実は逆なんです。
ちょっとの手伝いで「できた!」を積み重ねる→自信がつく→自己効力感が育つ この流れが出来れば、ADHDタイプのお子さんでも必ず自分の力で動けるようになります。
手伝うことは「甘やかし」ではなく、「自立への近道」
子どもの「ママやって!」その裏には、「一人じゃ不安」というサインが隠れています。
その気持ちを受け止めながら、一歩ずつ一緒にできたを積み重ねていくことが、本当の意味での自立につながっていくのです。
焦らず、比べず、今日の「できた」を一緒に喜んでいきましょう。
執筆者:大下せいこ
(発達科学コミュニケーショントレーナー)


イライラ育児を卒業するママの声かけをたくさん紹介しています
▼無料メール講座の登録はこちらから