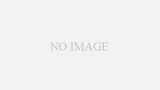「過干渉をやめたい」と感じている方へ。つい過保護に手や口を出してしまうその関わり方、実は子どもの脳の成長チャンスを奪っているかもしれません。子どもの自信や自立心を育むために、親ができる関わり方をお伝えします。
1.なぜ親はつい過干渉になってしまうのか
「つい子どものことに手や口を出してしまう」
「先回りして準備してしまう」…
そんな経験、ありませんか?
これは多くの親が感じる“あるある”です。
特に、子どもが一人っ子だったり、育児にしっかり向き合ってきた方ほど、子どもの困る姿を見るのがつらくて、つい助けたくなってしまいますよね。
また、私自身もそうでしたが、高齢ママの中には「やっと授かった大切な子だから、失敗してほしくない」という思いが強く、自然と『なんでもやってあげる』育児になってしまうことがあります。
でも、そこには思わぬ落とし穴があるのです。

2.「やってあげる」が当たり前だった過去の私
私は高齢出産で40代に息子を授かりました。今、小学4年生の発達凸凹のある息子です。
なかなか授からなかった分、「息子が困らないように」と何でもやってあげる、手を貸すという育児スタイルでした。
それが『正しい愛情のかけ方』だと思って疑いませんでした。
でも、小学校に入っても、私がやっていることが幼稚園時代から全く変わっていないことに、ふと気づいたんです。
そして小学3年生のとき、担任の先生との相性が合わず、学校に行けなくなる出来事が起きました。
そのとき初めて、「ああ、息子には自信と自立が足りなかったんだ」とハッとしたのです。

3.過干渉が子どもの脳の成長を妨げる理由
子どもが「自分でやる」ことは、実は脳の成長に直結しています。
脳は、自分で考えて行動したときにこそ、活発に働き、学びや経験として蓄積されていきます。
でも、親が代わりにやってしまうと、行動したのは親の脳。
子どもの脳はほとんど使われずにチャンスを逃してしまうんです。
息子がやればできる自分のことを、過干渉の私が代わりにやってしまったことで、息子は脳が成長するチャンスを逃してしまっていたのです。
その結果、子どもは「自分でできた!」という成功体験を積むことができず、自信が持てなくなってしまいました。
つまり、過干渉は子どもを助けているようで、実は大事な成長のチャンスを奪っている可能性があるということです。

4.過干渉をやめたい人に伝えたい、親のかかわり方のヒント
「過干渉やめたい」そう思ったとき、まず大事なのは「待つ勇気」を持つことです。
子どもはまだ未熟です。でも、だからこそ「信じて見守る」ことが、親にできる最大のサポートになります。
もし失敗しても、「どうして失敗したの?」「ほら、だから言ったじゃない!」と責めるのではなく、「次はどうしたらうまくいくかな?」と一緒に考える。
そのような親子のコミュニケーションを続けることで、子どもは少しずつ『考える力』と『行動する力』を育てていけます。
そして、できたことを見つけたら、どんな小さなことでもたくさん褒めてください。
それが子どもの「できる!」という感覚を強く育て、自信へとつながっていきます。
過干渉をやめることは、簡単ではありません。
でも、子どもの未来のために、今日から少しずつ「見守る」育児にシフトしていきませんか?
親が『がんばる』のではなく、子ども自身が『がんばってみたい』と思える関係性を育てていく。
それが、子どもの脳の成長を助ける最良のサポートになるのだと、私は実感しています。

*よくある質問・ご相談はこちら*
Q.ついつい口や手を出してしまいます…これって過干渉?
Q.ママべったりな子どもが自立できる関わり方は?