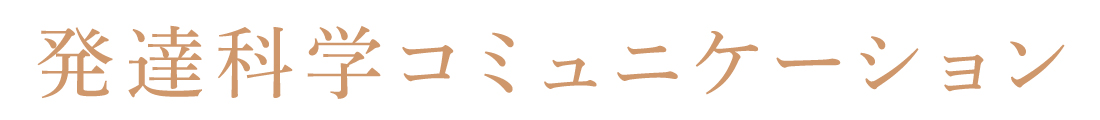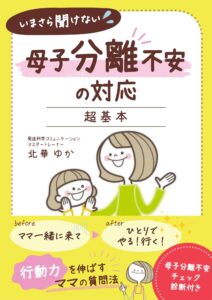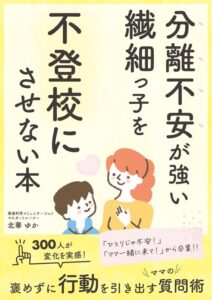反抗期じゃないかも?キレやすさの裏にある子どもの不安
うちの子最近なんだかやたらイライラしてない?
前はもっと穏やかな子だったのに・・・反抗期?
キレやすい子どもにお悩みの方はいませんか?
ちょっとしたことですぐにイライラして反抗してくる子どもを見ていると、こちらもイライラしてしまいますよね。
もしかしたら、そのお子さんのイライラには不安が関係しているのかも知れません。

我が家の娘もキレやすい子どもで、
家具をよけ切れずに少し足がぶつかっただけで「なんでこんなところにイスが置いてあるの!」と怒り出したり、
「お菓子が見つからない!」と食べたいお菓子が見つからないことに大騒ぎして壁に八つ当たりしていました。
どうしてこんなにも些細なことですぐに怒るのかが私にはわからず、イライラしてばかりの娘に対して
「自分がよけきれなかっただけでしょ。いちいち怒らないでよ」
「もっと冷静に探せばすぐに見つかるでしょ」
と怒ってしまっていました。
そんなとき、キレやすい子どもには不安が関係していることを知ったことで私が子どもへの関わり方を変えていくと、イライラしていた娘が穏やかになっていったのです。
この記事では、キレやすい子どもの不安を緩和し、穏やかに過ごせるようになる親の対応についてご紹介します。
\子どもの不安に巻き込まれない!/
すぐできる!31日分の声かけ集付き
▼無料ダウンロードはこちらから▼
ちょっとしたことで怒る子どもの“脳の仕組み”とは?
イライラしやすい子どもは不安を感じやすいという特徴があります。
環境の変化への不安
ちょっとしたことでイライラしやすい子は不安や恐怖を感じるセンサーが過敏に反応しやすいという脳の特性があります。
脳には慣れた環境を安全だと感じる仕組みが備わっているのですが、逆を言えば新しい環境は危険だと認識して不安を感じてしまいます。
このため不安を感じるセンサーが過敏な子は、環境の変化に強い不安を感じて脳にストレスを抱え込みやすいのです。
このように、不安を感じやすい脳の特性は、不安症キッズや母子分離不安キッズが持つ特性とも共通しています。
お子さんに何となく繊細な一面があるな、今思えばあの時のあの状況は不安からくる行動だったのかなと思い当たる節があるのであれば、注意していきたいポイントです。
見通しが立たないことへの不安
また、不安を感じやすくイライラしてしまう子は、見通しを立てることが苦手という特性も持っています。
こういう場合はこうしたらいいんだという見通しを立てることができないため、状況を予測して行動したり、変化に柔軟に対応することが苦手です。
そのため、今までと違う環境や突然の予定変更に脳が適応できずストレスを感じ不安になってしまいます。
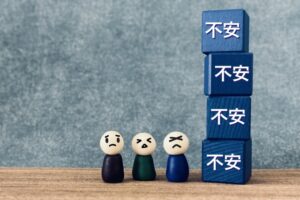
また、人間には不安を感じた時に落ち着かせてくれる脳の機能があるのですが、不安を感じやすい子はこの機能がまだまだ未熟であるため、理性が効かなくなってしまい、キレやすくなっているのです。
新学期や休み明けに要注意!イライラの引き金はここにある
実際に我が家の娘が怒りっぽくなっていたのは、新学期や長期休み明けのように、今まで過ごしてきた環境が大きく変わる時期でした。
新学期では、新しい学年になって教室が変わったり、担任の先生やクラスのお友達が変わったりしますよね。
そして長期休暇明けは、休暇中のゆったりとした生活からまた集団生活に入っていき生活のリズムが変わります。
休み明けなどは、いつもと帰宅する時間が違ったり、変則的なスケジュールで過ごさないといけないこともあります。
このように苦手のある環境の中で頑張らないといけないことに脳がストレスを抱え怒りっぽい子どもになってしまっていたのでした。
キレやすい子どものイライラは不安が強い子が出すストレスのサインだったのです。

私の娘のように、不安を強く感じやすい子どものイライラを放置してしまうのは危険です。
なぜなら、不安が強い子は我慢強いことが多く、本人も抱えている不安やストレスを言葉にすることが難しいため、知らず知らずのうちに不安が進行してしまうからです。
気づいた時には限界を迎え、腹痛や頭痛のような身体症状として現れてしまったり、ママから離れることに不安を感じて行き渋りに繋がってしまう可能性があるため、早めに対応する必要があります。
では、どのように対応したら良いのでしょうか?
\ママ一緒に来て!から卒業したい!/
HSC×母子分離不安の専門家が教えます!
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
効果立証済み!キレやすい子どもの脳を癒す2つの寄り添い方
環境の変化にストレスを感じやすい子どもの脳を癒し、イライラを落ち着かせるために私が実践した対応方法についてご紹介します。
笑顔で肯定する
脳は信頼できる大人がそばにいることで安全だと感じやすくなります。
子どもにとって一番信頼できる大人はお母さん。
お母さんがニコニコ笑顔で過ごしていることで、キレやすい子どもの脳が安全と判断し、イライラが落ち着いてきます。
私は子どもと関わる時に、笑顔を意識して、子どもがしていることに対して
「今は塗り絵をしているんだね」
「そのテレビ面白そうだね!どんなお話なの?」
と声をかけるようにしました。
こうすることで、いつも返事がトゲトゲしていた娘が
「ここはね、色を混ぜて工夫してみたんだよ」
「今ハマっているアニメなんだけどね〜」
と機嫌よく返事をしてくれるようになりました。
スキンシップをとる
スキンシップをとることで安心するホルモンが分泌されることや感情の脳が育つという効果があります。
このおかげで、情緒を安定させることができるのです。
娘が「着替えを手伝って」と言ってきたり、「抱っこして」、「ギューして」とお願いしてきた時は「あとでね」「ちょっと待ってね」と言わず要求に応じるようにしました。
こうすることで、短い時間のスキンシップでも娘が満足して笑顔になってくれるようになりました。
子どもとスキンシップをとれる時間は有限です。
お子さんが嫌がらないのであれば、もうこんなに大きくなったのに?と思わずにスキンシップタイムを取り入れていきましょう。
物の受け渡しや、さりげなく肩に手を置いたり、ハイタッチなどもスキンシップの仲間です。
抱っこやハグはさすがにもう喜ばないというお子さんには、これらを試してみてくださいね!

このように、笑顔で肯定の声かけをすることとスキンシップでお家を安全基地にして過ごせるようになったことで、キレやすい子どもだった娘のイライラも徐々に落ち着いてきて、元の笑顔を取り戻すことができました。
新学期や長期休暇明けの環境が切り替わるタイミングで、イライラしやすいなというお子さんがいたらぜひ試してみてくださいね!
\子どもの不安に巻き込まれない!/
すぐできる!31日分の声かけ集付き
▼無料ダウンロードはこちらから▼
\ママ一緒に来て!から卒業したい!/
HSC×母子分離不安の専門家が教えます!
↓↓無料ダウンロードはこちらから↓↓
<執筆者>
発達科学コミュニケーションアンバサダー
さいとうほのか