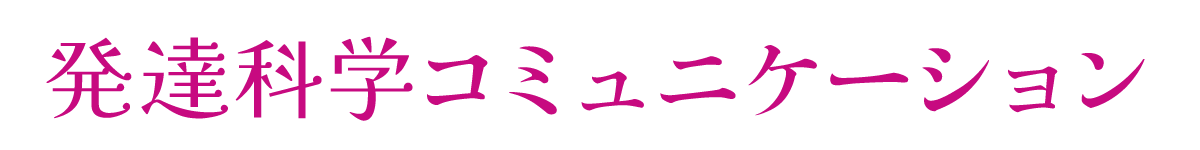行き渋りや不登校の「学校がしんどい理由」はひとつじゃない
朝、泣きながら「行きたくない」って言う。
理由を聞いても「わからない」って答える。
じゃあお休みにしようか…と言うと、家では好きなことをさせれば元気そう。
特別いじめられているわけでも学校に友達がいないわけでもない。
だからと言って叱って連れて行くのも違う気がするし、少し頑張れば行けそうなのにどうしてそんなに学校が嫌なの?もうお手上げ(涙)
というお悩みありませんか?
「うちの子、どうして学校に行けないんだろう?」
そう思いながらも、はっきりした理由が見えずに悩むママはとても多いです。
でも実は、学校がしんどくなる理由はひとつではなく、
お子さんによって 複数の困りごとが重なっていることがほとんど なんです。
「勉強が難しい」+「失敗を怖がる」
「感覚が敏感」+「分離不安」
「集団が苦手」+「賢すぎて退屈」
このように、2つ3つのタイプが重なり合うからこそ、
グレーゾーンの登校しぶりや不登校は
先生にも理解されづらく、家庭でも対応が難しいのです。
けれども大丈夫。
そのしんどさは「脳の発達の途中」によるもの。
だからこそ、脳を育てる関わり を家庭で積み重ねれば、確実に変わっていきます。
今日は、代表的な6つのタイプと、
それぞれに効く「おうちキャリア教育」の具体例をご紹介しますね。
学校がしんどくなる子の「6タイプ」
-
勉強が難しくてついていけない子→ 授業中に「わからない」が積もっていくタイプ
-
音や光、人混みなどにストレスを感じやすい子→ 学校の環境自体がしんどくて“行きたくない”につながるタイプ
-
集団の中でうまく立ち回れない子→ 距離感や空気が読めないと言われがちなタイプ
-
ママと離れるのが不安な子(分離不安)→ 学校そのものより“ママと離れる”のが怖いタイプ
-
賢すぎて“つまらない”と感じる子→ 低学年なのに達観していて、授業に意味を感じられないタイプ
-
失敗や間違いを極端に怖がる子(完璧主義)→ できない自分を見せたくなくて、やる前にあきらめてしまうタイプ
それぞれのタイプに効く「おうちキャリア教育」の具体例をご紹介しますね。
▼叱っても褒めてもやらない子の切り替え力が伸びる!
\表紙をクリックしてダウンロードできます/
学校がしんどくなる“6つのタイプ”の解決のヒント
タイプ①:勉強が難しい子
脳の状態:覚える・集中する・処理する力がまだ育ちきっていない
→「できた!」の体験を積むことで、勉強が怖くなくなり、やる気のスイッチが入りやすくなります。
たとえば料理のお手伝い。
レシピを読んで覚え、分量を測って集中して作業することで、自然に記憶力・集中力・段取り力が伸びていきます。
「おいしくできたね!」の成功体験が、勉強への前向きさにつながります。
タイプ②:感覚が敏感な子
脳の状態:音・光・人混みに過敏で“防御モード”になりやすい
→「安心」を積み重ねることで、環境ストレスに強い切り替え脳が育ちます。
たとえば「今どんな感じがする?」と気持ちや感覚を言葉にしてもらうこと。
「うるさい」→「ちょっと静かな部屋で休もうか」など、感覚を調整する練習を家庭で重ねると、
安心できる環境を自分で作り出せるようになります。
タイプ③:集団が苦手な子
脳の状態:人との距離感や空気を読むのが難しく、集団に入ると疲れやすい
→安心できるやりとりを家庭で積み重ねることが大切です。
たとえば「お店屋さんごっこ」や「役割分担のあるお手伝い」。
「ママはお客さん、あなたは店員さん」と役割を交代しながら遊ぶと、相手の立場を考える練習になります。
「ありがとう!」と返すやりとりの中で、安心の社会性が育っていきます。

タイプ④:分離不安な子
脳の状態:ママと離れることに強い不安を感じる
→「見通し」と「安心ルーティン」で不安が和らぎます。
たとえば「今日は朝ごはんの後に洗濯物をたたもうね」と予定を伝えてから行動すること。
「できたね!次はどうする?」と声をかけると、自分で進められる安心体験が増えていきます。
「ママがいないと無理」から「自分でも大丈夫」へと、少しずつ移行できるんです。
タイプ⑤:賢すぎてつまらない子
脳の状態:理解が早すぎて、授業が退屈に感じる
→探究心や創造力を満たす体験が必要です。
たとえば「今日の夕飯に合う献立を考えてみて!」とお願いすると、調べる・組み合わせる・工夫する…脳がフル回転。
「そのアイデア面白いね!」と承認されると、「学ぶのって楽しい!」が未来への原動力になります。
タイプ⑥:完璧主義な子
脳の状態:失敗を“危険”と感じ、挑戦を避けやすい
→「失敗しても大丈夫」の体験を積むことがポイントです。
たとえば一緒に料理や掃除をして、少し失敗しても「こうすれば直せるね」と笑ってやり直す。
「やり直してできたね!」の声かけが、挑戦する勇気を育てます。
6タイプそれぞれに「おうちキャリア教育」でできる関わりがあります。
大切なのは、子どもの苦手を“ダメなこと”と捉えるのではなく、
「脳の発達の途中」と理解して、家庭で“できる体験”を積ませてあげること。
それが「学校しんどい」を変える、確かな第一歩です。