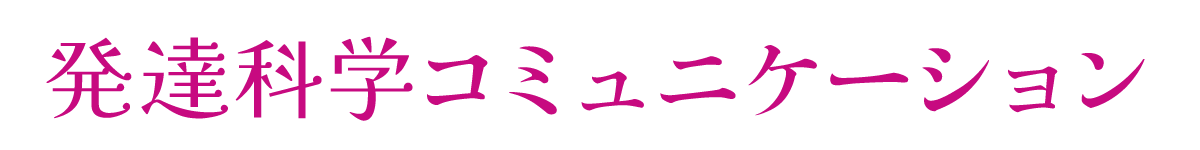先生の話を聞けずフラフラしていたADHDで集中力がない小学3年生の子どもが、体操教室で最後まで集中して参加できるようになった家庭での声かけや対応についてお伝えします。
頑張ってほしいのに集中力が続かない…ADHDの子どもの習い事のつまずき
子どもに習い事をさせているのに、ぼーっとして集中していない姿を見るとついイライラしてしまうこと、ありませんか?
他の子どもは先生の話をしっかり聞いて、次はここを注意してやってみようと頑張っているのに上の空
ほとんど話を聞いていないため、同じことを注意されるばかりでなかなか上達しない。
こんな調子で習い事を続けて意味があるの?毎回の送迎だって結構大変なのに…お金も時間もかけているのにこんな調子で無駄なことをしているのではないか?
そんな気持ちになってしまうこもあるのではないでしょうか。
ADHD(注意欠如・多動症)の小3の息子は5歳から体操教室に通っています。
本人は楽しいと言っているものの、小3になっても先生が説明している時にほとんど話を聞いていない様子が見られました。
・話をしている先生の方を見ていない、お手本を見ていない
・手足や体が常に動いてらふらしている
・ぼーっとして明らかに別のことを考えている
見学している私はイライラ。
「ちゃんと先生のお話を聞いて、お手本を見ていないと上手にならないよ」と言い聞かせていましたが、息子は「聞いてるよ!」と言い返すばかりでした。
「お友達がやっているところも見ていないから、次何をやったらいいかわからなくなっているよね」と伝えると「そんなこと無いよ!」とムッとして不機嫌になる始末。
このままでいいのかなと思いながら習い事に連れていく日々でした。
子どもに何かキラッとした才能が見つかるかも?!そんな期待を抱きながら習い事をさせているお母さんも多いのではないでしょうか。
イライラしてしまう気持ちも、子どもの将来を思うからこそですよね。
このあと、「なかなか集中子できない子ども」にお母さんが声かけをすると、る自信とやる気につながる簡単に実践できる工夫をご紹介していきますね。

集中力がないのはなぜ?ADHDの脳の特性
体操教室の先生の話はそれほど長くないし体操が嫌いではないのに、なぜ集中して聞けないのか? その理由は息子の脳の特性と環境要因にありました。
たとえば先生が「今日は跳び箱の踏切を練習するよ」と説明している間に、息子は隣で鉄棒にぶら下がっている友達が気になってキョロキョロ。
ようやく先生の声に耳を戻した時には「え?次なにするんだっけ?」と頭が真っ白になってしまう。こんなことが何度もありました。
ADHDの子どもは
・退屈でいることが苦痛であるため、自分の順番を待っている間に空想の世界に入ってしまう
・記憶を留めておくワーキングメモリが弱いため、聞いてすぐ理解し行動に移すのが難しい
・隣で鉄棒や跳び箱をする子が気になりキョロキョロしてしまう
・見学している保護者の視線が気になり落ち着かない
このようにもともと話を聞くことが苦手な上、周囲の環境や刺激で注意がそれやすいため、「ちゃんと聞きなさい」「ちゃんと見て」と叱っても効果がなかったのです。
本人も「集中できていない」とは気づいていないことが多いので、親のイライラと子どもの反発がぶつかってしまっていました。
ADHD小学生に効果があった3つの声かけ
息子のダメなところやできていないことを指摘するのではなく、できたことに注目する声かけに切り替えると息子に変化が起こり始めました。
◆子どもができていることを具体的に褒める
・「跳び箱の助走がカッコよかったよ!」「手がピンと伸びていたね」
子どもができていないことはスルーして、できていることを具体的に伝えることで、子ども自身も「僕 できているんだ」と前向きな気持ちになります。
◆視覚的に「褒めている」という合図を送る
・体操している時に息子がこちらを見たら「今のよかったよ」とグッドジョブサインを送る
見学している時に頑張っているところを「いつも見ているよ」というサインを送ることで、本人は頑張ろうという気持ちがアップします。
◆お母さんのポジティブな気持ちを伝える
・お母さん、かっこいい〇〇君の姿を見られて嬉しいな
大好きなお母さんが喜んでいるということを伝えるだけで、子どもはもっとお母さんを喜ばせたいと思うようになります。
具体的でポジティブなフィードバックを続けたことで、息子は「僕、跳び箱が得意かも」と自信を持ち始めました。
できたこと、良かったことを伝えたことで自信が芽生えると「もっと上手になりたい」という意欲が生まれます。
そして自ら先生の話を聞いて理解しようとする姿勢が見られるようになっていきました。
先生のお話を少しでも聞けたら、「先生のお話ちゃんと聞いていたね」と褒めることで
・お話を聞いたら褒められる
・先生のお話を聞いてチャレンジしたら跳び箱が上手になった
という本人の成功体験が積み重なっていきました。
話を聞く、集中力を高めるスイッチはお母さんの声かけにあるのです。
ADHDの子どもは不注意や聞き逃しがあることで、学校では注意されてしまうことが多いからこそ、お母さんが褒めることが、自信を育てるのです。

家庭でもできる集中スイッチの育て方
先生のお話を聞くことができるようになると
・先生の話を聞きながらポイントを覚えて実際にやってみる
・友達の動きを観察して真似る
息子の「聞く力」以外にも「見る力」順番通りに練習する「覚える力」がついてきたのです。
また、私が「あんなに高い跳び箱よく飛べるね、どうやって飛ぶの?」と聞くと「助走のスピードやロイター板のジャンプの位置が大事」と説明できるようになりました。
息子は先生の説明を理解して自分の中に落とし込み言語化することができるようになってきたのです。
できていない事を指摘するより、できている事を具体的に褒めていくことで、「自分はできる!」と思える自信と成功体験を積み重ねることが子どもの集中力だけでなく
そこに連動して「見る力」そして「行動する力」も伸びて子どもが成長するのです。
お母さんが子どものできていることを褒めるだけで、子どもがぐんと伸びていくので、できていることを褒めることから始めてくださいね。

執筆者:高田 みおり
(発達科学コミュニケーショントレーナー)