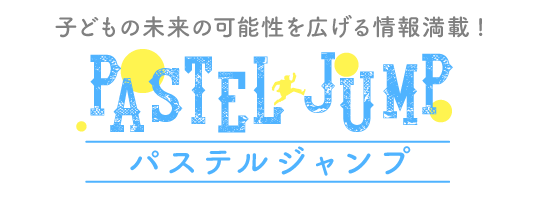1.隠れ不登校のサインを見逃さないで!
我が子が不登校になってしまうのではないか…と心配しているお母さんへ、今回は隠れ不登校さんの苦手をおウチで成長させて、学校でも「できるよ!」が増える方法についてお伝えします!
隠れ不登校さん、というのは、どんな子かというと…
学校には行っているけれど、
授業に集中できていない
友達との関わりが苦手で辛い想いを抱えている
集団が辛くて保健室で過ごしている…
こんな子ども達です。
毎日、朝、起きることが辛い
家ではため息ばかりついている
「学校行きたくないな」と言いながら登校している
おウチでこんな様子がみられたら、お子さんは隠れ不登校さんのリスクありです!決して、やる気がない、ダラダラしているわけではないということを理解してあげて欲しいです。

隠れ不登校の状態を見過ごしてしまうと、本格的な不登校に進んでしまう可能性があります。
だから、「不登校になったら困る!」といって、
ちゃんと毎日学校行かないと休みグセがつくよ!
しっかり勉強しないとますます授業についていけなくなるよ!
もっと友達と遊んでおいで!
と、子どもを激励しすぎるのはNG対応です。
苦手なことがあるのは、発達が凸凹しているから。
発達の凸凹は、脳の機能の問題です。やみくもに叱ったり指示を出したりするだけでは解消されません。
脳は、
聞いて→動く
聞いて→理解する
この繰り返しでネットワークが育っていきます。
科学的に根拠のある、子どもの脳が発達するのに効果的な声かけやサポートをご紹介しますね。
▼発達科学の視点で解き明かす。
不登校が続く不安を「成長のステップ」に変える、親子の対話術

メールアドレスの入力で無料でお届けします!
2.不登校になる前より発達が伸びて学校復帰できたのはなぜ?
我が家の息子は、現在大学1年生。
実は、元々は隠れ不登校さんでした。
不注意が強いことが学校の苦手さを感じる要因でした。
わが家の息子が
「集中できない」のは…
・興味のあることしかやりたくない
・注意がそれやすい
(友達との会話などにすぐ気がそれてしまう)
・ワーキングメモリが弱い
(一度に言われたことを受け止めて整理する力が弱い)
・不器用
(ノート書くのが苦手)
・感覚過敏
(音や声がたくさん聞こえる)
こんなさまざまな発達の特性が絡んでいました。
中学の授業参観に行った時私は衝撃をうけました。
授業を受ける息子の姿は…
No教科書
Noノート
Noふでばこ
先生の話は聞かずに、お友達とウフフアハハと好きな話をしているではないですか!
しかも席は一番後ろ。

特性が全開だったし環境も息子に合っていなかった。
一時期は楽しそうに学校に行っていた息子ですが、次第に学校に行きたがらない日が増えていき、不登校になりました。
脳科学的には、「わからない」状態をずっと繰り返している、つまりは頭を使わずに過ごしているのですから発達は次第にスローになっていきます。
息子は「学校に行く意味がわからない」とよく言っていました。
そんな息子ですが、不登校期間を経て学校復帰後どう変わったかというと…
・授業ききます
・提出物出します
・テスト取り組みます
(点数は別として)
・時間守って授業に参加します
こんなふうに急成長!
なぜ、こんな大変身をとげたのでしょうか?それも、学校に行かない間に成長したのです。
今、もし毎日学校に行けなくても
"大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
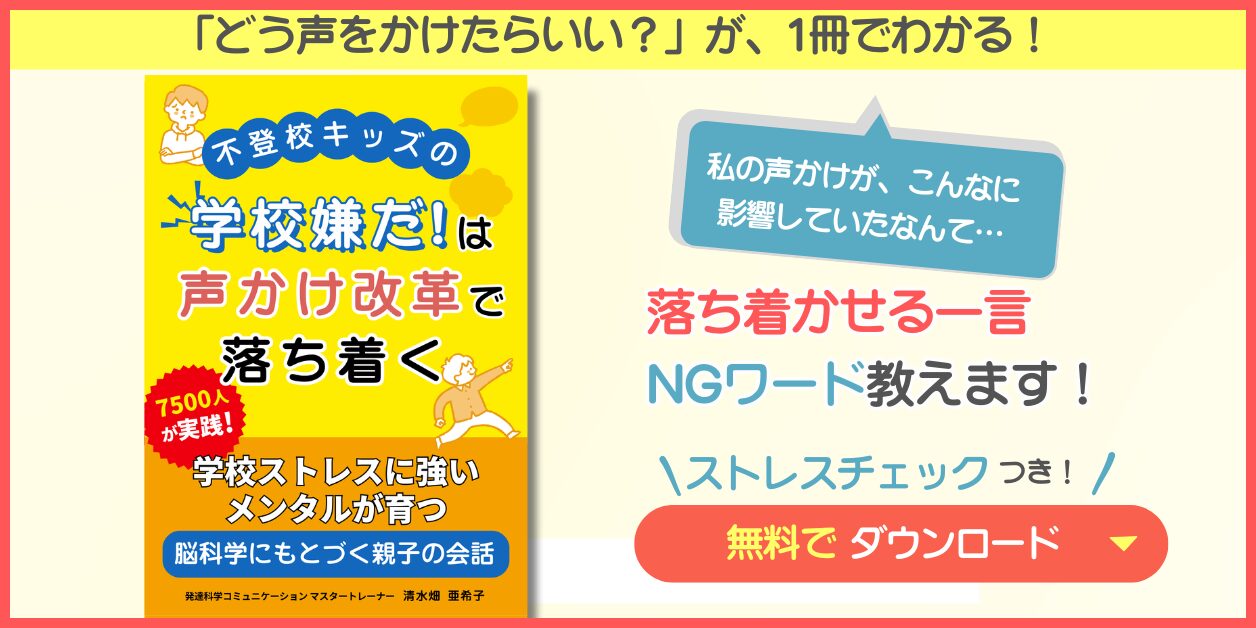
3.不注意タイプの隠れ不登校さんオススメ!おウチで聞く・集中するチカラを育てる方法
我が家の息子が、学校復帰後、学校での苦手さが解消されていた理由。
それは、不登校の間に「聞くチカラ」「集中するチカラ」を育ててあげたからです。
子どもの脳は、
「怒った言い方」
「長い話」
「難しすぎること」
はシャットアウトしてしまいます。
いくら大人の言い分が正しいとしても、このやりとりを繰り返していると脳は育ちません。
だから、会話をとことん、
ポジティブに
コンパクトに
簡単に
していきました。
例えば、不登校のお子さんであるあるなのが、「お風呂に入らない」問題。
「早くお風呂入りなさい!いい加減ゲームやめて!」
と、お母さんの怒りをヒートアップさせても子どもの耳には届きません。
・「お風呂何時から入る?」(笑顔で)
・「そろそろお風呂の時間だよ〜。」
・「お風呂に入るのと、歯磨きとどっち先にする?」
・「お風呂上がったら美味しいジュース用意しておくよ!」
こんな風に、選択肢を与えたり、ご褒美を用意してあげることが子どもの聞くチカを伸ばすコツ!
我が家では、お風呂以外でも、生活の色々なところで、不登校の間に脳を育てる会話をしたから学校に戻っていって集団の中でも「聞く」ことができるようになったんです。
「ちゃんと聞きなさい」と百万回言ってもそれだけでは聞く力は育ちません。
そして、もう1つ。
集中力を育てることにも工夫が必要です。
勉強に集中して取り組めない子に勉強を通じて集中力を育ててあげようとしてもそれはうまくいきません。
苦手な勉強でいやいややっているから「集中できた」という体験を積めないのです。
だったら、勉強以外のことで「集中する」体験を増やしてあげることが先決。
運動が好きな子なら一緒にバドミントンや卓球やキャッチボール。
モノづくりが好きな子なら、好きなものを一緒に作る
そんな時間を作って、
「たくさん夢中になってできたね!」
「こんなに長い時間集中できたんだね!」
「楽しくてあっという間の時間だったね!」
と、集中できたことをポジティブにお母さんが言語化してあげます。

そして、勉強以外で集中力が伸びてきたら、少しずつハードルの高い勉強や、お手伝い、など集中チャレンジの場面を増やしていきます。
これを続けたからこそ、我が家では勉強の集中力が10分しかなかった子が高校受験の時には4時間、5時間、と集中して勉強ができる子になっていったのです。
今回はADHDタイプの学校で集中できない!問題をどうやってお家で落ち着かせていったの?についてお話しました。
学校生活のつまずきは、学校での対応ではなく、おウチでのサポートで解消してあげられます!
冬休み、おウチで親子一緒に過ごす時間が長いタイミングはチャンスです!
3学期、4月からの新学期に向けて、お子さんの注意力を伸ばしてあげませんか?
隠れ不登校の子が、学校を楽しめるようになりますよ!
執筆者:清水畑 亜希子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
子どもの注意・集中力を引き出すアプローチの方法、学べます!