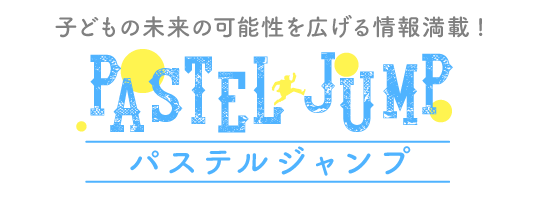1.お腹が痛くて朝起きられない思春期の子どもの体におきていること
朝になると「お腹が痛い…」と言って起きて来られない
早起きしてほしいのに前日の夜はゲーム三昧
学校に登校する時間が迫ってもなかなか起きられないお子さんに、イライラしてしまうことはありませんか?
思春期の子どもたちが朝起きれなかったりお腹が痛くなったりするのは、複数の原因がからんでいます。
特にママ達に知っておいてほしいのは、思春期特有の自律神経の乱れと子どもの脳の特性です。
まず、思春期特有の自律神経について。
小学生までとは違い、中学生や高校生(思春期)は、大人の体への体へむけてホルモンバランスが変化して自律神経の乱れを引き起こします。
自律神経の乱れによって夜なかなか眠れなくなってしまうということが起こってしまいやすいのです。
また、小さな頃から睡眠導入や覚醒リズム自体に課題があって、寝ることや起きることに時間がかかることも多いケースもあります 。
夜寝るのが遅いからといって、「遊んでばかりいるから寝られないんでしょ!」という思い込みがあったら、ちょっと注意が必要です。
次に、脳の特性について。
不安が強い傾向になる子は、楽しかった記憶よりも嫌だった辛かった記憶を強く覚えているという傾向を持っています。
学校で苦手なこと
学校でやってしまった失敗体験
勉強のことや友達関係への不安
これらの不安が強く心の中にわだかまってしまうと、体にも影響し、朝になると腹痛を訴えたり、体が重くて起きられない…という不調が起きやすいのです。

不安があるから前の日の夜、次の日の学校の不安をゲームで紛らわせていたり、ゲームに集中しすぎて 明日のことを考えて見通しを立てた行動ができなかったり…ということが起こります。
ブルーライトなど強い光を浴びると、睡眠を促すメラトニンというホルモンが出にくくなり、体内時計のリズムが後ろにズレてなかなか眠れなくなる…という悪循環が起こります。
そんな子どもを一生懸命起こそうと思って、お母さんがイライラした様子で大きな声で起こすと、さらに朝が嫌な記憶として残ってしまいます。
▼発達科学の視点で解き明かす。
不登校が続く不安を「成長のステップ」に変える、親子の対話術

メールアドレスの入力で無料でお届けします!
2.学校の日はなかなか起きられない息子を叱らずに起きれるようにしてあげたい!
我が家にはちょっと発達に凸凹がある現在高校二年生の息子がいます。
中学生から、朝になると腹痛を訴えて、遅刻や欠席が増えてきました。
原因としては中学校生活で
「朝、早起きをしなければならない」
「見通しを立てて行動しなければならない」
「興味がなくてもやらなければならない」
「大量にある課題の提出がつらい」
などいくつもの苦手を抱えたことによるストレスが考えられました。
息子は、好きなことをして過ごすことができる長期休みには、腹痛を訴えることはなく、体調は良いのです。
しかし新学期になると一気にストレスがかかり、腹痛を訴えて、遅刻や欠席が続くことが悩みでした。
高校生になっても状況は変わりませんでした。
様子を見ていると、学校がある日は早起きが苦手な息子ですが、自分の予定(楽しみ)があると早起きして元気に出かけて行くのです。

私は
『息子は、朝起きられないのではなく、学校のある日には早起きをして登校したい!という気持ちになれていないからなんだ。』
と気づきました。
苦手のうちの一つ『早起き』に着目して、高校二年生になる春休み、生活リズムを大きく崩さずに過ごして、新学期にかかる体のストレスが少なくてすむようにサポートをしてあげたいと思いました。
でも、起きる必要性を感じていない息子には、夜には「早く寝ないと、朝起きれないよ」と何度言ってもどう伝えても長期休みの生活リズムを整える大切さが伝わらず…
朝には大きな声で「起きなさい!」とイライラ。
きっと息子も怒られたら朝に嫌なイメージがついてしまっているだろうな…と自分自身にもどかしい思いを抱えていました。
だから、思春期で発達特性の出ている息子のことを怒らずに、「早く起きよう!」と思ってもらえるもらえる作戦を考えよう!と思いました。次に我が家の実践例をお伝えします。
▼発達科学の視点で解き明かす。
不登校が続く不安を「成長のステップ」に変える、親子の対話術

メールアドレスの入力で無料でお届けします!
3.楽しいことを朝に用意しておくことで起きられればハナマル!と思おう!
楽しみのために早起きできるのは、大人も子どもも一緒ですね。
楽しみなことのために早起きできるのであれば、朝早くに楽しみを作ればいいのです!
ここでは、大人の常識の範囲で考えずに、「子どもの好き!楽しい!」を否定しないことがコツです。
息子にとっての楽しみ、それは、ネットワークに繋いでゲームをすることでした。
そこで我が家では、ネットワークが使える時間を朝6時から夜22時までに変えることにしたのです。それまでは、ゲームは学校から帰宅する15時から22時までと厳しく言っていました。
・学校を休んだ日にゲームをして楽しく過ごして欲しくない
・せっかくの休日に朝からゲームをする息子の姿を見たくない
・ゲームを優先して日中に家族と外出しなくなるのでは
という理由からでした。
けれど、朝の早起きをサポートするためにゲームを活用することにしたんです!
大人の常識の範囲で考えずに、「子どもの好き」を否定しないことがコツです。
起きてすぐにゲーム、パジャマのままゲーム、ご飯を食べなくてゲームをしても、まずは起きてきたことを肯定しました。
「いつもより早く起きたね」
「春休みも早起きだね」
「今日は、起きてくる足音が元気だね」
ゲームのきりがつきそうなタイミングで、朝食に誘い「一緒にご飯たべられて嬉しい」など、嬉しい感情も伝えていきます。

できるだけ笑顔で雰囲気良く、を心がけました。
息子にとって「朝早く起きると楽しいことができて、お母さんも優しいな」という良い記憶になるようにしていきました。
今、もし毎日学校に行けなくても
"大丈夫です!"
毎日の声かけを変えて
子どもの脳を育ててストレスをリセット!
▼今読めば進級進学前に間に合う!▼
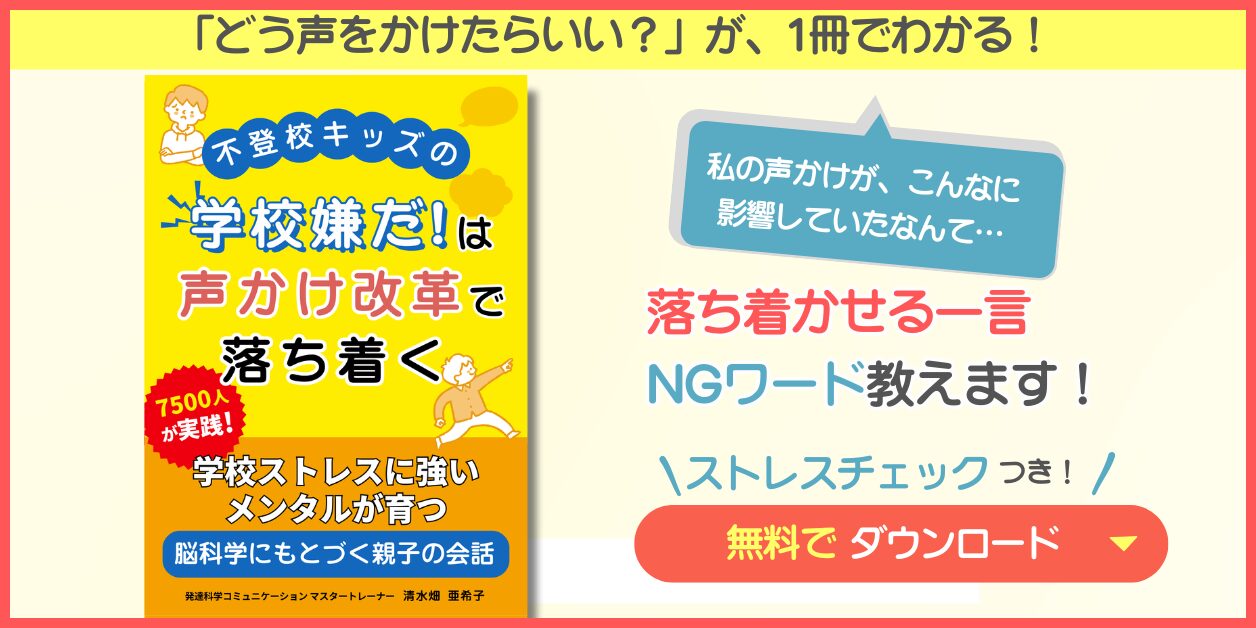
4.学校のない長期休みでも寝すぎることなく早起きできるようになった!
サポートを続けていくと、大声でいくら起こしても起きなかった息子が毎朝6時に起きてくるようになりました。
朝にお腹が痛いと言うことも少なくなっていきました。
「起きれたね」と行動に注目して肯定の言葉をかけることで、早起きすることがいい記憶として息子の中に残り、嫌な記憶だった「起きること」が良い記憶に上書きされたのです。
私は、なぜ、早起きが続けられているのかな?と思って「どうやって、早起きしているの?」と聞いてみました。
すると、息子は「起きれるように23時ごろには寝てる」と言ったのです。
この答えを聞いて、ハッと気づかされました。
起きたい気持ちがあれば、どうやって早起きするかを子ども自身が考え始めます。
大人が無理やり子どもの行動を変えようとするのではなく、子どもが安心して過ごせる、楽しい空間をおウチで作ってあげることで、子どもは自分で考えて行動することができるようになるんですね。
子育てでは、よく「どうしたらいいの?」と壁にあたることがありますが、その答えはいつも子どもの中にあったのです。


いかがでしたか?
お母さんが子どもがワクワクすること、楽しいと思うことを見つけて、子どもの力を伸ばしてあげたいですね。

執筆者:佐藤かおり
(発達科学コミニュケーションリサーチャー)
【子どもの力を信じるママになれる!】
▼子どもの発達を学んで、学校が苦手な子どもの力を引き出すサポート方法があります!