疲れると癇癪を起こす子どもに困っているママ
発達でこぼこのお子さんが「疲れると癇癪を起こす」「疲れると癇癪が起きやすくなる」というお話はママからよく聞きます。
幼稚園や保育園、学校がから帰ってくると、
些細なことで泣き叫ぶ、泣きだしたら止まらない、ひっくり返って大泣きする。
テーブルをひっくり返す、おもちゃを投げて襖に穴を開ける…。

このような癇癪に困っているママさんはいませんか?
発達でこぼこのお子さんが疲れると癇癪が起きやすいのは事実です。
皆さんはお子さんが疲れてきたかどうかを見極める時に、どんなポイントをチェックしますか?
一番わかりやすいのは、体の疲れですね。
お出かけしてたくさん歩いた、スイミングに行った帰り、遠足の後、
などなど、たくさん体力を使う活動をした際は、癇癪が起きそうだな〜と予想がしやすいはずです。
しかし、実は見落としがちなのは『脳の疲れ』なんです。
脳に負荷がかかる活動をたくさんやった時にも同じように癇癪が起きやすくなります。
・手先が不器用なお子さんが園で工作の活動をしてきた。
・給食のメニューが嫌いなメニューだった。
・新しい環境が苦手なのに、席替えがあった 。
・感覚の過敏性があり、園や学校の人の体臭や声、動きなどの刺激が強い。
・みんなと遊びたいのに声のかけ方がわからなかった。
・先生に複数の指示されて混乱した。
などなどです。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

疲れると癇癪を起こす「脳の疲れ」の正体
疲れると癇癪を起こすお子さんのママが意識してほしいのは
「体の疲れ」だけではなく、「脳の疲れ」です!
脳は、重さとしては体重のおおよそ2%ほどのほんの小さな臓器なのですが、 静かにしていてもエネルギー消費量は体全体の消費量の約20%も占めていて、 非常にエネルギーを使う臓器なんです。
ですから、実は気がつかないうちに脳にはとてもとても大きな負荷がかかっています。
加えて、発達でこぼこのお子さんは、普段の園での生活や学校生活において、他のお子さんと比べて倍以上も脳に負荷がかかっていることが多いのです。
皆さんも運動したわけではないのに、テスト勉強したらものすごく疲れた、という経験をされたことがあると思います。
大人なら、体が疲れた、なんか頭がパンパン!などと感じると、
一旦やめて休憩しよう!少しゆっくりしよう!となります。
しかし、お子さんはそもそも自分が疲れていると感じること(いわゆる内省と言います) がまだ得意でありません。
ですから、 疲れているのに、嫌なのに「やりたくない!」と言えないときなどに癇癪が起こりやすくなります。
この反応は脳の反応なので、子どもが自分で抑える事が難しいです。
癇癪が起こった際には、背景に「脳に負荷がかかっている」という状況です。
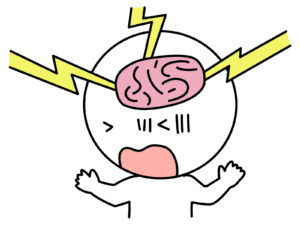
ですから、シンプルに「脳の負荷をなくす方法や声かけ」さえわかればいいんです!
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

疲れると癇癪を起こす子どもへエネルギーを取り戻すおうち対応
発達でこぼこのお子さんは、普段の園での生活や学校生活において、他のお子さんと比べて 倍以上も脳を酷使して、ひどく疲れています。
「脳の負荷をなくす方法や声かけ」とはどのようなものでしょうか?
1.家では思いっきり好きなことに没頭させる
おうちでは思いっきり好きなことをさせてあげましょう!
その時間は「していると安心できること」に没頭したいときです。
脳の疲労を回復し、気持ちを切り替える上で大切な時間です。
そんな時に近づいてくる人は、「迷惑な侵入者」「邪魔者」でしかありません。
邪魔がささやかであれば無視して自分の時間を守りますが、無視しきれなくなると、癇癪を起こします。
何かに没頭している時には、「今は声をかけないでおこう」とそっと見守りましょう。

お夕食の時間などで、どうしても終わりにしてほしいと話しかけるときには、
できるだけ切りのいいところまで待ってから話しかけましょう。
決して「今すぐやめて!」といきなり指示・命令をしてはいけません。
もしも、絵を描いたり、工作などをしていたら、
目を合わせて、微笑み、穏やかな声で
「楽しそうだね。何を書いたのかな?」など楽しく会話をスタートします。
そして、 「そろそろ、お夕飯だよ。」 「〇時までにしようか」
時間がわからないお子さんの場合は「長い針が〇までにしようか」 と期限を伝えるようにします。
時間がきても片付けられないときは、少しだけ時間を延長します。
自分で切り替えられるように2回はチャンスを与えましょう。
2回はチャンスをあげて、3回目は片付けを手伝いましょう。
2.子どもの話を笑顔で聞く
お子さんがお話しているときは、「笑顔で聞く」ことを徹底しましょう。
「そうだったんだね、うれしいね!」「そうか、楽しかったね」と肯定的な相槌を打ちながら聞きましょう。
3.確認や質問は「1回に一つ」
もしも、お子さんの話を聞いていて、
お母さんが確認や質問したいことがあるときは「1回に一つ」を心がけます。
子どもが疲れているときは、集中力が低下し、「考えて、思い出して、答える」の切り替えが難しくなっているためです。
疲れると癇癪を起こすお子さんをお持ちのママさん、
家では思いっきり好きなことに没頭させる
子どもの話を笑顔で聞く
確認や質問は「1回に一つ」
を実践してみませんか?

脳の疲れがとれ、明日の園や学校で過ごすエネルギーを取り戻すことができますよ。
執筆者:桜井ともこ
(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)


脳を育てて伸ばしていく子育てを一緒に体験しましょう!
▼無料メール講座の登録はこちらから



