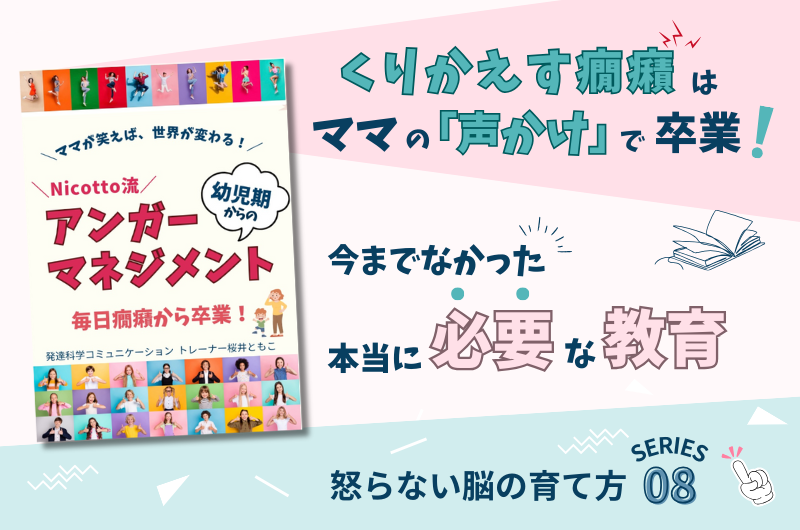支援級予定の娘と普通級であろう息子。息子に聞かれたら何と答える?
お子さんが支援級に通っているママ、これからお子さんが入級されるというママ、日々の対応お疲れ様です。
兄弟姉妹がいる子の場合、その兄弟姉妹から、
「何で◯◯くん(ちゃん)は支援級に行っているの?」
と質問されて、説明に困ったご経験はありませんか?

4月から年長になった私の娘は、年少の終わりに自閉症スペクトラム(ASD)と診断されています。
知的障害の診断はありませんが、新版K式の検査結果(年少秋時点)だと、「平均下位〜ボーダー」だったので、「発達ゆっくり」といったところです。
就学相談はこれから始まりますが、親としては支援級(自閉症情緒障害)を第一希望としています。
一方新年少の息子(弟)は、繊細な部分はありますが、集団活動にもついていけるし、今のところ発達ゆっくりではなさそうです。
今後3年間園の先生のご指摘が何もなければ、普通級になるであろうと思われます。
私は3年後、息子が小1になったとき、
「何でお姉ちゃんは支援級なの?」
と質問されたらどう説明しようか、悩んでいました。
シリーズ累計1万ダウンロード突破!
今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」
24時間イライラしない習慣術
↓↓↓

学校での実態…そもそも兄弟やママの脳も凸凹がある!?
発達障害への世間の理解は、昔と比べると格段に良くなってきています。
だけど未だに学校では、普通級のお子さんにとってみたら、支援級って何をしているのかわからない、遠い存在になっている実態もあるそうです。

ここで少し、脳の仕組みを見てみたいと思います。
脳は、大きく分けると8エリアに分かれます。
運動、視覚、聴覚、記憶、感情、伝達、思考、理解です。
その8エリアをさらに細かく分解すると、120の場所に分かれて仕事を分担しています。
120の場所の働きの組み合わせ系列を数えていくと、京単位になります。
つまり、全く同じ脳を持った人はいない。
発達障害の有無にかかわらず、世の中に「全く同じ」人は1人としていないのです。
一口に「発達障害」と言っても、特性の出方は十人十色であるのはこれが所以です。
発達障害があろうとなかろうと、苦手なことは誰にでもあるし、得意なことと苦手なことの差(凸凹)が全くない人はいないのです。
もちろんパパもママも兄弟姉妹もです。
毎日癇癪から卒業!
本当に必要な新しい教育がわかります
↓↓↓

親御さんのわかりやすい説明で、兄弟が多様性を学べるチャンスに!
悲しいことですが、大人でも多様性を受け入れるのが難しい人や、発達凸凹やLGBTQなどマイノリティの方々を下に見ている人は少なからずいます。
お子さんには、多様性を尊重できる大人になってほしいですよね。

そのために、子どものうちから兄弟姉妹に支援級に通う子がいるというのは、貴重な経験です。
せっかく兄弟姉妹が疑問を持ってくれたなら、多様性について伝えるチャンスです!
聞いてくれたタイミングで上手く説明できるように、事前準備をしておきましょう。
家族の得意苦手の話、支援級のメリットを話しながら説明しよう!
兄弟姉妹に説明するためのポイントとしては、
・苦手なことやできないことは誰にでもあること。
・だけど支援級に通っている子は、その「苦手なこと」が他の子より多かったり、「苦手」の度合いがお友達より大きかったりすること。
・支援級に通う子が少人数の安心した環境で、得意なことをさらに伸ばしながら、苦手なことも少しずつ克服していけるように、支援級と言う場所がある。
という3点です。

もちろん兄弟姉妹の年齢や発達段階、理解度に応じて、言葉を噛み砕く必要はあります。
「兄弟姉妹(パパ、ママ)は何が得意(苦手)か?」と家族みんなの得手不得手について話し合うなど、具体例を挙げながら説明するとより腑に落ちやすいかと思います。
どのように説明するか、パパともよく話し合っておくとより安心ですね。
普通級の子ども達にとっても支援級が、もっと身近なものになることを願っています。
執筆者:たちばな あずさ
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)


ママが安心して子育てできるようになるためのヒントが見つかります!
▼無料メール講座の登録はこちらから