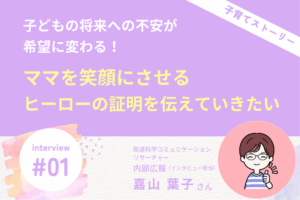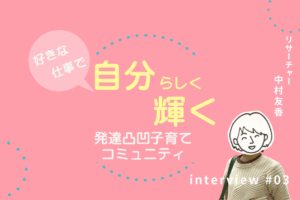いつも不機嫌な旦那さんに振り回されて疲れているママ。家族で笑い合う未来を諦めていませんか?イライラの裏にはアスペルガーの特徴が隠れているのかも。気を遣うだけの日々から抜け出すことはできます!
【目次】
1.旦那がすぐにイライラするのはなぜ?ママが疲れる理由
2.旦那の不機嫌の背景にあるアスペルガーの特徴
3.ママの性格の問題ではない—カサンドラ症候群とは
4.夫の不機嫌に振り回されない!10年後もっと幸せになる3ステップ
1.旦那がすぐにイライラするのはなぜ?ママが疲れる理由
夫の不機嫌に振り回されて、ずっと気を張りつめてきたママ。
まず最初に知ってほしいのは「夫の不機嫌は、あなたのせいではない」ということ。
毎日を振り返ると、こんな場面が思い当たりませんか?
・お出かけの準備でバタバタすると、夫が急にイライラ
・車の中で子どもの声が少し大きいだけで雰囲気がピリつく
・人混みに出た瞬間、夫の機嫌が落ちていくのがわかる
・帰り道は夫の疲れと不機嫌に気を遣いっぱなし

子どもには楽しい経験をたくさんさせてあげたい。
けれども、夫の機嫌が悪くなるのも避けたい。
だから「私が気をつければ大丈夫」と、ずっと自分に言い聞かせてきたのではないでしょうか。
けれど、その“気遣いの積み重ね”は、ママの心を静かにすり減らしていきます。
気づけば、家の中の空気を読んでばかり。
子どもまで遠慮がちになっていくこともあります。
このままでは、ママ自身が限界を迎えてしまうかもしれません。
次章では、ママが自分を責めてしまいやすい理由をお伝えします。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
3週間で癇癪が落ち着き
毎日が穏やかに過ごせるようになる!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.旦那の不機嫌の背景にあるアスペルガーの特徴
夫がすぐに不機嫌になる理由には、アスペルガーの特性が関係していることが多いのです。
旦那さんが不機嫌になりやすい3つの特徴をお伝えします。
◆感覚過敏 —「音・光・人混み」が負担になりやすい
アスペルガーの人は、五感がとても敏感な場合があります。例えば、お出かけ中に…
・車内での子どもの声
・人混みのざわつき
・予想外の音や匂い
こうした刺激が、本人には“ストレス”として感じられてしまいます。
そのため、周囲から見ると「急に機嫌が悪くなった」ように見えるのです。
言い換えれば、人一倍繊細なセンサーを持っているということ。
だからこそ、子どものちょっとした体調の変化にすぐ気づけるなど、良い面にもつながります。
◆ルーティンの崩れが大きな負担になる
予定変更やイレギュラーが苦手なのも特徴のひとつ。
・思っていた段取りと違う
・出かける直前で準備がバタつく
・到着時間がズレる
こうした“いつもと違う流れ”が起こると、不安や戸惑いが一気に高まり、その結果としてイライラが表に出てしまいます。
これは裏を返すと、一度覚えた家事や決まった役割は安定して続けられるという強みでもあります。
皿洗い・ゴミ出し・洗濯など、型が決まった作業は得意になりやすいのです。
◆自分の時間が奪われると強いストレスに
アスペルガーの特性として、好きなこと・興味のあることに深く集中する力があります。
そのため、
・子どもに呼ばれる
・家族時間で自分の予定が中断される
・自分だけの時間が取れない
こうした状況では、気持ちがうまく切り替えられずイライラの原因になりやすいのです。
裏を返せば、好きなことへの集中力が高く、探究心が強いという力にもなります。
細かい調べもの、電車の時間の管理、段取りを細かく考えるなどは得意なことが多いでしょう。
「アスペルガー=困った特性」ではなく、困りごとの裏側には必ず“力”が隠れています。
夫の不機嫌も実は、特性が生活の中でうまく活かしきれていないだけなのです。
ただし、夫の特性を理解しただけでは、ママの心がラクになるとは限りません。
次項では、ママ自身がしんどくなってしまう「カサンドラ症候群」についてお伝えします。
3.ママの性格の問題ではない—カサンドラ症候群とは
夫の不機嫌にいつも気をつかい、機嫌を予測して動いてしまう…。
そんな状態が続くと、ママの心は慢性的に疲れ切ってしまいます。
これは決して「性格が弱いから」起きるのではなく、カサンドラ症候群という状態。
パートナーの特性ゆえにコミュニケーションが噛み合わない環境に置かれ続けることで起きる心の疲労です。
「どう伝えてもわかってもらえない」「怒らせないように先回りしてしまう」
その積み重ねが、ママの自信や安心感を奪ってしまうのです。

ママ自身がつらくなるだけでなく、この状態が続くと子どもの心にも影響が出てきます。
・家の空気がピリピリして情緒が不安定に
・ママが否定される姿を見て自己肯定感が下がる
・「人間関係は我慢するもの」と誤って学んでしまう
家庭の安心感は、子どもの心の土台です。
ママが限界まで我慢し続けることは、決して「家族のため」にはなりません。
それどころか10年後、夫との2人生活が心配なママも多いですよね。
次項では、夫の不機嫌に振り回されない妻の新習慣をご紹介します。
情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!
”脳のクセ”を育て直す声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.夫の不機嫌に振り回されない!10年後もっと幸せになる3ステップ
夫の不機嫌に振り回されてヘトヘト…。
まず一番大切なのは、夫ではなく“自分の気持ち”を知ることです。
そのためのシンプルで効果的な方法が ジャーナリング(書く習慣)です。
研究でも「書くこと」はストレス整理に役立つことが示されています。
◆ステップ1:気持ちを書き出す
夫へのイライラ、悲しかったこと、納得いかなかったこと——
思いつくままノートへ。
書くことで、自分の感情を客観的に見られるようになります。
◆ステップ2:本当の願いを見つける
書き出したことをよく読むと、「○○すべき」「○○しなきゃいけない」という思い込みが混じっていることに気づくかもしれません。
そこで自分に問いかけます。
「本当はどうしたい?」
思い込みが薄れ、本音が浮かび上がります。
◆ステップ3:小さな行動から始める
気持ちが整理できたら、ほんの少し家庭の行動を変えてみましょう。
例えば、
・あいさつを必ずする
・毎日1回質問をしたり、話をする時間をあえて持つ
・夫の特性に合いそうな家事や育児を少しまかせてみる
・家族で出かける時は、夫の希望も確認し、段取りを組んでもらうなど
「全部変える」必要はありません。
“小さく任せる”“少し話す” の積み重ねで、家族の空気は確実に変わっていきます。
私自身、夫とは会話なんて無理…と思っていました。
ですが、書き続けていくうちに“本当は仲良く過ごしたいんだ”という気持ちに気づいたんです。
そこから少しずつ行動を変えたら、今では家族で過ごす時間が以前よりずっと穏やかになりました。

10年後、夫婦ふたりの生活を想像できますか?
不安になったママ!諦める前にできることがあります。
夫が変わるのを待つのではなく、自分の世界を少し広げてみること。
自分を助けるための知識や、没頭できる趣味を手に入れてくださいね。
家庭以外の楽しみや「私だけの時間」が増えると、心の余裕も戻ってきますよ。
▼▼家族みんなが安心して過ごせるおうちを作りたい方!こちらの記事もおすすめです。
▼▼子育てで悩んだママたちが変わり、経験を発信しています!
家族の困りごとを解決するヒントがわかります!
不登校小学生の子どもの親によくある質問(FAQ)
Q1:アスペルガーの特徴は?
A1.会話は表面上問題なくできますが、本心を読むことが苦手で、字義どおりの意味で解釈する傾向があります。 そのため、冗談や皮肉が理解できず、相手の真意を勘違いしやすい傾向があります。
Q2:夫の不機嫌を見て育つことで、子どもに悪影響はありますか?
A2.家庭の雰囲気が常にピリピリしていると、子どもは敏感に感じ取り、不安や緊張を抱えやすくなります。ママが「心の安全基地」になれるだけで、子どもの情緒は安定しやすくなります。
Q3:カサンドラ症候群は、よくなることはありますか?
A3.はい、よくなる可能性は十分あります。 カサンドラ症候群は「あなたの性格が弱いから」ではなく、理解されにくい環境で長く頑張りすぎたことによる心の疲れです。安心できる環境を取り戻すことが、回復の一番の近道です。
執筆者:林 花寿美
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)