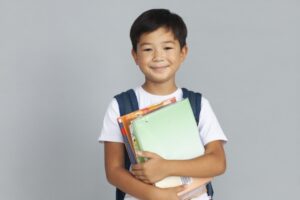登校班で行かない子はわがまま?無理に行かせていませんか。実はその対応、行き渋りを悪化させることも。登校班ストレスの正体と、子どもが自分から行ける力を育てる親の関わり方を体験談から解説します。
【目次】
1.登校班で行かない子はわがまま?行かせるべき?
2.登校班で行けない子が感じる3つのストレス
①人間関係のストレス
②身体・感覚のストレス
③朝の切り替えのストレス
3.登校班って絶対行かなきゃいけない?本当に大切にしたいこと
4.登校班で行かない子が行けるようになった!ストレスが減る3つの関わり方
①「登校班で行きたくない」もOK!「楽しく通う」を優先しよう
②帰宅後は“好きなこと時間”で心を満たす
③「できたね」を言葉で伝えて、自信を育てる
1.登校班で行かない子はわがまま?行かせるべき?
登校班の集合時間が近づくたび、朝から家の中はピリピリ。
子どもが「登校班で行かない」と言いだすと、つい「行きなさい!」と言ってしまいますよね。
実は、登校班で行かない・行けない子を無理矢理行かせるのは逆効果なんです。
私自身、長女の朝のしたくが進まず、「早く!遅れるよ」と声をかけては毎朝ギリギリ。
「登校班で行かない」と言う娘に、「学校の決まりなの!行きなさい!」と無理に送り出していました。
当時の私の中に「登校班で行かない」という選択肢は1ミリもありませんでした。
学校の先生から、
「学校では元気に過ごしていますよ」
と言われるたびに、「大丈夫、この対応で間違っていない」と自分に言い聞かせていました。
学校に行けていれば大丈夫だと思っていたのです。

ところが、無理に登校班で行かせ続けた結果、
・習い事にも行けない
・学童にも行けない
そしてついに、学校にも行けなくなってしまいました。
叱っても、励ましても、お願いしても動けなくなった娘を前に、私はどうしていいかわからなくなりました。
そんなときに出合ったのが発達科学コミュニケーション(発コミュ)でした。
無理に行かせることが、子どもの脳にとってどれほど負担の大きいことだったのか、ようやく気付くことができました。
その理由を、次でお伝えします。
繊細な子の「頑張りすぎ」を防いで元気に登校する方法がわかります▼▼
発達凸凹キッズの「学校行きたくない」はタイプ別で解決!無料プレゼント中▼▼
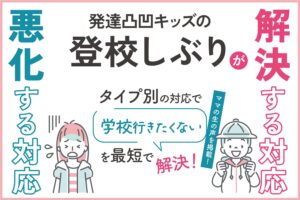
2.登校班で行けない子が感じる3つのストレス
登校班で行けない子が「行きたくない」と言うとき、その裏には“見えないストレス”が隠れています。 代表的なのは次の3つです。
◆①人間関係のストレス
小さい頃から周りの人の感情に敏感なところはありませんでしたか?
顔見知りでも「上の学年の子が怖い」「話しかけづらい」「冷たくされてる気がする」と感じることも。
繊細な子ほど相手の表情やトーンを敏感に読み取り、無言の圧にも強い緊張を感じます。
小さなストレスが積み重なると、「登校班=苦しい時間」と脳が記憶してしまうのです。

◆②身体・感覚のストレス
「みんなのスピードについていかなきゃ」と小走りで頑張るうちに、毎朝クタクタに。
さらに話し声や車の音、朝の光などの刺激が重なると、脳がオーバーヒート状態になります。
音や光・匂いなど感覚が敏感な子はとくにこうした刺激が、強い不快感として残り「理由はわからないけど行きたくない」という形で出やすくなります。
◆③朝の切り替えのストレス
朝の準備に時間がかかり「遅れる」「また怒られる」と焦りながら家を出る。
この焦りが脳の切り替え機能を妨げ、行動するエネルギーを奪ってしまいます。
「早く!」と急かされるたびに自信をなくし、登校班がプレッシャーの象徴になってしまうのです。
朝の支度がスムーズになる方法がわかります!▼▼
ストレスを感じやすい子は、前頭前野(感情のコントロールや切り替えをつかさどる部分)がまだ発達の途中。
不安がひとつ解消されても、また新しい刺激に反応してしまうことがあります。
だからこそストレスに強い脳を育てることが、根本的な解決につながりやすいのです。
ママから離れられない子の行き渋り対応をお伝えしています▼▼
休み明けの登校しぶりを改善したい方はこちら▼▼
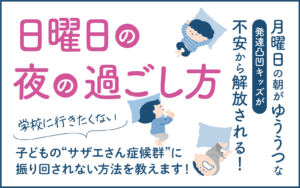
3.登校班って絶対行かなきゃいけない?本当に大切にしたいこと
「みんな登校班で行ってる」「学校の決まりだから」そう思って無理に行かせてしまった結果、私自身、後悔した経験があります。
“登校班で行くこと”にこだわりすぎて、子どものSOSを無視していたのです。
その後、次女が小1になり同じことを言ったときは、すぐに対応しました。
登校班で行けるようになるまで、しばらく別で登校することを班に伝え、安心して登校できるようにしました。
そして付き添い登校や車で登校を続けるうちに、少しずつ自信を取り戻し、小2では自分から登校班で行けるようになったのです。
「今日はここまでできたね」と小さな成功を積み重ねることで、脳は“やってみよう”という力(自己効力感)を育てていきます。
どうしてもできないときは、一旦できるところまで戻って自信を育てるのもひとつの方法です。
4.登校班で行かない子が行けるようになった!ストレスが減る3つの関わり方
登校班で行けない日があっても自分に自信があれば、子どもは少しずつ自分のペースで前に進めます。
ここでは、家庭でできるストレスを減らす3つの関わり方をご紹介します。
◆①「登校班で行きたくない」もOK!「楽しく通う」を優先しよう
登校班で行かない子=ダメな子、ではありません。
「行けた形」よりも「行こうとする気持ち」を大切にしてあげましょう。
付き添い登校や車での送迎も立派な登校。
どんな形でも登校時間=楽しい時間にすることを意識しましょう。
◆② 帰宅後は“好きなこと時間”で心を満たす
朝にエネルギーを使い切ってしまう子にとって、放課後の時間は「回復の時間」。
ゲームでも絵でもいいので、ひとつでも好きなことをする時間をつくりましょう。
帰宅後のストレスを極力減らし、寝る前に「楽しかったこと」を思い出すことで、翌朝の意欲にもつながります。
毎日の宿題ストレスを次の日に持ち越さない方法はこちら▼▼
◆③「できたね」を言葉で伝えて、自信を育てる
子どもが一歩踏み出せたときには、すかさず言葉で伝えるのがポイント。
「自分で着替えられたね」「がんばって玄関まで行けたね」と、できた行動を具体的にほめましょう。
普段から“できたこと”を積み重ねていくと、「自分はやればできる」という自信が育ち、やがて登校班にも自分から加わる力がついていきます。

登校班で行けるかどうかは、あくまで「通い方のひとつ」。
子どもの脳が育てば、今できないこともちゃんとできるようになります。
焦らず、比べず、子どもの「自信」を育てる関わりで「脳」を成長させましょう。
不安が強い子の脳を育てる対応がわかります▼▼
子どもが帰ってきたら最初にすることはコレ!登校しぶりを悪化させない方法▼▼
登校班の困りごとについてよくある質問(FAQ)
Q1:「登校班で行きたくない」と言われたら、どう対応すればいい?
A1:まず大切なのは、「甘えかも」「慣れの問題かも」と判断する前に、今の子どもにとって本当に負担になっていないかを見ることです。
低学年の繊細な子は、人間関係・歩く速さ・朝の緊張だけで、体も心もいっぱいになります。無理に背中を押すより、「どうしたら少し楽かな?」と安心を先に整えることが、結果的に自分から行ける力につながります。
低学年の繊細な子は、人間関係・歩く速さ・朝の緊張だけで、体も心もいっぱいになります。無理に背中を押すより、「どうしたら少し楽かな?」と安心を先に整えることが、結果的に自分から行ける力につながります。
Q2:登校班に間に合わず、周りに迷惑をかけてしまうのが心配です…
A2:そう感じるのは自然なことです。でも、間に合わないのは努力不足ではありません。朝の時間に強い不安やストレスを感じる子は、体がうまく動かなくなることがあります。
大切なのは、無理に合わせさせることではなく、
班長さんや学校にこれまでの感謝と子どもの状況を伝えたうえで、
-
しばらく個別で登校する
-
行ける日は登校班に参加する
-
時間になったら班は先に出発してもらう
など、子どもの状態に合った形を一緒に決めておくことです。
登校班は「守るための仕組み」であって、我慢を強いるルールではありません。
Q3:登校班で行かなくても大丈夫?学校や他の保護者の目が気になります…
A3:「登校班で行けているか」よりも、学校に対して前向きな気持ちを保てているかの方が、ずっと大切です。
一時的に付き添い登校や個別登校を選んだからといって、集団に戻れなくなるわけではありません。むしろ、無理を重ねて学校そのものが怖くなる方が、長い目で見ると回復に時間がかかります。
一時的に付き添い登校や個別登校を選んだからといって、集団に戻れなくなるわけではありません。むしろ、無理を重ねて学校そのものが怖くなる方が、長い目で見ると回復に時間がかかります。
子育ては楽しんだもんがち!子どもと楽しく成長したい方におすすめです!
執筆者:本田ひかり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)