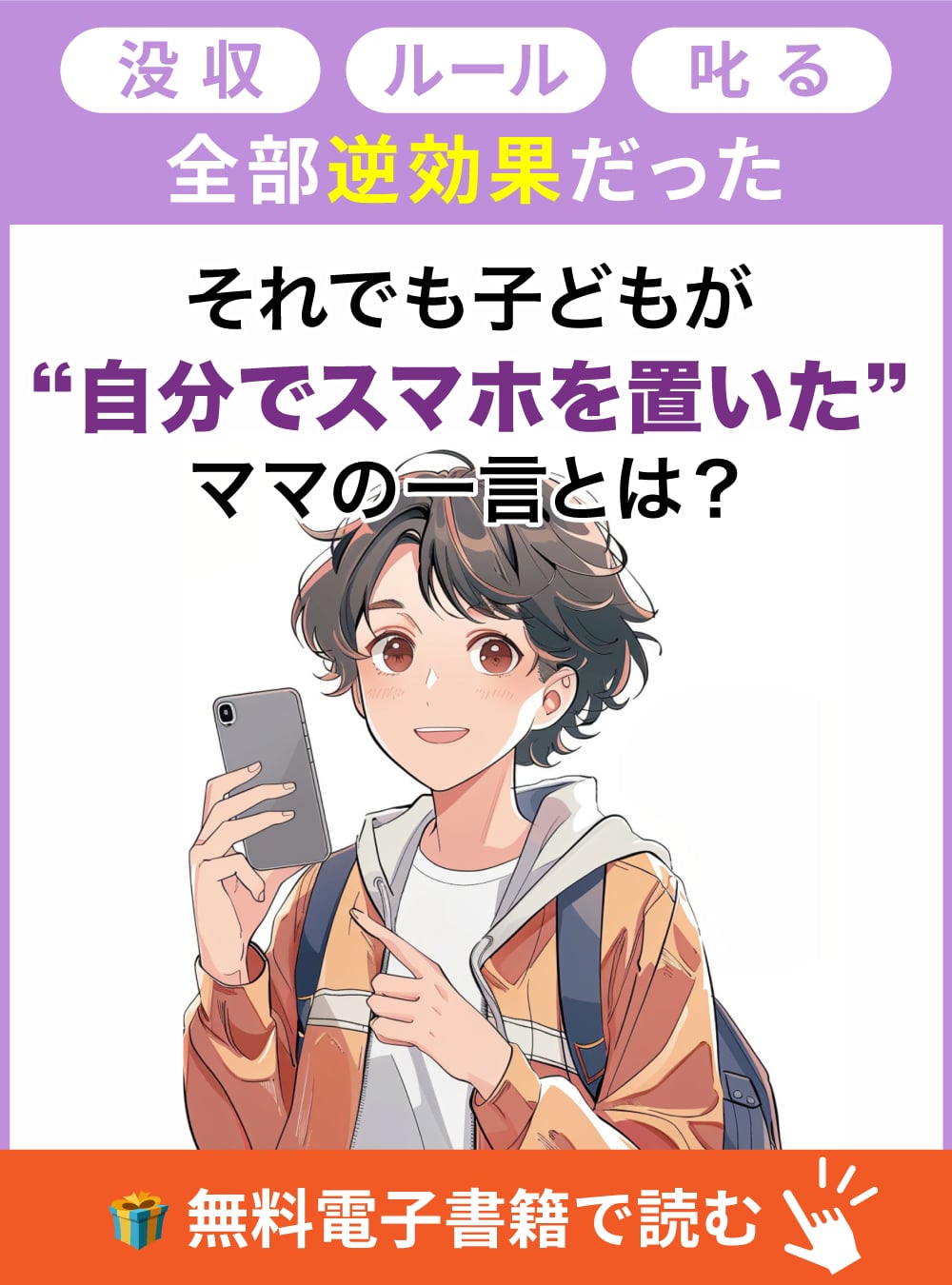4歳の酷い癇癪は毎日、外で頑張っている証拠。頑張ったストレスが限界を超えてあふれ出した状態です。そんな時こそ、癇癪がない時のママとの会話がカギ。ストレスの受け皿を広げる新習慣を試してみませんか?
【目次】
1.4歳児の酷い癇癪はストレス限界のサイン
2.癇癪対応はリラックスタイムがチャンス!
3.癇癪を予防する親子で取り組む新習慣
1.4歳児の酷い癇癪はストレス限界のサイン
「4歳の癇癪は成長の証」と言われても、癇癪が酷い状態が続くとつらいですよね。
そもそも子どもはなぜ癇癪を起こすのでしょうか?
実は、ストレスが溜まる受け皿が小さくて、ちょっとしたことで感情が溢れてしまうからなんです。
ママだって育児・家事・仕事、時間に追われて毎日いっぱいいっぱい。
ちょっとしたことでイライラ、爆発してしまうのは子どもの癇癪と同じ状態と言えます。
このストレスの受け皿を親子で大きくすることで、ニッコリ穏やかに過ごせるようになりますよ。

子ども達は毎日、幼稚園や保育園というお母さんに頼れない環境で、一人で頑張っています。
頑張った結果、ストレスを溜める受け皿が限界になって処理しきれない感情が溢れて癇癪になります。
この感情が爆発した状態の時は、コントロール機能が働かないので外からの刺激を受け取れません。
ですので、「叱る」「諭す」「他の行動に誘う」など癇癪に直接対応をしても意味がないんです。
火に油を注ぐだけで癇癪をもっと激しくしたり長引かせてしまいます。
癇癪は繰り返すと癖になり、火が付く導火線が短く、爆発も激しくなっていくので早めの対応が必要です。
外ではいい子なのに
家では癇癪に悩むママへ
家では癇癪に悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で
手が付けられない癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.癇癪対応はリラックスタイムがチャンス!
実は、癇癪が起きていない時こそ、ストレスの受け皿を大きくし、癇癪を予防するチャンスなんです。
親子で穏やかに過ごす時間を増やすためにも、外からの刺激や情報を冷静に受け取れる時がねらい目です。
お母さんの話を素直に聞ける、リラックスタイムを活用すると、安心感が得られやすくストレスの受け皿を大きくするのに最適です。

仕事から帰ったら、子どもを早く寝かせるためにご飯、片づけ、お風呂…。
子どもに構っている場合ではないのに
・ママ~と呼ばれたら対応
・癇癪が起きたら対応
というスタイルを続けていると、子どもに何かあったら対応し続けなければなりません。
いつまでたってもお母さんの時間はずっと奪われ続けることになってしまいます。
お母さんのストレスの限界値を上げるためにも癇癪予防は親子で取り組める方法がおすすめです。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.酷い癇癪を予防する親子で取り組む新習慣
ストレスの受け皿を大きくして癇癪を予防するために取り入れて欲しい新習慣をご紹介します。
その日1日のベスト3を報告し合う、今日のヒーロー&プリンセス自慢です。
子どもとリラックスした雰囲気で過ごせる、寝かしつけやお風呂の時間のルーティンとして取り入れるのがおすすめです。

やり方は簡単です。
リラックスタイムに「今日のベスト3を教えてね」と伝えて親子で言い合います。
・ひとりで靴が履けた!
・挨拶できた!
・虫を見つけた!
・ピッタリ金額で支払えた
・友達から連絡があった
・席を譲ってあげた
正解や不正解はないので、内容はなんでも構いません。
3つ以上あってもいいし、3つ出てこない日があってもOKです。
最初は出てこない日もあるかもしれません。
そんな時は、お母さんのベスト3を楽しそうにお話して下さいね。
お母さんが楽しそうに話していると、子どもは今日はお母さんに何を話そうかな?と考えながら1日を過ごすようになります。
慣れてきたら、そう思った理由や感想を聞いたり、お話をするとより楽しめますよ。

いかがでしたか?
4歳児は自分の限界に気づかないくらい、毎日精一杯頑張っています。
頑張っているところを認めて欲しいって思っています。
だからこそ、お母さんとの安心できる時間が、ストレスの受け皿を大きくするカギになります。
癇癪がもっと酷くなる前に、リラックスタイムの「ヒーロー&プリンセス自慢」を取り入れてみてくださいね。
お母さんと一緒にホッとする時間ができると、子どもの安心して、表情や気持ちに変化が現れてくるはずですよ!
癇癪が起きた時の具体的な対応方法が分かります▼
特性に合わせた癇癪対応が丁寧に解説してあります▼
一人ではどうにもならない子育ての悩みを一緒に解決していきましょう!
執筆者:福原かおり
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)