3歳の子どもが思い通りにならないと癇癪を起こし、泣き叫ぶ姿に限界を感じていませんか?成長の証とわかっていても、「このままで大丈夫?」と不安になりますよね。この記事では、泣き叫ぶ癇癪にも焦らず向き合えるようになる対応法をご紹介します。
【目次】
1.3歳の思い通りにならないと癇癪を起こす理由
2.泣き叫ぶ癇癪にはどう対応するのが良いの?
3.待つがカギ!癇癪を笑顔に変える関わり方
1.3歳の思い通りにならないと癇癪を起こす理由
3歳の子どもが思い通りにならないと癇癪を起こし、泣き叫ぶ姿に戸惑っていませんか?
まるで予測不能な爆弾のように、いつどこで感情が爆発するかわからず、お母さんも気が気でなくなってしまいますよね。
癇癪は、お母さんの対応を変えることで落ち着かせることが可能です。
床に寝転がって暴れたり、おもちゃを投げつけたり、急に走り出したり……。
3歳の癇癪は激しく、体力も精神力も削られます。
そして、ハッとするのが、急に走り出して物陰に隠れようとする行動。
「一体何がしたいの?」と戸惑うと同時に、危険がないか安全面の心配も募りますよね。

3歳は、自我がぐんぐん成長して「自分でやりたい!」「僕の思い通りにしたい!」という気持ちが、体中で渦巻いている時期なんです。
でも、その気持ちを上手に言葉にしたり、コントロールしたりする力は、まだまだ発達の途中です。
癇癪はお子さんなりに一生懸命自分の気持ちを表現しようとしているサインなのです。
頭の中では、「〇〇したいのに!」「なんでできないの!」という強い感情が渦巻き、まるで大洪水のように溢れ出している状態です。
泣き叫ぶ声は、その心の叫びです。
暴れる手足は、どうにもならないもどかしさの表現です。
そして、物陰に隠れようとするのは、自分だけの安全な場所で、押し寄せる感情の波と戦おうとしているのかもしれません。
このように、子どもが自分の中では抱えきれない負の感情を、暴れたり、ぐずったりして感情を爆発させることで問題解決しようとしているのです。
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.癇癪にはどう対応するのが良いの?
毎回全力で向き合って、気づけば親の方が泣きたくなっている…そんな経験はありませんか?
子どもの気持ちをわかってあげたい。でも、毎回のように泣き叫ばれると、こっちも余裕がなくなってしまいますよね。
3歳の思い通りにならないと癇癪を起こすとき、子どもの感情に巻き込まれず「見守る姿勢」が大切です。
なぜなら、泣き叫ぶ癇癪の時に大声で叱ったり、無理やり引き離そうとしたりすると、追い打ちをかけるようなものなのです。
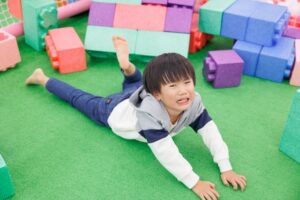
お母さんが取り合うことで、「お母さんがこっちを見てくれている!」と、さらに反抗しようという気持ちを強くさせてしまうんですね。
癇癪が強くなればなるほど、どんなに声をかけても「お母さんもわかってくれない!」という気持ちが加わり子どもはますます怒り、癇癪が長引く原因になります。
このように、3歳が泣き叫ぶ癇癪のときに親が同じ土俵に立ってしまうと、悪循環が生まれてしまうのです。
だからこそ、冷静に、巻き込まれず、見守る姿勢を意識しましょう。
とはいえ、実際に泣き叫んだり暴れたり、ときには走り出してしまうなど、外で癇癪を起こされたら冷静に対応するのは難しいですよね。
次の章では、安全を守りながら癇癪を笑顔に変える対応法をご紹介します。
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
3.待つがカギ!癇癪を笑顔に変える関わり方
3歳の癇癪には、まず「安全の確保」と、「気持ちに寄り添う姿勢」が大切です。
まるで嵐が過ぎ去るのを静かに待つように、子どもの感情が落ち着くのを待ちましょう。
取り合わずに待つことは、子どもを良い行動へと導くために欠かせません。
まずは安全確保から始めます。
室内であれば、危険なものをどけて、子どもが怪我をしないよう見守ります。
外出先であれば、場所を移動して見えるものを変えることで、癇癪が落ち着くことがあります。
泣き叫び走り出す子や、物陰に隠れようとする子には、「安心できる物」を用意しておくと良いでしょう。
私の息子の場合は、大人の上着が役立ちました。
普段から上着の中に隠れて遊んでいたため、「安心できる場所」という認識があったようです。
そのため、外で癇癪を起こした時は、上着に隠れて落ち着くようになりました。
待つ間は、ため息をついたり、大きな音を立てたり、顔をこわばらせたりせず、否定的な感情を示さないように心がけましょう。

そして、褒める準備をします。
子どもが泣きながらでも、次の行動を始めたらすぐに褒めましょう。
癇癪が日常的だった子は、お母さんが反応してくれないことに慣れず、最初は癇癪が激しくなるかもしれません。
しかし、「次の行動をすれば褒めてくれる」と理解すようになるので、根気強く接してください。
「泣き止んだね」「立ち上がったね」など、小さな変化にも声をかけてあげることで、次第に行動で気持ちを伝えることができるようになります。
そして、「悲しかったね」「悔しかったね」と気持ちを代弁してあげることで、子どもは「気持ちを言葉で伝える」練習になります。
このように対応を続けていくと、息子は思い通りにならなかったときの気持ちを癇癪ではなく、言葉で伝えてくれる事ができるようになりました。
3歳の癇癪は成長の一歩。
焦らず、シンプルに「待つ」「受け止める」「褒める」を繰り返して、癇癪を笑顔に変えていきましょう。
▼▼子供の癇癪が限界!と感じてるママにおすすめの記事はこちら▼▼
子どもの癇癪に困り果てているママ!対応策をご紹介しています!
執筆者:かねた 愛
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)
(発達科学コミュニケーションアンバサダー)






