| 発達障害ADHD・グレーゾーンの子どもは、誤解を受けやすく、お友達関係をつくっていくことが苦手でトラブルも起きやすい。どうして、お友達とうまくいかないの?と悩んでいるお母さんもいらっしゃると思います。おうちでできる解決法をお伝えします。 |
【目次】
1.このままでは孤立したり、いじめられたりするのではないか…
2.発達障害ADHD・グレーゾーンの子どものお友達トラブルが多い理由はこれ!
3.さらに悪化させてしてしまう要因も!?
4.お友達と仲良く遊ぶための3つのステップ!
①ルールを決める
②子どもが話しやすい環境を作る
③今後の対応策を一緒に考える
1.このままでは孤立したり、いじめられたりするのではないか…
うちの子、お友達とうまくいかないみたい… そんなお悩みを持っていませんか?
私には、発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)グレーゾーンの7歳の娘がいます。娘は人が大好きで、人なつっこい性格。
お友達とも仲良くしたいので、積極的に関わろうとするのですが、本人の気持ちとは裏腹に、お友達とトラブルになることが多く、落ち込んだり、イライラしたりする姿が家でもよく見られていました。
お友達との関係がうまくいかないことで、
「『〇〇ちゃんとはもう一緒に帰りたくない!』って、言われちゃった。」
「どうしてみんな私のこと嫌いっていうの?」
と聞かれたりもしました。
子どもも自分で何とかしたいと強く思っているのですが、どうしてもお友達と上手く関係を築けません。

このままでは孤立したり、いじめられたりしてしまうのではないか。そんなことが私の頭をよぎるようになりました。
わが子がひとりでいる姿を見ると、お母さんとしては、とても不安な気持ちになりますよね。
2.発達障害ADHD・グレーゾーンの子どものお友達トラブルが多い理由はこれ!
では、どうして発達障害・ADHDグレーゾーンの子どもは、お友達関係がうまくいかないのでしょうか?
ADHDの特性に多動性と衝動性があります。
多動性がある子は、じっとしているのが苦手です。
無意識のうちにも体が動いてしまうので、落ち着きがない、動きが激しい、といった印象を与えてしまいます。
衝動性があると、考える前に行動してしまうので、気になることがあると、ぱっと手が出てしまう、という状況にもなります。
元気で活発、明るくて行動力があるというのは、素晴らしいADHDの特性です。
ですが、感情のおもむくままに行動してしまうので、周囲から浮いてしまい、ちょっと変わった子と思われてしまいがちです。
本来の子どもの良さも度を超えてしまうと適応が難しくなってしまいます。
発達障害・グレーゾーンの特性は、自分の努力や根性では克服することができません。
娘は、力加減がわかりにくく、力が強すぎてしまうという特性もありました。
そのため、お友だちにぶつかって痛い思いをさせてしまったり、お友だちに近づくときの勢いが強すぎて、相手が転んでしまったりすることもありました。

これでは、本人がみんなと仲良くしたい、と思ってしている行動だったとしても、お友達からは「あの子とはもう遊びたくない」と思われてしまいますよね。
そのため「お友達が嫌がることをする乱暴な子」という誤解をされ、お友達とトラブルを起こしてしまうのです。
3.さらに悪化させてしまう要因も!?
トラブルが起きてしまったときや、本人が困ったときに、言葉で気持ちを伝えることができれば良いのですが、発達障害・グレーゾーンの子どものなかには、自分の気持ちを言葉で伝えることが苦手な子が多く見られます。
言葉で伝えられないと、悪態をついたり、手が出てしまったりすることもあります。
こうなると、お友達との関係はさらにうまくいかず、悪循環となってしまいます。

ではどうしたら、お友達と仲良く遊べるようになるのでしょうか?その方法をお伝えしたいと思います。
4、お友達と仲良く遊ぶための3ステップ!
発達障害ADHD・グレーゾーンの子どもは人好きな子が多いです。問題と思われる行動も悪気があってしているわけではありません。
落ち着いて行動できるようになると、トラブルはグっと減ります。
我が家で実践した3ステップ解決法をご紹介します。
◆ルールを決める
①お友達に近づくときは、そーっと行く
②「やめて」と言われたらもうやらない
③嫌なことをされたら「やめて」と言葉で伝える
ポイントは、短く具体的に教えることです。
発達障害・グレーゾーンの子どもは、特性をなくすことはできませんが、ルールを理解できると意外と守ろうとするものです。
また、家でも①~③の行動ができたときに、
「やめてくれてありがとう!!」
「そのくらいのスピードで近くに来てくれたら安心」
など肯定の声かけをしていくと、その行動は定着しやすくなります。
言葉で気持ちを伝えることが苦手なお子さんの場合は、③をルールに入れてあげると効果的ですよ。
◆子どもが話しやすい環境を作る
子どもも大人もそうですが、うまくいかなかったこと、失敗したことを話すのはとても勇気のいることです。
気持ちを言葉で伝えることが苦手な発達障害・グレーゾーンのお子さまは特に話したがらないと思います。
話したがらないときは、無理に聞き出そうとはせず、子どもが話してくれるのをじっと待ってあげてください。
私は「おかえり!学校どうだった?」 と、一言だけ声をかけて、その後はただ待ちました。
子どもが話してくれたら、
・できたことはたくさん褒める
・できなかったことは「話してくれてありがとう」と話してくれたことを褒める
を繰り返します。
話すだけでも気持ちはスッキリします。
子どもは話したら「叱られるかもしれない」と思っているのに、話したことで「褒めてもらえた」となれば、また話したくなりますよね。
娘は、帰宅すると学校での出来事を良いことも悪いこともたくさん話してくれるようになりました。
◆今後の対応策を一緒に考える
お子さんが話してくれるようになったら、チャンス到来!!
お子さんに、トラブルになってしまったことに対して、「次はどうしたらいいかな」と一緒に対応策を考えます。
考えられると、行動は変化します。すると、お友達とうまくいかない状況は確実に良くなっていきました。

今では、娘は、
「今日はみんなと仲良くできたよ」
「〇〇ちゃんに、やさしいね、って言われたよ」
「今日は〇〇くんに手が当たっちゃったけど、すぐに謝ったよ」
と、うれしい報告をたくさん聞かせてくれるようになり、お友達と楽しく過ごしています。
ADHDタイプの子どものお友達トラブルに悩んでいるお母さんはぜひ、この3つのステップを参考に親子のコミュニケーションを整えてみてください。
親子のコミュニケーションが良くなると、発達障害・グレーゾーンの子どもはどんどん成長します。
お母さんの心配が少しでも軽減されますように。応援しています!
▼▼お友達と仲良く遊べるようになる方法を知りたい方はこちら ▼▼
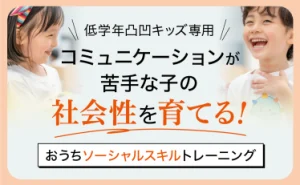
お友達関係が良くなる対応を多数紹介しています!
執筆者:杉山かずみ
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





